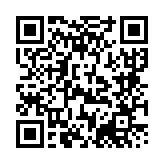|
最新更新日:2024/05/30 |
|
本日: 昨日:15 総数:62842 |
【電話】042-341-0008(平日8:00頃〜17:30頃)
【E-mail】gakkou@01.kodaira.ed.jp(24時間)
3年体育 ハンドベースボール

どうやって打てば遠くまでボールをとばせるのか、みんなで考えながら取り組んでいます。 10月30日(金)の給食





明日はハロウィンです。 日本では十数年前から、ハロウィンの仮装をして、パーティーをするイベントが、あちこちで行われるようになりましたが、もともとは秋の収穫をお祝いして悪霊をおいはらうお祭りです。 ハロウィンでは、かぼちゃをくりぬいた「ジャック・オー・ランタン」を玄関先に飾ったり、子どもたちが「トリック・オア・トリート(おかしをくれなきゃ、いたずらするぞ)」と言いながら、近くの家を訪ねておかしをもらったりする風習があります。 給食では、かぼちゃを使ったプリンを作りました。 かぼちゃの味が濃厚でおいしいプリンです。 「スパゲティトマトきのこソース」は、旬のきのこを使いました。 きのこが苦手な子が多いですが、今日はどのクラスもおかわりする人がたくさんいました。 「ごぼうのカリカリサラダ」は、ささがきに切ったごぼうをカリカリに素揚げして、サラダにトッピングしました。 シャキシャキした野菜にカリカリの食感が加わり、野菜が苦手な人にも食べやすい味です。 今日は、図書委員の児童が「おなかのなかで」を読み聞かせしました。 そのあと、今の季節にぴったりな「しきしきむらのあき」を副校長先生が読み聞かせしました。 秋の情景が描かれている本で、挿絵を紹介しながら読み聞かせしてくださいました。 「広げよう、元気のわ!やさいのわ!」絵の展示のお知らせ

みなさんが応募した「野菜が食べたくなる絵」の中で審査に通過したものが展示されます。 展示される方には個別にお知らせをお渡ししています。 一小の子どもたちの絵もたくさん展示されます。 おどもだちが描いた素敵な絵をぜひご覧ください。 ★期間:令和2年12月12日(土)〜18日(金) ※14日(月)は休館です。 ※日にちにより展示時間が異なります。 詳細は添付ファイルでご確認ください。 ★場所:小平市中央公民館 1階プロムナード (小平市小川町2−1325) ★ご案内添付ファイル 「広げよう、元気のわ!やさいのわ!」絵の展示のお知らせ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら今年度は「みんなの健康展」は行いません。 ご来場の際はご自宅で検温、マスク着用の上、体調不良の方は来場をお控えください。 10月29日(木)の給食





今日は「十三夜」です。 10月1日の十五夜に引き続き、きれいなお月様を眺める日です。 十五夜と十三夜を合わせて「二夜の月(ふたよのつき)」と呼びます。 十五夜のお月様だけを見ることを「片見月」といい、縁起が悪いこととされています。 今夜、十三夜のお月様も眺めてみましょう! 十三夜は新月から数えて13日目の夜なので、満月には少し欠ける月です。 十五夜の次に美しい月といわれています。 十三夜は秋の収穫に感謝をしながら月をめでる日です。 「栗名月」「豆名月」ともいわれ、栗や豆ををお供えしたり、食べたりします。 給食でも行事食として「栗ごはん」と、大豆を使った「呉汁」を作りました。 真ん中の写真は、栗ごはんが炊き上がったところです。 一番下の写真は、煮てすりつぶした大豆を汁に加えているところです。 栗は秋の味覚ですね。 栗の歴史はとても古く、縄文時代の遺跡からも出土しています。 平安時代には栽培もされていました。 今日は、栗が出てくるお話「さんまいのおふだ」と、明日の給食「かぼちゃプリン」にちなみ「おおきなかぼちゃ」を石井先生が読み聞かせしました。 10月28日(水)の給食





「きな粉豆乳トースト」は、きな粉と豆乳と砂糖を溶いた液に食パンを浸して、オーブンで焼いたものです。 真ん中の写真は、パンを豆乳液に浸しているところです。 フレンチトーストに似ていますが、牛乳や卵、バターは使っていません。 豆乳が苦手な人も食べやすい味で、子どもたちに大好評でした。 大豆製品をたっぷり使ったメニューですね。 「きな粉豆乳トースト」は簡単に作ることができるので、ぜひご家庭でも試してみてください。 ≪作り方≫ ※食パン1枚分の分量です。 1.人肌に温めた豆乳(大さじ2)にきな粉(小さじ1弱)と砂糖(小さじ1強)を加えて混ぜる。 2.食パンの両面を1の豆乳液に浸し、オーブンで焼く(フライパンで焼いてもOK)。 「大根のクリームシチュー」の大根は、小平産のものを使用しました。 みずみずしく甘い大根でした。 大根は軟らかく煮てあるので、シチューと一緒に口に入れるととろける味わいです。 給食のシチューのルゥは、油とバターで小麦粉を炒めて手作りしています。 市販のものとは一味違い、コクがあり優しい味です。 シチューを作っている様子は、一番下の写真をご覧ください。 シチューもおかわりの列ができるほど大人気でした。 今日は、図書委員の児童が「ちいさいきみとおおきいぼく」を読み聞かせしました。 そのあと、今日の「きな粉豆乳トースト」にちなみ、いろいろなパンが登場する本「たのしいパンのくに」を副校長先生が読み聞かせしました。 絵本に出てくる絵の情景を紹介しながら読んでくださいました。 10月27日(火)の給食





今日は、「5年2組のリクエスト給食」です! 「ビビンバ」と「フライドポテト」をリクエストしてくれました! 「ビビンバ」は、日本のおとなりの国、韓国の料理です。 韓国では「ピビムパプ」といいます。 「ピビム」が「混ぜる」という意味、「パプ」は、「ごはん」のことです。 キムチとともに、今では日本でもだれもが知っているくらい、有名な料理ですね。 給食の「ビビンバ」はごはんと肉、野菜を別出しにして、教室でごはんの上に肉と野菜を盛り付け、各自で混ぜながら食べていたのですが、コロナ対策で配膳の数を減らすため、今日はごはんと肉をあらかじめ給食室で混ぜ合わせてから提供しました。 炒めて調味した豚肉を炊きあがったごはんに混ぜ合わせました。 野菜は茹でて冷まし、みそだれを上にのせて別配缶しました。 (野菜を茹でている様子は、真ん中の写真をご覧ください。) たっぷりの野菜ですが、みそだれの味が効いています。 ふだんはほうれん草が苦手で食べられなかった子も、「今日のほうれん草は甘くておいしかった!」と完食していました。 「フライドポテト」はじゃがいもを拍子切りにし、素揚げしたあとに塩をまぶしています。 全校分で52kgのじゃがいもを使いました。 じゃがいもは洗ってから皮をむいて、芽取りをし、包丁で切るので、意外に手間がかかります。 一度に大量には揚げられず、揚げ時間も長いので、簡単そうに見えて時間のかかる料理です。 (揚げている様子は一番下の写真をご覧ください。) でも、やはり冷凍のものとは違い、生のじゃがいもを使ったフライドポテトはおいしいですね。 「フライドポテト」はどのクラスも大人気でした! 「フライドポテトをおかわりしたい人」と先生が声をかけると、クラスのほとんどの子が手を挙げて猛アピールです。 ほんの一口ずつですが、先生方が上手におかわりを希望する子たちへ分けていました。 今日は「フライドポテト」に関連して、「せかいでさいしょのポテトチップス」を石井先生が読み聞かせしました。 世界で一番最初にポテトチップスを作った人のお話で、実話です。 2冊目は「ぶたのたね」を読みました。 【2年生】町たんけんに行こう!
11月13日(金)に予定されている町たんけんに向けて準備を進めています。






6年 家庭科 マイバック作り





手縫いをしたりミシンを上手に使ったりして、丁寧に作業をすすめています。 もうすぐで仕上げです。完成が楽しみですね。 1年生 生活科見学 10月22日(木)
生活科見学へ行ってきました。
保護者の方々におかれましては持ち物やリュックの準備をありがとうございました。 出発前は曇りでしたが、徐々に晴天に恵まれました。子どもたちはお山、林、アスレチックを学級に分かれて回り、それぞれでドングリ、葉などの秋のものを拾ったり、しおりの絵と同じ秋のものを見つけてシールを張ったりしました。子どもたちは楽しく活動し、全員無事に学校へ帰ってくることができました。 





10月26日(月)の給食





今日、10月26日は「柿の日」です。 明治28年のこの日、俳人の正岡子規が奈良旅行へ出発し「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の句を詠んだとされることから、この日が記念日になりました。 柿が旬の季節ですね。 今日の給食では、小平産の柿を使っています。 甘くておいしい柿でした。 真ん中の写真をご覧ください。 小平ではたくさんの野菜が作られていますが、果物もたくさん栽培されています。 ぶどう、梨、柿、ブルーベリーなど、どれもおいしいですね。 柿は、ヘタを皮をむかないと食べられませんね。 今日は全校分で92個の柿を使ったので、なかなか大変な作業です。 調理員さんは包丁を使って一つずつ丁寧に皮をむきました。 一番下の写真をご覧ください。 「柿」がでてくる昔話といえば「さるかにがっせん」ですね。 石井先生が読み聞かせしました。 2冊目は「エドワルドせかいでいちばんおぞましいおとこのこ」を読みました。 2年生遠足〜特別号その2〜





ありがとうございました! 2年生遠足〜特別号その1〜
先週、16日(金)に東村山中央公園まで歩いて行ってきました。
当日の様子をもう少し詳しくお伝えします。 40分程の道のりを歩き、公園に着いてからは班ごとに分かれてスタンプラリーをしました。 風船バレーや片足バランス、森の美術館のお題では「橋本館長(校長)の顔」や「食べたいと思うお昼ご飯」を班ごとに作ってもらいました。どの班も素敵な力作が出来上がりました! クラスごとに分かれておいしいお昼ご飯を食べた後、クラス遊びをしました。 どのクラスもいつもとは違う原っぱの上で、とても楽しく過ごすことができました。 帰りは少し疲れた様子が見られましたが、最後まで頑張って歩いていました。 





10月23日(金)の給食





今日のコロッケは旬のさといもを使って作りました。 じゃがいもで作るコロッケとは一味違い、さといも特有のねっとりとした食感がおいしいですね。 使ったさといもは、もちろん小平産です。 付け合わせのキャベツも小平産です。 給食のコロッケは冷凍食品を使用せず、いもを蒸してつぶして成形し、衣をつけて、油で揚げ、手作りしています。 成形している様子は、真ん中の写真をご覧ください。 全校分、約540個も作るのは、とても大変な作業です。 コロッケは油で揚げるときに爆発しやすいので、注意して作業しました。 一番下の写真はコロッケを油で揚げているところです。 今日は図書委員の児童が「ぼくのニセモノをつくるには」を読み聞かせしました。 そのあと、今日のメニューにちなみ「コロッケです。」を副校長先生が読みました。 コロッケがいろいろなところへ転がっていく本で、子どもたちは想像力を膨らまし、ニコニコ笑顔になりながら聞いていました。 10月22日(木)の給食





今日は、「5年1組のリクエスト給食」です! 「カルボナーラ」と「パンケーキ」をリクエストしてくれました! 「カルボナーラ」は「フェトチーネ」という幅広のパスタを合わせました。 いつもは乾燥パスタですが、今日のフェトチーネは生パスタです。 生パスタはモチモチした食感があり、ソースとよくからんでおいしいですね。 真ん中の写真はフェトチーネを茹でているところです。 大きなお釜で茹でます。 量が多いので、2回に分けて茹でました。 「ミニパンケーキ」は新メニューです! 生地をカップに入れて焼き、メープルシロップをかけました。 下の写真はケーキ生地をカップに流しているところです。 今日の読み聞かせは副校長先生が行いました。 まずは昨日読み聞かせした「もったいないばあさんのいただきます」をふり返り、あとがきに書いてある食べ物の大切さや食べ物への感謝の気持ちについてお話しました。 今日のメニューの食材にあわせながら、それぞれの食べ物に含まれる栄養、いろいろな食べ物をバランスよく食べることで元気に過ごせることを伝えました。 食育は生きる上での基本であり、知育、徳育、体育の基礎となるものです。 子どもたちに食の大切さを繰り返し伝えていきたいと思います。 次に、今日のメニューの「ミニパンケーキ」に関連して、「ルルとララのホットケーキ」を紹介しました。 「ルルとララのホットケーキ」にはいろいろな種類のホットケーキが載っています。 作り方がくわしく書かれているので、ぜひ読んでみてくださいね。 10月21日(水)の給食





スロッピージョーは、ミートソースのような具をパンにはさんで食べる料理で、アメリカのアイオワ州の郷土料理です。 今日の給食は、コッペパンの断面にミートソースを塗って、オーブンで焼きました。 スロッピージョーの「スロッピー」には、「汚れた」「だらしない」という意味があります。 食べるときにミートソースで口のまわりを汚してしまうことから、この名前がつけられたともいわれています。 そのほかにも、ジョーという名前の人が初めて作ったことが名前の由来という説もあります。 デザートは、旬のさつまいもを使って「スイートポテト」を作りました。 小平産のさつまいもを使いました。 大きくて甘く、ほくほくしたさつまいもでした。 今日は、アメリカ料理「スロッピージョー」にちなみ、アメリカの昔話「夢の望み」の読み聞かせCDを流しました。 そのあと、先週の「世界食糧デー」「食品ロス」の話をふり返り、「もったいないばあさん」「もったいないばあさんのいただきます」を副校長先生が読みました。 「もったいない気持ち」「食べ物やものを大切にする心」がストレートに伝わってくるお話で、あとがきにも素晴らしいことが書かれています。 「いただきます」は食べ物の命、料理を作ってくれた人への感謝の言葉。 食事の最後は「ごちそうさま!」…いただいた命と作ってくれた人への感謝をこめて。 私たちは生きていくために、いろいろなものの命をいただいていること。 食べ物にはそれぞれ役割があるため、気持ちよく毎日をすごし、元気に大きく育つためには、いろいろな食べ物をバランスよく食べることが大切であること。 すきなものばかり食べていてはもったいない。 すききらいせずに、残さないように、ありがたくいただきましょう! といった内容が書かれています。 感謝の気持ちを忘れずに、食べ物を大切にしていきたいですね。 【5年生】食育授業・お米の脱穀、籾摺りをしました!





各クラス2時間ずつの授業で、夢の広場で行いました。 6月2日に田植え、夏の間は水やりでお世話をし、10月2日に稲刈り、その後乾燥させて、いよいよ今日は脱穀、もみ摺りです。 はじめに栄養士から「お米の品種」「米の消費量が減っていること」「米離れの問題点」「お茶碗1杯のごはんを作るにはどれくらいの稲が必要なのか」などについて、パワーポイントを使ってお話しました。 はたして、5年生が育てた稲はどれくらいの収穫となるのか…。 一人お茶碗1杯食べられるのか、それともスプーン1杯か。 稲刈りのころは「お茶碗1杯ある!」と自信満々の子どもたちでしたが、話を聞けば聞くほど、稲を見れば見るほど自信を無くす様子…。 プロが育てた稲と自分たちが育てた稲を見比べると、「やはりプロはさすがだなぁ!」と驚く子どもたちですが、大切に育てたお米を無駄にしないよう、一粒一粒を大切に脱穀ともみ摺りをしました。 脱穀した稲をすり鉢の中に入れて、野球のボールでゴリゴリとすりつぶします。 するともみが外れて、玄米が見えてきます。 うぉ〜!と感動する子どもたち。 うちわを仰いでもみを飛ばしていきます。 本来なら息を吹きかけてもみを飛ばすのですが、今年はコロナ対策でできません。 うちわで飛ばすのは難航しましたが、徐々にコツをつかんでいきました。 「少しでも多く収穫を得るために!」「少しでも多く食べられるように!」と子どもたちは頑張りました。 「まだここに米が残ってるよ」と捨てる前にチェックをしながら、一粒一粒の重みを感じました。 なんとか時間ぎりぎりで脱穀、籾摺り、後片付け(掃除)を終え、次は食べられる日を待つばかりです。 収穫したお米の量は2クラス合わせて「1.18kg」でした。 カップでいえば8合弱、一人当たりに計算すると17gです。 炊飯すると2.2〜2.3倍に増えるので、予想される食べられる量は一人当たり40g弱といったところでしょうか。 ここまでの体験を通して、改めて農家の方の大変さ、食べ物のありがたさを感じることができました。 自分たちで作ったお米、きっと最高の味になることでしょう! 10月20日(火)の給食





もうすぐ、木々の葉っぱが赤や黄色に色づく季節ですね。 特にもみじは真っ赤に色づき、きれいですね。 今日の給食は、もみじの形に切ったにんじんをかざった「もみじごはん」を作りました。 もみじの形のにんじんはどのように作ったのかというと、まずにんじんをもみじ型で型抜きをし、それを薄くスライスして、だし汁に薄口しょうゆを加えた物でやわらかく煮ました(真ん中の写真はにんじんを煮ているところです)。 今日は久しぶりのすがすがしい秋晴れで、気持ちの良いお天気でしたね。 秋の季節を楽しみましょう。 汁物の「みみ汁」は山梨県の郷土料理で、小麦粉を練ったものを一口大にし、野菜と一緒にみそ味で煮込んだ料理です。 「みみ汁」の「みみ」という呼び名の由来は、「耳の形に似ている」「農具の箕の形に似ている」などといわれています。 給食の「みみ」も、もちろん手作りです。 小麦粉を練って生地を作り、それを綿棒でのばして、包丁で三角形に切りました。 それを下茹でしてから、汁の中へ加えています。 一番下の写真は「みみ」を下茹でしているところです。 今日は秋が旬の「鮭」を使って、おろし炊きを作りました。 下味をつけた鮭に粉をふって油で揚げ、大根おろしのたれをかけました。 今日のメニューの「鮭」にあわせて、石井先生が「さけがよんひき」「かえってきたさけ」の本を読み聞かせしました。 「かえってきたさけ」は、鮭の一生をわかりやすく書いた絵本です。 10月19日(月)の給食





「給食DE世界旅行」第四弾は、「アフリカ料理」です。 全て新メニューです! アフリカは54の国と一つの地域からなる大陸で、人類が生まれた土地といわれています。 「ジョロフライス」は、西アフリカ各地で作られているアフリカ式の炊き込みご飯です。 牛肉や羊肉、鶏肉、魚介類などを使います。(今日の給食では鶏肉を使いました。) トマト風味のスパイスの効いた味付けです。 「カランガ」は主にケニアで作られているトマト煮込み料理で、ピラウ(ピラフ)に添えて食べます。 じゃがいもが入っていない料理は「ンコンベ」といいます。 「クスクスのサラダ」に使われている「クスクス」とはパスタの一種で、世界一小さいパスタとして知られています。 サラダのほか、主食として食べることもあります。 「マンダジ」は、食事にもおやつにもなる揚げパンです。 ココナッツミルクやスパイスを入れたものもあります。 食べなれないアフリカ料理でしたが、給食後に児童と廊下ですれ違うたびに「今日の給食、おいしかったです!」と声をかけられました。 「クスクスはどうだった?」と聞くと、 「クスクスがおいしかったので、また出してください。」 「クスクスはちょっと苦手だった。食感が…。」 「クスクスは初めて食べたけれど、おいしかったです。」 などの感想が聞かれました。 食の体験を増やすことができ、良かったです。 今日はメニューにあわせて、アフリカのお話「くいしんぼうのシマウマ」を石井先生が読みま聞かせしました。 2冊目は読書週間の親子読書におすすめな本「だいすきひゃっかい」を読みました。 5年 社会科見学





【2年生】遠足に行ってきました!
朝は肌寒さが残っていましたが、晴れ間ものぞき、絶好の遠足日和になりました。
スタンプラリーをしたり、クラス遊びを楽しみました。 おいしいお弁当をありがとうございました。 



|
小平市立小平第一小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目1082番地 TEL:042-341-0008 FAX:042-341-0052 |