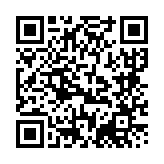|
最新更新日:2026/01/23 |
|
本日: 昨日:26 総数:118023 |
図書委員会による読み聞かせ



7月1日(金)の給食





今日は旬の「とうがん」を使ってスープを作りました。 「とうがん」は漢字で書くと「冬」の「瓜」と書きますが、旬は夏です。 そのまま冷暗所で保管しておけば冬までもつことから、「冬瓜」と記すようになったといわれています。 やわらかくとろっとした食感でおいしいですね。 真ん中の写真は、「冬瓜スープ」を作っているところです。 「チャプチェ」は韓国料理で、春雨の炒めものです。 今日の給食のようにチャプチェをごはんの上に盛ったものは「チャプチェパプ」といいます。 一番下の写真は、「チャプチェ」を炒めているところです。 「ちゃぷちぇどんがおいしかったです。」 「スイカがつめたくて、おいしかったです。」 などの感想が書かれていました。 収穫が始まりました(2年生) 7月1日
学級園に植えた野菜が実をつけて、2年生が収穫です。とうもろこしはもう少し時間がかかりそうですが、今日はなす、えだ豆が収穫されました。枝豆は根本から抜いて、後で実を外します。何人かが収穫した野菜を見せてくれました。




考えは色分けして(3年生)



タブレットに慣れる(1年生) 7月1日



かざりつけ(全学年) 7月1日



6月30日(木)の給食





「水無月」は京都の郷土料理で、6月30日に食べる行事食です。 一年の半分が終わる6月30日に、この半年の厄をはらい、残りの半年の無病息災を願って食べられています。 表面に飾られている小豆は、魔よけの意味があると言われています。 今日の給食ではカップに入れて作りましたが、本来は三角形に切り分けた料理で、暑さをしのぐ氷を表しているともいわれています。 真ん中の写真は、「水無月」の材料をカップに入れているところです。 生地を一度蒸してから、あずきの層を流して、もう一度蒸しました。 「水無月」にあわせて、今日は京都の郷土料理を作りました。 「まつぶた寿司」は、京都の丹後地方で、お祝いのときに食べる料理です。 「まつぶた」とは、もちを入れる細長く浅い箱のことで、この箱に寿司を敷き詰めて作ることから「まつぶた寿司」といわれています。 一番下の写真は、「まつぶた寿司」を配缶したところです。 「京風みそ汁」は、京都でよく使われている白みそ仕立てに作りました。 今日は全て新メニューです! 「おもちみたいで、とてもかわいいきゅうしょくでした。」 「新メニューがおいしかったです。いつもおいしいきゅうしょくありがとうございます。」 「まつぶたずしがおいしかったです。」 「水無月がモチモチでおいしかったです。またつくってください。」 などの感想が書かれていました。 七夕のかざりつけ 6月30日
先だって運び込まれた笹に、七夕の飾り付けを付ける作業が始まりました。ボランティアで作業に当たられた皆様、ありがとうございました。今年も子どもたちの願い事が、昇降口に飾られることになりました。今年はどんなお願い事が出てくるでしょうか。




【4年】習字



1.「あめかんむり」と「云」の大きさのバランス 2.「あめかんむり」のはね 3.「云」の「ム」 4.中心はどこか の4点について練習し、本番に臨みました。 多くの子が「今回は上手く書けた。」と納得していました。 夏の暑さで(1年生) 6月30日
1年生のアサガオの世話が続いていて、今日は肥料をまきました。このところの暑さで、夕方になるとほとんどの葉がしおれて元気がなくなってしまい、昨日は夕方にも水撒きをしました。一日1回の水では間に合わない暑さです。




動画撮影(3年生) 6月30日



展覧会にむけて



6月29日(水)の給食





カレーパンはふつう油で揚げますが、今日の給食ではオーブンで焼いて作りました。 あらかじめパン粉をオーブンで焼いて焼き色をつけました。 それをパンのまわりにまぶしてからもう一度オーブンで焼いています。 中にはさんであるカレーの具も給食室で手作りしました。 揚げたカレーパンとは一味違っておいしいです。 真ん中の写真は、パンの間にカレーの具をはさんでいるところです。 パンはカレー丸パンを使いました。 包丁で切れ目を入れて、具をはさみました。 今日の果物は「さくらんぼ」の予定でしたが、この暑さで変色などの痛みがあり、急遽「すいか」に変更させていただきました。 一番下の写真は「すいか」を配缶しているところです。 甘くて水分たっぷりで、暑い季節にはぴったりでした。 「カレーパンの具がおいしかったです!最高!」 「やきカレーパンがおいしかったです。」 「すいかがおいしかったです。」 などの感想が書かれていました。 こんなところにも 6月29日
今日の給食にはさくらんぼが出される予定でしたが、この暑さのため一部に変色などの傷みがん出ていることがわかりました。急遽、すいかを納品して献立が変更でした。栄養価に問題はありません。6月中の梅雨明けは、こんなところにも影響が出てしまいました。


国調べ(5年生) 6月29日
5年生は、自分ので一つの国を選び、生活や文化、人口や国土の面積などを調べ、プレゼンテーションを作って発表しています。タブレット端末の「スライド」という機能を使うと、簡単にプレゼンテーションを作ることができます。ギリシャ、中国、アメリカなど、自分の調べた国に関わる「情報を整理する」というのも、高学年ならではの学習内容です。情報を集めたり加工したりする技能を高めていくことも、ひとつのねらいです。


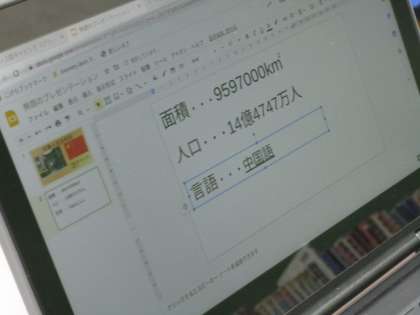

タブレットに加えて(3年生) 6月29日



先に視聴しました(6年生) 6月29日



社会 食材調べ!

まずは、自分たちの給食で使われている食材はどのようなものがあり、それはどのようなグループに分けられるのかを考えました。(例えば、米や小麦は「穀類」と呼ばれる等) 調べるときには、十三小のホームページに載っている「給食室から」のブログ記事をそれぞれが読みながら調べました。 【2年1組・食育】とうもろこしの皮むき





当日の給食に使うとうもろこし130本の皮をむきました。 生産者の加藤さんにゲストティーチャーに来ていただき、とうもろこしのお話を伺いました。 畑からとうもろこしの苗も持ってきてくださり、実物を見ることができました。 今日は朝4時から収穫をしてくださったそうで、朝取りのおいしいとうもろこしを味わうことができました。 今日使ったとうもろこしは、3月20日ごろに種をまいて、約3ヶ月で収穫を迎えたとのことです。 とうもろこしは肥料をたくさん使うこと、1本の苗に1つしか実がつかないことを教えていただきました。 とうもろこしを収穫した後の苗は、全て土に戻して、次に作付けする小松菜の栄養になるそうです。 お話を聞いた後はいよいよ皮むきスタート! 子どもたちは一生懸命、夢中になってむいていました。 ひげが残らないようにていねいにむきました。 中には「赤ちゃんのとうもろこしがいたよ!」と発見する子もいました。(一番下の写真) むいたあとは、部屋の掃除もていねいに行いました。 「とても楽しかった!」 「給食で食べるのが楽しみ!」との声がありました。 給食時間は、「おいしい!」「とても甘いよ」「おかわりしたよ」とニコニコ笑顔で食べていました。 旬の食材、小平産の野菜に触れる良い機会になりました。 6月28日(火)の給食





今日のとうもろこしは、小平市内の農家の加藤さんが育てたものです。 2年1組のみなさんが、1時間目に皮むきをしてくれました。 (皮むきの様子は次のブログ記事をご覧ください。) 加藤さんのとうもろこしは、甘みがあって粒がプチプチもちもちしていてとてもおいしいです。 子どもたちは「とうもろこし、おいしい!」と満面の笑みでした。 芯の部分につぶを残さないようにきれいに食べていました。 真ん中の写真は、とうもろこしを切っているところです。 一番下の写真は、蒸しあがったとうもろこしに塩をふっているところです。 「なすとトマトのスパゲティ」は新メニューです! なすを素揚げしてから、トマトソースの中へ加えました。 夏野菜をたっぷり味わえた給食でした。 「とうもろこしがあまくてすごくおいしかったです。」 「なすとトマトのスパゲティがおいしかった!」 などの感想が書かれていました。 |
小平市立小平第十三小学校
〒187-0035 住所:東京都小平市小川西町1丁目22番1号 TEL:042-342-1762 FAX:042-342-1763 |