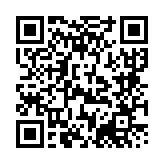|
最新更新日:2024/06/14 |
|
本日: 昨日:27 総数:63795 |
【電話】042-341-0008(平日8:00頃〜17:30頃)
【E-mail】gakkou@01.kodaira.ed.jp(24時間)
11月30日(火)の給食





ミニパンケーキは、給食室で手作りしました。 カップの中にケーキ生地を流し込み、オーブンで焼きました。 焼きあがったら、加熱したメープルシロップのソースをかけました。 真ん中の写真は、焼きあがったホットケーキにメープルシロップをかけているところです。 一つずつ、ていねいにかけました。 一番下の写真は、完成したミニパンケーキです。 ツヤツヤでおいしそうですね! 今日は、児童からリクエストされた本2冊を読み聞かせしました。 「おさるのジョージパンケーキをやく」、「ごめんねともだち」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 【5年図工】消しゴムはんこ作り





久しぶりの彫刻刀でしたが、安全に楽しく活動を行うことができました。 細かいところはカッターを使って模様をつけています。 できあがってはんこをおしてみるのが楽しみです。 11/29 朝会の話 凸凹





20211129 村松 きょうは漢字の勉強をしましょう。 これは記号ではありませんよ。なんと2つとも漢字なのです。なんと読むかわかりますか。難しいですね。これで「でこぼこ」と読むのです。 一文字ずつ見ていくと、「凸」という字は凸レンズなどというように、「とつ」と読みます。「凹」という字は、凹レンズというように「おう」と読んだり、「み」をつけて「くぼ(み)、へこ(み)」と読んだりします。 次は難しいですよ。この漢字の書き順はわかりますか。一筆書きのように書いてはだめです。ヒント1。漢字の書き順には大きな約束が2つあります。それは、「上から下へ」と「左から右へ」という2つです。このことがわかると、この漢字も書くことができます。ヒント2。「凸」も「凹」どちらも五画です。書き順を予想してみてください。時間は15秒。どうぞ。(15秒後)やめ、私が正解を書いてみますね。みんなの予想と同じでしたか。では、みんなで書いてみましょう。まずは「凸」から。声を出して「いち、に、さーん、しーい、ご」です。次は「凹」。「いーち、に、さん、しーい、ご」です。 みなさんは、6年生までに約1000の漢字を覚えますよ。漢字は集中してしっかり練習すると、すぐに覚えられます。また漢字には、いろいろな秘密もあるので、それも覚えるととても楽しくなります。 二学期が終わるまで一ヶ月もありませんが、学習に集中してくださいね。そして先生の言うことをよくきいて、一小のみんなは、さらに賢くなってくださいね。 これで朝会の話を終わります。 <裏面に「先生方へ」があります> <先生方へ> きょうは、学習についての話をしました。特に漢字に親しめればと考え、「凸凹」を題材にしてみました。教室でも、漢字の指導を日常的にしていると思いますが、興味や関心を高めるために、少し楽しい話題も取り入れてみてください。よろしくお願いいたします。漢字のネタなどで困るようでしたら、聞きに来てください。持ちネタは少ないですが、授業での活用などを教えますよ(^_^;)。 さて、漢字の指導では、「指書き→なぞり書き→写し書き」が基本です。(その中でも一番大切なのが指書きです。)書き順を確かめるために、最初に空中で書く「空書き(そらがき)」から入ることもあります。指書きのあとに確かめで空書きを入れるときもあります。空書きだけをやり、覚えたことにするのはダメです。机に指をしっかりとつけて書く「指書き」と、うまく組み合わせることです。指書きのポイントは、しっかり力を入れて、机を感じながら書かせることです。その後に目を閉じて指書きをさせ、書いた字が見えた気がすれば、覚えたことになります。 なぞり書きは鉛筆を使って行います。薄く書いてある漢字をはみ出さないようになぞって書くのです。ポイントは「はみ出さない」です。 最後は写し書きです。正しい漢字を見ながら書く、次に見ないで書く、これができれば合格です。なお、漢字の指導はテンポ良く、くどい説明をしないでやると効果的です。 さて、明日で11月が終わります。二学期の学習のまとめをする時期が来ます。成績付けは、とにかく計画が大事です。予定をしっかりと立て、それにそって進めましょう。学年会で歩調を合わせていくといいと思います。 最後に、今はコロナは落ち着いていますが、インフルエンザが流行するかもしれません。お互い免疫力を落とさないよう、栄養と睡眠を意識して、二学期末をのりきりましょう。 <参考:筆順あれこれ> 漢字の筆順については、内閣告示によって定められている常用漢字や現代仮名遣いとは違い、公的な基準は存在しません。唯一、公的な関与があるものとして挙げられるのが、60年以上前に出版された「筆順指導の手びき」と題する100ページ強の小型本です。 これは、1958年(昭和33年)に当時の文部省が小学校教師向けに作成した筆順指導の「マニュアル」です。筆順の大原則と、小学生に学ばせるよう指定した当時の教育漢字881字について、筆順を列記しています。 凸は教育漢字には含まれなかったので、筆順はこの手びきには載っていません。何かよりどころがあるとすれば、手びきに書いてある筆順の大原則だけです。凸の字は、原則の「上→下」「左→右」のどちらをとったらよいのか微妙です。どちらをとっても原則通りで、現在は、縦が先と横が先の2通りあるのです。 展示発表の準備
展示発表の準備をしていました。
写真は南校舎の西側階段1階部分、6年生有志による作品です。 製作から取付まで数日間をかけて有志の皆が協力して行っていました。 本日ついに完成! 分割して慎重に貼って、展示完了!! 階段を利用して展示しているので、角度によって見え方も微妙に異なります。 保護者会でご来校の際にぜひご覧ください。 





小平産大蔵だいこん(江戸東京野菜)





大蔵だいこんは江戸東京野菜のひとつです。 立派なだいこんが届きました! 11月29日(月)の給食





今日は、「4年2組のリクエスト給食」です! 「カレーライス」と「ジョア」をリクエストしてくれました!! どちらも、一小のみなさんに人気がある献立ですね! 真ん中の写真は、カレーを作っているところです。 給食のカレーはルウから手作りしているので、おいしいですね。 今日のサラダは、小平産の大蔵だいこんを使って作りました! 新メニューです。 大蔵だいこんは、17日に使った金町こかぶと同様に「江戸東京野菜」です。 大蔵だいこんの写真は次のブログ記事をご覧ください。 一番下の写真は、サラダの野菜を茹でているところです。 大蔵だいこんはシャキシャキとした食感でおいしかったです。 今日は「おばけのアッチ カレーライスはこわいぞ」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 11月26日(金)の給食





今日は旬のさといもを使って、コロッケを作りました。 使ったさといもは、もちろん小平産です。 さといもの独特のねばりが、いつものコロッケとは一味違ってまたおいしいですね! 給食のコロッケは、冷凍食品を使用せず、さといもを蒸してつぶして成形し、衣をつけて、油で揚げ、手作りしています。 真ん中の写真は、つぶしたさといもを成形して、衣をつけているところです。 一番下の写真は、コロッケを揚げているところです。 今日は、図書委員の児童が「トマトさん」を読み聞かせしました。 学校図書館ボランティアの皆様による飾り
学校図書館ボランティアの皆様による飾りです。
今回は、本校の開校記念日(12月8日)を前に、昔の学校や子供たちの学校生活をテーマに作ってくださっています。 保護者会や展示発表会の折に、図書館入口もぜひご覧ください。 学校図書館ボランティアの皆様、いつもありがとうございます。 

11月25日(木)の給食





「給食DE世界旅行」第六弾は、「スリナム料理」です。 スリナムは南アメリカの北東部に位置する国家です。 前回の「給食DE世界旅行」はオランダでしたが、スリナムはかつてオランダの統治下にあったこともあり、オランダとは関係の深い国です。 オランダにはスリナムから移民してきた人も多くいて、スリナム料理屋さんがたくさんあります。 スリナムはその歴史的背景から多民族国家で、他宗教な国家でもあります。 このため料理も多彩で、インドネシア、ジャワ島、イギリス、インド、中国、アフリカなどいろいろな国の料理が食べられていて、各国料理を混ぜ合わせたスリナムならではの料理もあります。 スリナムは人口の約2割がジャワ人です。 ジャワ人のインドネシア料理に大きく影響を受けていて、主食は米です。 スリナムの「ナシ」はインドネシアの「ナシゴレン」と同様のものです。 「サテ」もインドネシアなどの東南アジアでも食べられている料理で、日本の焼き鳥に似ていますがスパイスを使い、ピーナッツソースをかけることがあります。 今日の給食ではピーナッツのかわりに「ごま」を使ってソースを作りました。 真ん中の写真は、焼きあがった鶏肉にソースをからめているところです。 一番下の写真は、「サテ」を配缶したところです。 「サオトスープ」はジャワ料理で、ぐだくさんのチキンスープです。 オランダでも人気があります。 給食では、フライドポテトとフライドオニオン(もちろん給食室で作りました)をトッピングしました。 サクサクの食感がスープとあわさって絶妙な味です。 今日は「ちいさいいすのはなし」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 外壁工事が終わりました



長い間ご不便をおかけしましたが、これから自転車でご来校の際は以前のように理科室前に駐輪していただくことができるようになりました。 岩石園や昇降口周辺には、3年生が図工「私は色の博士」で3原色(青・赤・黄色)から作った色水の入ったペットボトルが並んでいます。 どれも作品です。決して誤って飲まないようにしてください。 11月24日(水)の給食





11月24日は、「和食の日」です。 「1124」を「いい日本食」と読む語呂合わせで、この日に決められました。 日本は、海、山、里と豊かな自然に恵まれ、四季折々の旬の食材、行事食、郷土料理、ごはんを中心とした栄養バンスの良い食事と世界に誇る食文化があります。 日本食離れが進んでいますが、日本人の伝統的な食文化について見直し、和食文化の大切さについて、あらためて考えてみましょう。 今日の給食は、ごはん、汁物におかずを組み合わせた和食です。 和食の味の基本は「だし」ですね! 給食では、さば節や昆布をつかって、ていねいにだしをとっています。 真ん中の写真は、だしをとっているところです。 一番下の写真は、五目汁を作っているところです。 給食の汁物は、だしの味がきいていておいしいです。 和食は世界中の人が注目している健康に良い食事です。 今こそ和食の良さを見直しましょう! ツナメルト



好評でしたので、作り方を掲載します。 ツナメルトはアメリカのホットサンドウィッチです。 これ一品で主食と主菜がセットになっているので、あとはサラダやスープを組み合わせれば簡単な朝食や昼食になります。 <材料(4人分)> 食パン4枚(厚さはお好みで) ツナ缶 100g キャベツ 1枚(40g) 玉ねぎ 1/4個(40g) 油 小さじ1/2 マヨネーズ 大さじ1+小さじ1 塩 少々 こしょう 少々 ピザ用チーズ 16g パン粉 大さじ2 <作り方> 1.キャベツは短めの千切り、玉ねぎは粗みじんに切る。 2.油で玉ねぎをしんなりするまで炒め、ツナ、キャベツを加えて炒め合わせる。 3.調味料を加えてパン粉で水分を調整し、チーズを加えて味を調える。 4.食パンで3を挟み、半分に切る。 5.アルミホイルで包み、オーブントースターで焼く。 (目安:1000wで5分程度) アツアツのうちに召し上がれ❤ 11月22日(月)の給食





一昨日、11月20日は「ピザの日」です。 「ピッツァ・マルゲリータ」の名前の由来となったイタリアの王妃マルゲリータの誕生日です。 今日は、ナンを使ってピザトーストを作りました。 食パンで作るピザトーストよりも、生地の感じがピザらしく仕上がっていると思います。 真ん中の写真は、ナンにピザソースとチーズをのせているところです。 一番下の写真は、キャロットポタージュを作っているところです。 野菜の味が効いた優しい味のポタージュです。 食パンを細かく切ってオーブンで焼いたクルトンを添えました。 今日は、3年生がリクエストしてくれた本「げんきいっぱいあさごはんのじゅつ」と「またまたねえどれがいい?」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 11/22 二宮金治郎(にのみや きんじろう)





二宮 金治郎(にのみや きんじろう) 20211122 村松 みなさんは、この石像を見たことがあるでしょう。昇降口のところにありますね。ところでこの人、誰だか知っていますか。 この人は、二宮 金治郎(にのみや きんじろう)と言います。今から、240年近く前、江戸時代の中頃、今の神奈川県小田原市に生まれ、いろいろなところで活躍した人です。 金治郎は裕福な農家の子供として生まれました。しかし、4歳のとき洪水によって家の田畑が大きな損害をうけ、貧乏のどん底にたたき落とされます。その上、金治郎が13歳の時に父が、そのあと母も続けて亡くなります。弟2人の生活を支えることになります。 朝は早起きをして、山の薪(たきぎ)とり、夜は草鞋(わらじ)づくりをしたと言われています。その薪とりの姿が、石像になっているのです。 金治郎は働きながら勉学にも励み、20歳のときには失った土地も買い戻し、自分の家をふたたびもとに戻しました。 そののち、小田原で武士の家につとめて、小田原藩(今で言うと小田原市)の発展のために活躍したのです。その活躍は小田原だけでなく、関東地方のいろいろなところへ行き、その土地の発展に力を尽くしたといいます。 50歳を過ぎたころには、江戸幕府の武士となり、70歳で亡くなるまで日本の農村の発展に尽くしました。 働きながら勉学にがんばった金治郎のことは、110年以上前の修身(今の道徳)の教科書に載り、90年近く前には、多くの小学校で、二宮金治郎の石像や銅像ができたと言われています。 今は、金治郎の石像のように、働きながら本を読んだり、スマホをしたりすると危ないですよね、みんなならわかると思います。勉強するときはしっかりと集中していく、これが大事なのです。 金治郎の石像を見るときには、子供のときは集中して学び、そして大人になってからは人々のためにがんばった 金治郎の姿を思い浮かべてください。 きょうは二宮金治郎のことについて、話しました。 (裏面に「先生方へ」があります) 「先生方へ」 前にも書きましたが、朝会では、いわゆる「偉人」を取り上げたいと思っています。年間3人くらいを目安にと考えています。平櫛田中、ノーベルと取り上げたので、今回は一小にも関係ある「二宮金治郎(尊徳)」です。 二宮金治郎については、一学期中に話そうと思っていたのですが、今になってしまいました。子供たちが何気なく見ている石像の人物、その人について知っておくことは、これからの学びにいい影響があると思っています。学級学年の実態にあわせて、補足をしておいてください。 なお、石像の金治郎が読んでいる本は、「大学」と言います。インターネットがないころに、苦労して調べたことがあります。「大学」は儒教の経書で、四書五経の四書の一つです。 さて、11月も後半です。二学期の成績付けの時期がせまってきました。日頃の授業を充実させ、記録をしっかりとっていけば大丈夫です。計画的に仕事をすすめていきましょう。特に授業では、リズムとテンポを心がけたいですね。子供たちが何をしたらいいかわからない時間、いわゆる空白の時間をなくすことを意識しましょう。マル付けなど子供たちが5人以上並んでいると、空白の時間が生まれます。並んで待っているときに、やることがなく、おしゃべりが始まるのが常です。5人以上並ぶことがないようにすること、すばやくマル付けをすること、これも空白をなくすには必要です。よろしくお願いいたします。 <資 料 二宮金治郎> 生誕 天明7年7月23日(1787年9月4日) 死没 安政3年10月20日(1856年11月17日) 江戸時代後期の経世家、農政家、思想家である。自筆文書では金治郎(きんじろう)と署名している例が多いが、一般には「金次郎」と表記されることが多い。また、諱(いみな)の「尊徳」は正確には「たかのり」と読むが、「そんとく」という読みで定着している。 学校の石像は、昭和に入ってから全国で設置されたものの一つである。戦前の勤勉・勤労、愛国心を育てるために設置された。小平第一小学校の石像の正面に刻まれている「勤倹力行」(きんけんりっこう)の意味は次のようである。 よく働き、つつましい生活をし、何事にも精一杯努力すること。「勤倹」は、「勤勉倹約」の略で、よく働き、むだ使いをしないこと。「力行」は、物事を精一杯努力して行うこと。「力行」は、「りきこう」「りょっこう」「りょくこう」とも読む。 なお、明治時代の内村鑑三は、英語著作の「代表的日本人」に、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮 を紹介している。 【5年図工】展示発表に向けて





5年生の立体作品は「使って楽しい焼き物」を出品します。 これまで作って焼き上げた焼き物に添える最後の仕上げとなる、オリジナルの箸を作りました。 この箸は用務員さんが切ってくださった一小の竹からできています。 小刀を使った難しい作業でしたが、どの子も上手に作り、きれいに磨き上げました。 展示発表をお楽しみに! 11月19日(金)の給食





「ジャンボぎょうざ」は、みなさんに人気がありますね! 今日は「甘酢あんかけ」にしました。 パリパリに揚がったぎょうざにとろっとしたあんがかかり、ぎょうざの味にマッチしておいしいです。 真ん中の写真は、ぎょうざの皮で具を包んでいるところです。 給食では直径15cmの大きなぎょうざの皮を使っています。 一番下の写真は、ぎょうざを揚げているところです。 今日は図書委員の児童が「へんしんプレゼント」を読み聞かせしました。 【5年生食育】お米の脱穀と籾摺り





脱穀は、稲を指でこすって行いました。 籾摺りは、すり鉢と野球ボールを使って行いました。 すり鉢の中に籾を入れて、野球ボールでゴリゴリこすると、籾殻がとれて玄米が現れます。 根気のいる作業ですが、一生懸命取り組みました。 今は機械でやることが多い籾摺りですが、昔の人が手作業でやっていたことを想像すると、いかに大変だったかがわかりました。 最後は片付けもきれいに行い、立派でした。 籾摺り後のお米は、給食室で炊いて試食したいと思います。 11月18日(木)の給食





今日は、旬のきのこをつかった炊き込みごはんを作りました。 「どんまいきのこズ」のみなさんが参加して、おいしい炊き込みごはんができあがりました! 子どもたちからはは、「どんまいきのこさんたちかわいいから、きのこごはんいっぱい食べるんだ!」という声も聞こえてきて、10月に行った食品ロスの取組の成果を感じました。 「さつま揚げ」と「さつま汁」は鹿児島県の郷土料理です。 「さつま揚げ」は魚のすり身を成形して揚げた料理で鹿児島名物として有名ですが、鹿児島県では「さつま揚げ」ではなく「つけ揚げ」と呼ばれています。 「さつま汁」は「さつま鶏」を使うことに由来していると伝えられ、鶏肉を使った具だくさんなみそ汁です。 今日の給食では「さつまいも」も使いました。 「さつま」づくしですね。 真ん中の写真は、さつま揚げの具を成形しているところです。 一番下の写真は、さつま揚げを揚げているところです。 今日は、5年生がリクエストしてくれた本「ほしじいたけほしばあたけ」と「ちっちゃなサリーはみていたよ」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 学童農園 サトイモを掘りました。
サトイモを掘った後は、塊をばらばらに分けます。全部のサトイモの塊をばらす時間はありませんでしたので、学童農園の方にばらばらにするのと袋詰めをお願いして、児童は学校へ帰りました。




学童農園 サトイモ掘り
11月16日 学童農園へサトイモを掘りに行きました。子どもたちは、朝から「早く掘りたいな。」と楽しみにしていました。
はじめに、4人グループで里もの根っこを手で掘り、大きなサトイモのかたまりを「せーの」と掛け声をかけて掘り出しました。 



|
小平市立小平第一小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目1082番地 TEL:042-341-0008 FAX:042-341-0052 |