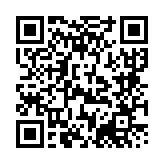|
最新更新日:2024/06/14 |
|
本日: 昨日:27 総数:63801 |
【電話】042-341-0008(平日8:00頃〜17:30頃)
【E-mail】gakkou@01.kodaira.ed.jp(24時間)
4月30日(金)の給食





「たけのこごはん」は、この季節にだけ食べられる料理ですね。 旬の新たけのこを使って、給食室で調理しました。 たけのこはもちろん小平産です。 とれたて新鮮なのでおいしいですね! 真ん中の写真は、小平産の新たけのこです。 今年は季節の進みが早くて、たけのこが仕入れられるか心配しましたが、JAさんが用意してくれました。 一番下の写真は、茹でたたけのこを切っているところです。 たけのこは灰汁(あく)があるので、米のとぎ汁と鷹の爪で下茹でしてから使います。 「飛鳥汁」は、古くから飛鳥地方に伝わる家庭料理で、本来は牛乳を使った鍋料理です。 今から約1300年前の飛鳥時代に、中国から日本へ牛乳が伝わりました。 当時はとても貴重なもので、貴族の間で飲まれていました。 牛乳を使った飛鳥汁もこの頃から作られていたといわれています。 いつものお味噌汁とは一味変わって、まろやかな味になりますね。 今日は、図書委員の児童が「おばけのおうちいりませんか?」を読み聞かせしました。 続いて、たけのこごはんにちなんで「ふしぎなたけのこ」を副校長先生が読み聞かせしました。 4月28日(水)の給食





今日の給食の「紅茶マフィン」は、紅茶を煮出してロイヤルミルクティーを作り、細かく刻んだ茶葉と一緒にケーキ生地に混ぜ、カップに入れて焼きました。 真ん中の写真は、カップにケーキ生地を流しているところです。 「紅茶マフィンおいしかったです!」という声がたくさんありました。 紅茶は春から夏にかけて「ファーストフラッシュ(1番摘み茶)」「セカンドフラッシュ(2番摘み茶)」が収穫されます。 紅茶にも旬があるんですね。 「田舎うどんが楽しみなんだ!」と何日も前から言っている1年生がたくさんいました。 うどんは茹でて、流水でしめて、汁とは別々に配缶しています。 汁はさば節でだしをとっています。 一番下の写真は、流水でしめたうどんをタライに移しているところです。 今日は図書委員の児童が「ノラネコぐんだんパンこうじょう」を読み聞かせしました。 続いて、紅茶マフィンにちなんでお茶がでてくるお話「おちゃのじかんにきたとら」を副校長先生が読み聞かせしました。 4/26 チンパンジーのあいさつ

学年のはじめでもあるので、あいさつについて、以下のような話をしました。 チンパンジーのあいさつ 20210426 村松 私たちの住む地球には、人間の他にたくさんの動物が住んでいますね。 その動物たちは、人間と同じようにあいさつをするのでしょうか。犬と犬、猫と猫、ライオンとライオン、どうもしていないようです。犬と犬が出会って、吠え合うことはあっても、頭をさげてあいさつをしているのは見たことありません。頭をさげてあいさつをするのは、どうも人間だけのようです。 ところが、人間と同じように、きちんとあいさつをする動物がいるんです。それは、チンパンジーです。(写真を見せる) 多摩動物園の人から聞いた話を紹介しますね。チンパンジーは朝起きると一斉に広場に出ます。広場に出ると、お互いが顔を向け合って「ホウ、ホウ、ホウ」と言い合うそうです。人間でいうと何になるんでしょうか。きっと「おはようございます」という言葉かもしれません。 その次に、お互いの指と指をくっつけ合うそうです。これは人間でいうと何になりますか。そう「握手」ですね。これで終わるかというと、そうではないのです。もうひとつあります。それは、一番仲の良い同士がお互い肩を寄せ合って、相手の方をトントンとたたき合います。 「ホウ、ホウ、ホウ」「手の指と指」「肩のトントン」この3つのあいさつは毎朝必ず行われます。しかも、「ホウ、ホウ、ホウ」のあいさつを忘れたり、怠けたりすると、仲間に入れてもらえないことがあるそうです。チンパンジーの世界では、朝のあいさつは仲良しになるための「しるし」「約束」なのです。 さて、友達をたくさんつくるためには、まずはあいさつが必要ですよね。チンパンジーよりもずっと進んだ頭をもつ人間ですから、たくさんのあいさつをすすんでしたいものです。 きょうの朝会の話、これで終わります。 (裏面に<先生方へ>があります) <先生方へ> 4月も今週で終わりです。週末の30日には離任式があります。お世話になった先生方とのお別れをきちんとさせたいですね。ご指導よろしくお願いいたします。 また今週末の29日は昭和の日でお休みです。祝日の指導は忘れずにしておいてください。大型連休の資料を下に書いておきました。参考にしてください。 さて、あいさつは仲間づくりに必要、そして仲良しになるために欠かせないもの、そんな意識をもたせられないかなと考え、この話をしました。緊急事態宣言下ですが、学級・学年の実態にあわせて補足などをしていただけると助かります。 <祝日に関する資料> 祝日法には、次のように書かれています。 ○昭和の日 4月29日(2007年から) 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。(この日は1948年以来ずっと祝日でした。その間に「天皇誕生日(1948-1988)」→「みどりの日(1989-2006)」→「昭和の日(2007-)」と名前が変わっています。) ○憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。(1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年の祝日法によって制定されました。公布日の11月3日は、日本国憲法が平和と文化を重視していることから文化の日になっています。) ○みどりの日 5月4日(2007年から) 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 ○こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。(こどもの日には母に感謝するという意味合いもあります。「母の日」がポピュラーになっているので、この意義は忘れられていますが、この機会に是非話しておいてください。) <参 考> ○「ホウ、ホウ、ホウ」のあいさつ 「ホウ、ホウ、ホウ」というあいさつは、パントグラントと呼ばれるチンパンジー特有の発声のことです。これは、必ず自分より優位な個体に向けて発するので、個体間の優劣関係を知るよい指標になると言われています。メスやワカモノ・コドモにとって、オトナのオスは自分より優位であり、パントグラントを発する対象になるそうです。また、チンパンジーには笑いがあります。くすぐったり、追いかけ合ったりして笑い声を出します。ただ、テレビ番組で芸などを披露する際、歯を見せて笑っているように見えることがありますが、これは「グリマス」と呼ばれ、チンパンジーが恐がっている時の顔です。 4月27日(火)の給食





今日のコロッケは、大豆を使っています。 大豆はやわらかく煮て、細かく切ってあるので、大豆が苦手な人も食べやすくなっています。 じゃがいもだけで作るより、食物繊維を多くとることができますね。 豆を食べる量は不足しがちです。 豆は苦手な子が多いですが、給食では細かく切ったりすりつぶしたりして、献立に取り入れています。 給食のコロッケは、じゃがいもを蒸してつぶして衣をつけて、手作りしています。 真ん中の写真は、コロッケを成形しているところです。 一番下の写真は、コロッケを油で揚げているところです。 揚げるときも、爆発したり形が崩れたりしないように慎重に揚げています。 今日は、豆とスープが出てくるお話「まいごのまめのつる」と、「ねえ、どっちがいい?」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 4月26日(月)の給食





今年度も「給食DE世界旅行」を給食メニューに取り入れていきます。 コロナ禍でお出かけが難しい日々が続いていますが、給食で世界中を旅する気分になってもらえるとうれしいです。 世界の料理に触れて世界の食文化を知り、いろいろな国々へ興味を高めましょう! 「給食DE世界旅行」今年度第一回目は、「中国」です。 中華料理は食べたことがある人が多いと思います。 「マーボー豆腐」には、豆腐がたくさん使われていますね。 真ん中の写真は、豆腐を切っているところです。 給食では大量の豆腐を使いますが、崩れないように丁寧に切っています。 豆腐は、おみそ汁や、冷ややっこなど、和食にかかせないものですが、豆腐は、中国で作られたのが、はじまりだといわれています。 中華料理に豆腐を使った料理が多いのは、そのためです。 「トウファ」は新メニューです! 「トウファ」は豆乳を使ったプリンのような料理で、中国や台湾で食べられています。 今日のような甘いデザート系もあれば、塩味のもの、辛いものもあります。 地方によって味付けや使う材料が様々です。 今日の給食では、豆乳プリンにシロップをかけて黄桃を飾りました。 一番下の写真は、豆乳プリンに黄桃をのせているところです。 今日は「二ひきのカエル」と、中国の昔話「なんでもふたつ」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 4月23日(金)の給食





「ターメリックライスのクリームソースかけ」は、言わずと知れた人気メニューで、昨年度の6年生の好きなメニューとして1位に輝いたクラスもありました。 給食室で作ったホワイトソースが味の決め手です。 「海藻サラダ」は野菜が苦手な子でも食べやすいサラダです。 給食のサラダのドレッシングは、毎回手作りしています。 市販のものとは一味違っておいしいです。 また、手作りすると味のバリエーションも増えますね。 真ん中の写真は、ドレッシングを配缶しているところです。 「清見オレンジ」は、旬の果物ですね。 日本のみかんと外国産のオレンジを交配して作られた品種です。 さわやかな酸味と甘みがあり、食べやすいオレンジですね。 一番下の写真は、清見オレンジを切っているところです。 食べやすいように皮と実の間にも包丁を入れています。 今日は、図書委員の児童が「フンガくん」を読み聞かせしました。 つづいて「世界のむかしばなし」より、ノルウェーの昔話「七人さきのおやじさま」を副校長先生が読み聞かせしました。 4月22日(木)の給食





今日の「手作りフォカッチャ」は、新メニューです! 給食室で小麦粉を練ってパン生地を作りました。 パン作りは、生地を練ったのあとに発酵させて、一人分ずつに分けて成形して…ととても手間がかかります。 でも焼き立てのパンの味は最高ですね! 子どもたちからも「おいしかった」の声がたくさんありました。 みなさんにおいしいものを届けたくて、給食室は力をあわせて頑張りました。 真ん中の写真は、フォカッチャを成形しているところです。 一人分ずつに丸めてから平らにのばして、オリーブオイルを塗って表面に穴をあけ、塩をパラパラとふりかけました。 フォカッチャはイタリアのパンです。 小麦粉(強力粉)、オリーブオイル、水、塩、イーストなどで作るシンプルなパンですが、オリーブオイルの風味がおいしいですね。 フォカッチャはピザの原型ともいわれています。 「ポークビーンズ」は大豆を使いました。 給食では大豆は乾燥したものを仕入れて、朝から水に浸けて茹でています。 一番下の写真は、ポークビーンズに茹でた大豆を加えているところです。 今日は「ポークビーンズ」にちなんで「やせたぶた」、豆が出てくるお話「ちゃっかりこぞうはまるもうけ」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 どんな動物ですか?
給食の時間に読み聞かせた絵本『じゃがいもアイスクリーム?』(市川里美作・絵 BL出版)に出てきた動物はどんな動物ですか?と質問をしてくれた子がいました。
興味をもってくれてうれしいです。 表紙をご紹介します。 日本から遠く南アメリカ大陸のペルーでしょうか、アンデスの山に住む少年とその家族が飼育するアルパカの母子の心あたたまるお話です。 実物のアルパカには日本では動物園でしか会えませんし、どのページの絵もすてきですから、この絵本は手に取って見ていただけるとうれしいです。 

一小タイム
今年度最初の一小タイムです。
クラスでそれぞれの場所に集まり、活動を始めました。 

4月21日(水)の給食





「新じゃがいものバター焼き」は、今が旬の新じゃがいもを使って作りました。 新じゃがいもは、水分が多く、やわらかくて香りが良いといった特徴があります。 この時期ならではの味わいです。 給食では、じゃがいもの皮をむいて、芽を取り、半分に切ってから一度蒸して、表面にバターと塩合わせたものを塗り、オーブンで焼きました。 真ん中の写真は、じゃがいもを蒸したところです。 一番下の写真は、じゃがいもにバターと塩を合わせたものを塗っているところです。 また、今日のスープは旬の春キャベツを使っています。 旬の食べ物は、一年で一番味がおいしく、栄養がたっぷりです。 春はおいしい旬の食べ物がたくさんあります。 旬の味わいを楽しみましょう! 今日は、図書委員の児童が「ノラネコぐんだんカレーライス」を読み聞かせしました。 続いて、今日の給食「新じゃがいものバター焼き」にちなみ、「じゃがいもアイスクリーム?」を副校長先生が読み聞かせしました。 4月20日(火)の給食





「豆腐ハンバーグ」は、たまねぎを炒めて、ひき肉とあわせてよく練り、一つずつ手で丸めて手作りしています。 全部で約470個作りました。 真ん中の写真は、ハンバーグを成形しているところです。 一番下の写真は、オーブンでハンバーグを焼いているところです。 「じゃがいものきんぴら」は、拍子切りにして素揚げしたじゃがいもをきんぴらの具材として加えています。 普通のきんぴらは苦手な子が多いですが、揚げたじゃがいもを加えることで食べやすくなります。 今日は「豆腐ハンバーグ」にちなみ、「おばけのアッチ ハンバーグつくろうよ」と「うさぎとかめ」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 5年 高尾山遠足 下山開始

下山します。帰りはリフトです。 5年高尾山遠足

4/19 3つの耳





20210419 村松 私たちは、口は1つですが、耳は2つあります。これはお話しすることも大切ですが、それ以上に聞くことが大切だということで、神様などが耳を2つにしてくれたのではないかと思います。 ところで、この耳の使い方ですが、人によって3つに分けられるそうです。 一つは、「鉄砲耳」です(鉄砲の絵を見せる)。この耳は鉄砲の弾のように、聞いたことを右から左へとすぐに抜けてしまう耳です。おうちの人の話、先生の話などを「うん、うん」とうなずきながら聞いていたようなのに、お話しが終わると何にも覚えていない耳です。 二つ目は「ざる耳」です(ざるの実物を見せる)。ざるは、野菜など入れて洗うときに使いますね。ざるで洗うと、野菜はそのまま残りますが、水だけは流れてしまいます。このざるのように、人の話を聞いたときには、だいたいのことは覚えているのですが、細かいことは覚えていない、そして時間がたつと忘れてしまう、水が流れ出てしまうような耳を「ざる耳」と言います。 三つ目は「さいふ耳」です(さいふの絵を見せる)。さいふというのは、お金を大切に入れておく物です。これを落としたり、なくしたりしたら大変です。さいふは、必要なときには取り出してすぐに使えるようにしておかなくてはだめですよね。このさいふのように、おうちの人や先生から言われたことを、しっかりと頭の中にしまっておき、必要なときにそれを思い出して上手に使える耳、これを「さいふ耳」といいます。 きょうは3つの耳についてお話ししましたが、みなさんの耳はどれでしょうか。そして、一番良い耳はどれでしょうか。考えてみてください。お話しを終わります。 (裏面に「先生方へ」があります) <先生方へ> 2回目の朝会ということで、できるだけわかりやすくということを意識しています。ただ、この話は少し難しい内容かもしれませんね。 さて、話をしっかり聞くと言うことは、生活の基本です。学習するうえでとても大切な約束の一つでもあります。これができないと、生活はもちろん学習も積み重なっていきません。学年の最初の4月に、「聞く 聴く」ということを徹底させるためにこの話をすることにしました。 きょうの話は有名で、むかしは「きんちゃく耳」と言っていました。「きんちゃく 巾着」では、今の子どもたちはなんのことだかわからないので、さいふと言い換えてあります。聞くことの大切さを、学年・学級に応じて補足して指導していただけたら幸いです。 ◎地震 学級指導で 今週の21日に避難訓練があります。地震時の避難経路を知る、避難経路を確認することが目当てになります。 最近は九州のトカラ列島で地震が頻発しています。九州という東京から相当離れたところですが、他人事(ひとごと)ではないと思っています。先生方もご存じの通り、首都直下型地震については、30年以内に70パーセントの確率でおきると言われています。降水確率で70パーセントと言えば、ほとんど間違いなく雨が降ります。 私が担任だったら、子どもたちに「みんなが生きている間には、東日本大震災と同じくらいのものすごく大きな地震がおこります。今からしっかりと準備をしておくことが大切です。おうちの人と、自分が寝るところは安全か、物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこないところで寝ているか、すぐに確かめましょう。そうして、危ない場所で寝ていたとしたら、安全に寝られるようにしていかないとだめですね。」というような話をします。学年・学級の実態に即して、必ず指導してください。 ところで、この地域の活断層として「立川断層」というのが有名です。聞いたことがあると思います。私は教員になってから、立川断層が動く可能性について常に注目していました。少し古いですが、6年前に立川市の広報紙に次のような記事があったので、紹介します。(この記事を読んで少し安心しましたが、首都直下型地震の確率は変わりません) 東京大学地震研究所教授・佐藤比呂志氏による立川断層講演会が開催され、立川断層は市内に存在しないことが報告されました。この報告は、佐藤教授のグループが平成24年から3年間にわたって行ってきた大規模かつ多岐にわたる調査において、断層の存在が確認できなかったことから結論づけられました。 (中略) また、箱根ヶ崎断層(同グループが新称)は過去の活動状況から、近い将来の活動の可能性は低いとされています。この調査結果は国の地震調査推進本部等で検討され、今後正式に評価結果が発表される予定です。 (広報たちかわ: 2015年平成27年6月25日号2面より) 4/12 桃太郎と3つの力
きょうは、令和3年度、最初の朝会です。1年生もいるので、きょうはこの本、桃太郎のお話をしましょう。
桃太郎の話はみんな知っていますよね。桃太郎がイヌ、サル、キジのお供をつれて、鬼ヶ島で鬼退治をするお話です。 私は子どもの頃、「桃太郎は強いのだから、お供などの力を借りないで自分一人で行けばいいのに」と思っていました。大きくなって、なんでお供を連れて行ったのか調べてみると、桃太郎一人だけでは、やはり鬼退治は無理だということがわかったのです。 それは、こんな理由です。 サルを連れて行くのは、鬼退治をする作戦「計画をたてる」ためです。サルはかしこくて知恵があります。その知恵をだしてもらい鬼退治の計画をたてるのです。 つぎにキジを連れて行くのは「よく調べる」という理由があります。作戦をたてても、鬼退治するには、鬼の数はどれだけで、どんな武器をもっているのかをしっかり調べなければなりません。キジは空を飛びながらそれを調べるのです。 次にイヌです。イヌはよく吠えますが、元気で行動力があります。桃太郎にいろいろと言うことができる、言い換えると「発言し行動する」力があります。 このイヌ、サル、キジのお供の力、「計画をたてる、よく調べる、発言し行動する」この3つの力が合わさって、桃太郎は鬼退治というとても難しいことができたのです。 さて小平第一小学校には、4つの目標があります。黒板の上に貼ってありますね。そのうちの一つ「考える子」が今年一番大切にする目標です。考える子というは、桃太郎の話にあるように、「計画をたて、よく調べ、発言する」子のことです。 みなさんは今年1年、考える子目指して毎日の学習をがんばりましょう。そして考える子は桃太郎の話と関係があることを忘れないでくださいね。 これで朝会の話を終わります。 (裏面に「先生方へ」があります) <先生方へ> 年度の最初の朝会では、教育目標について話すべきだと思っています。ただ、教育目標を朝会で話すのはとても難しいのです。一小は4つ目標がありますから、一つずつやると朝会4回分です。それではあまりに冗長です。また、4つをまとめて話すことも考えましたが、焦点が定まらなくなりそうです。そのため、今年度は考える子だけに焦点をあて、桃太郎の話にからめて話しました。あとの3つについては、学級で補足しておいてください。よろしくお願いいたします。 ご存じのように、桃太郎をはじめ昔話には、多くの知恵が隠されています。それを見つけるのはとてもおもしろいと思っています。みなさんはどうですか。ぜひ昔話のおもしろさを子どもたちに伝えてみてください。このことがきっかけで、昔話をもう一度読んでみようという子が出てきたら、うれしいかぎりです。 さて、新しい学級がスタートして約1週間がすぎました。この時期は、飛行機で言うと離陸したばかりの状態と同じです。離陸するときの飛行機は、エネルギーを一番使います。そして神経も一番使います。同じように先生方の体力・神経の消耗も、1年間の中でもっとも大きいときです。疲れがピークに達していると思います。コロナ対応などもあるからなおさらです。 とにかくこの4月は、ゴールデンウィークを楽しみにがんばってください。よろしくお願いいたします。とはいえ無理は禁物です。お互い健康第一でやっていきましょう。 ただ、学級のほころびやゆるみがでてきている場合は、今週が最後の修正時期です。ゴールデンウィークをすぎるとまず修正はききません。あとでやろう、まだ大丈夫と思っていると絶対にダメです。今週の朝の会の時間、掃除の時間、帰りの会の時間などをよく見てください、確かめてください。子どもたちを中心にうまくまわるシステムができていますか。それができていれば大丈夫です。万一できていない場合は、学年で対策をたててすぐに実行しましょう。自分だけで抱えてはいけません。また管理職にも相談してください。多くの経験から、いい方法をアドバイスできると思います。よろしくお願いいたします。 <参 考> 指導しておいてください(小平第一小学校の教育目標) 考える子 :異なる意見を受け入れ、深く考え主体的・創造的に問題解決に取り組む子供 <行動目標:読書いっぱい 発言いっぱい> やさしい子:自他の生命を尊重し、共感し、人が喜ぶ姿を見て喜べる子供 <行動目標:挨拶いっぱい 笑顔いっぱい> やりぬく子:目標に向かって努力し、失敗しても何度でも挑戦する子供 <行動目標:努力いっぱい 挑戦いっぱい> 元気な子 :自ら抵抗力を高め、誰とでも協同する子供 <行動目標:汗いっぱい 遊びいっぱい> 4/6 入学式 式辞
令和3年度 入学式の話 「カエル」を合言葉に
令和3年 4月 6日 校 長 村松 守夫 1年生のみなさん、入学おめでとうございます。 みなさんは、きょうから小平第一小学校の1年生です。かわいい、かわいい1年生です。みなさんが来るのを先生方、みんなで待っていました。 そうしたらやっと今日、みなさんが来てくれました。だから、どの先生もニコニコしているでしょう。マスクをつけているから、わからないかな? ところで、学校は幼稚園や保育園と違うところがあります。それはね、学校では勉強などいろいろなことがあるということです。でも大丈夫、みんなががんばれば楽しくすごせますよ。 では、何をがんばったらいいかを話しますね。それは「カエル」がヒントです。 まず「か」です。これは「考える子は賢い子」です。学校の勉強では、よく考えることが大切です。自分で考えて行動する、こういう子は必ず賢くなりますよ。 次は「え」です。「笑顔でいいあいさつ」です。学校では、笑顔であいさつする子はたくさんの友だちができます。いつも笑顔であいさつするようにしていきましょう。ちょっと練習してみましょうか。笑顔で「おはようございます」と言ってみましょう。 さんはい!上手ですね。素晴らしい!! 最後は「る」です。「ルールを守って、安全に」です。学校に来るとき家に帰るとき、車に気をつけて、またお友だちとふざけたりよそ見をしたりしないで、ルールを守っていきましょう。わかりましたか? わかったひとは「はい」の返事をしましょうね。 それでは今日から「カエル」を忘れないで、がんばる1年生になってください。 これから、大人の人たちにお話をしますから、みなさんは少し待っていてください。 保護者の皆様に一言申し上げます。お子様のご入学、おめでとうございます。皆様が手塩にかけて育ててこられたお子様を、今日から6年間お預かりするわけです。その責任の重さをひしひしと感じます。教職員一同、力を合わせてベストを尽くしてまいります。 幸い本校の教職員はみんな熱心ですし力も備えております。保護者の皆様と力を合わせて、よりよい子に育てていきたいと思います。ご協力、よろしくお願いいたします。 結びに、今回の入学式は、新型コロナウイルス対応で、縮小した形になりましたこと、まことに申し訳ありません。小平市としてまた小平第一小学校として、お子様の安全を第一に考えてのことです。ご理解いただければ幸いです。 では1年生のみなさん、明日7日も元気よく学校に来てくださいね。お話しを終わります。 4/6 始業式
令和3年度 始業式の話
令和3年 4月 6日 校 長 村松 守夫 (時間の関係で4/7にも分けて話す場合あり) きょうから、小平第一小学校の校長としてきました 村松守夫です。3月までは、小平第五小学校にいました。みんなで力を合わせて楽しい学校をつくっていきましょうね。 さあ、春休みが終わり、いよいよ新しい学年がスタートします。みなさんの春休みはどうでしたか。 みなさんはきっと、「きょうからひとつ上の学年だぞ。がんばろう。」という気持ちで登校してきたことでしょう。 この1年間、まずしっかり勉強をすること、そして2つめ、友達と力をあわせること、この2つをしっかりがんばりましょうね。 <去られた先生方> では、皆さんがお世話になった先生方が、おやめになったり、他の学校に行かれたりしたのでお知らせします。 みなさんが大変お世話になった 橋本 忠明 校長先生は、おやめになり、小平市教育委員会でお勤めされています。 岡山 明子 先生は、おやめになりました。 細谷 愛 先生は、国立市立国立第八小学校へ行かれました。 伊藤 美里 先生は、小平第十二小学校へ行かれました。 梶原 郷(かじはら あきら)先生は、武蔵村山市立村山学園に行かれました。 山本 侑 先生は、東大和市立第九小学校へ行かれました。 内田真生子(まきこ)先生は、練馬区立中村西小学校へ行かれました。 学生ボランティアの井関 奈々さんは、杉並区立杉並第七小学校で、新しく先生になりました。 警備の上吹越 久光さんは、おやめになりました。 用務の諫山(いさやま) 矢一郎さんは、おやめになりました。 <お休みになられる先生方> 赤ちゃんを産むために、また育てるためにお休みになる先生です。 嶋 奈月 先生 <新しく来られた先生方> 次に新しく来ていただいた先生方を紹介します。 渡辺 佳恵 先生です。市内の小平第十二小学校から来ていただきました。 安部 澪菜 先生です。今年から新しく先生になりました。 給食調理員の安田 真実さん 今年から来ていただきました。 スクールサポートスタッフの岡庭 佳恵(かえ)さん 新しく来ていただきました。 <復帰される先生方> 赤ちゃんを育てるためにお休みしていて、4月から復帰された先生方です。 土方 佳那 先生 古谷 浩 先生 新宅 智代 先生 4月19日(月)の給食





今日は、ねぎをたっぷり使ったチャーハンです。 真ん中の写真は、ねぎを切っているところです。 唐揚げは「カリッとジューシーでおいしい!」と、とても人気があります。 一番下の写真は、唐揚げを揚げているところです。 調理員さんの揚げ方が上手なのが一番のポイントです! また、下味に砂糖とレモン汁またはお酢を少し使うのもポイントで、粉はでん粉と上新粉をあわせたものを使っています。 材料と作り方は以下の通りです。 ぜひお試しください。 <材料(4個分)> 鶏もも肉(40g) 4枚 にんにく ひとかけ しょうが ひとかけ しょうゆ 小さじ2 レモン汁または酢 小さじ1/2 砂糖 小さじ1弱 酒 小さじ1/2 でん粉(片栗粉) 大さじ2強 上新粉 大さじ1/2強 揚げ油 適宜 <作り方> 1.にんにく、しょうがはすりおろす。 2.鶏肉に1と調味料で下味をつける。 3.でん粉と上新粉を混ぜたものを2にまぶし、180度の油で揚げる。 今日は「ふしぎなたいこ」「ちいさいきみとおおきいぼく」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 4月16日(金)の給食





「ホットポテトサンド」は、じゃがいもを蒸してつぶして具を作り、それをパンにはさんでアルミホイルに包み、オーブンで焼きました。 真ん中の写真は、パンに具をはさんで、半分に切ったあとアルミホイルで包んでいるところです。 とても手間がかかっていますね。 ところでみなさん、サンドイッチの由来を知っていますか? サンドイッチという名前が誕生したのは、今から200〜300年前です。 カードゲームが好きなサンドイッチ伯爵が、ゲーム中でも片手で食事ができるよう、パンに具をはさんだものを作らせたことから、サンドイッチという名前がついたといわれています。 一番下の写真は、いちごを数えているところです。 大きくて甘い、立派ないちごでした。 子どもたちはいちごが大好きですね。 1年生も目を輝かせていました。 1年生の給食は今日で3回目ですが、毎日「おいしい!」と言ってたくさん食べてくれています。 おかわりを希望する子も多くいて、今日も「おかわりじゃんけん」をしていました。 しばらくの間、1年生が食べやすい献立、配膳しやすい献立を取り入れています。 「おいしい」体験を増やして、給食をもっともっと好きになってもらえるように、給食室一同頑張ります! 今日は、図書委員の児童が「ちりとちりりあめのひのおはなし」を読み聞かせしました。 続いて、今日のパンメニューにあわせて、4年2組の児童がリクエストしてくれた本「おばけのアッチとくものパンやさん」を副校長先生が読み聞かせしました。 4月15日(木)の給食





ミートソースは、イタリアのボローニャという町で誕生しました。 イタリアでは、「ラグー・アッラ・ボロネーゼ」といい、「ミートソース」とはいいません。 日本のミートソースは、ひき肉を使ったトマトソースに近いですが、本場のボロネーゼは、肉の割合が多く、トマト風味は少ないです。 給食では野菜とひき肉を炒めて、トマトソースでじっくりと煮込んで作っています。 時間をかけて煮込むので、深い味わいでおいしいです。 1年生の子どもたちも「おいしい!」と笑顔がいっぱいでした。 真ん中の写真は、ミートソースを煮込んでいるところです。 「カリカリワンタンのサラダ」は、短冊切りにしたワンタンの皮を素揚げして、サラダに混ぜて食べました。 パリパリの食感がサラダのアクセントになり、野菜が苦手な子も食べやすくなっています。 今日のゼリーはぶどう味にしました。 一番下の写真は、ゼリー液をカップに流し終えたところです。 子どもが好きなゼリーの種類を予想して「ぶどうゼリー」にしたのですが、1年生の子どもたちから「私はゼリーの中でぶどうが一番好き!」という声がたくさん聞かれ、うれしかったです。 今日は「ぶどうゼリー」にあわせて「ぶどう畑のアオさん」と「くんちゃんのはじめてのがっこう」を図書の石井先生が読み聞かせしました。 |
小平市立小平第一小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目1082番地 TEL:042-341-0008 FAX:042-341-0052 |