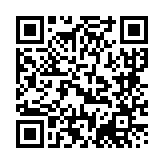|
最新更新日:2025/12/15 |
|
本日: 昨日:104 総数:164983 |
さようなら またあした



久しぶりにこどもたちに会えてうれしかったです。元気をもらいました。 さようなら またあした (校長) 2学期の始まりにあたりまして(9月学校だより巻頭より)
きのどくなね
校長 山縣 弘典 はじめに、本年9月1日は、大正12年(1923年)に発生した関東大震災発生から101年が経ちました。 関東大震災は、日本の首都圏に甚大な被害をもたらした決して忘れてはならない災害です。死者・行方不明者は、10万5385人、うち火災が原因とされるのは、9万1781人(内閣府中央防災会議:令和5年8月)と、尊い命が奪われました。ここに改めて、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともに、災害の教訓を、日々の備えや学校においては安全教育に活かすこと、次代に継承していくことが私たちに課せられた役割と考えます。 また、能登半島地震発生から9ヶ月、さらに今夏は九州地方日向灘震源とする地震が発生し、その直後の南海トラフ地震臨時情報の発表、全国的な大雨による各地方での河川の氾濫、土砂崩れ等の災害など多くの自然災害を眼前にしています。 私は、石川県災害ボランティア本部を通じて、7月30日に能登町(旧能都町)で一日(実質は半日です)お手伝いをさせていただきました。お手伝いの内容は、災害廃棄物の片付けや運搬です。前日の29日深夜に自家用車で金沢に入り、翌日の午前6時30分に金沢駅前に集合し、団体バスで能登町に向かいます。能登半島地震後の報道は徐々に少なくなり、今どのような様子なのか分からなかった私は、車窓から復旧にはまだ時間がかかることをまのあたりにします。 千里浜なぎさドライブウェイを見ながら、かほく市、羽咋市をバスは走ります。志賀町、穴水町からまわりの様子が変わってきます。家々の玄関に「危険」の表示が貼ってあります。また、土地が隆起している所もあります。走っている道路もうねっている所があります。金沢駅前からおよそ3時間かけて、能登町災害ボランティアセンター能都サテライト(山村開発センター)に到着しました。ボランティア活動は20名で行い、4〜5人が一つの班になって活動を進めます。ボランティアセンターを運営している皆さんも地元の方と他県の福祉協議会の皆さんが一緒になって運営しています。 早速、作業対象となるお宅に伺います。宇出津港近くにあるのですが、多くの道路が隆起していて、軽トラックが入ることができません。細い道をゆっくり運転しながら目的地に向かいます。到着すると、家主の方が待ってくれています。そのお宅は一見異常がないように見えますが、危険なため別の家に引っ越しをするそうです。家の中にある布団や家具、電化製品などを運び出し、軽トラックの荷台に積み込みます。思い出の品であろうものもいっぱいあります。都度、お聞きしながら運び出すのですが、家主の方は、「なっとない、なっとない(大丈夫、大丈夫)」と言います。 廃棄物一時処分場(藤波運動公園の一部を使用)には、1回では運搬できず、何回か往復します。そのお宅の作業は午前中で終了しました。 その家主の方から、私たちに何度も「きのどくなね」と言います。「ありがとう」を能登弁では、「きのどくなね」というそうです。 家主の方の言葉に私は胸が熱くなりました。むしろ力をもらったのは私の方で、家主の方の力強さや前向きさに頭の下がる思いでした。先行き不透明な中でも、能登の皆さんは前向きに力強く生活していらっしゃる。私は「また来ます」と言って、お宅を後にしました。たった半日で何ができたかといえば、力になったかといえば、申し訳ないぐらいのほんのちょっとのお手伝いしかできていません。でも、報道や新聞、インターネットでの見聞きでなく、自分のめで確かめられたことや、地元の皆さんとお話しできたこと、また、当日偶然一緒にお手伝いをすることとなった皆さんとのかかわりは大変貴重な経験になりました。また、週休日を活用するなどして活動ができればと考えています。 いよいよ、今日から2学期が始まりました。始業式では、子どもたちに「スタートはゆっくりめで、困ったことや悩みがあったら遠慮なく誰にでも相談してください。」、「多くの人々やモノとよりよくかかわる勉強を2学期もしていこう。」、「これまで以上に、自分も他の人も大切にする人になろう」という話をしました。 陸上競技の三段跳びに例えるなら、ホップは1学期、『ステップ』は最後の「ジャンプ」に向かう重要な段階です。それが2学期です。これまでと同様に、「次代を担う十小の子どもたちのためになること」は常に工夫改善・挑戦を繰り返しながら、本校の教職員は「チーム」になって努力してまいります。 この夏の8月30日も保護者の皆様にもご協力をいただき、タブレット端末を活用して全学級で「オンライン朝の会」に取り組みました。わたくしも各学級の様子を見に行きましたが、子どもたちのいい声を聞くことができました。 お子様のことで何か気になることがございましたら、遠慮なく本校の教職員にご相談ください。 この2学期も、本校のこどもたちにとり、学びや思い出の多い学期となるよう、保護者の皆様、地域の皆様にご協力とご支援を賜りながら学校経営・運営を進めてまいります。 よろしくお願い申し上げます。 下の写真は「のと里山海道」とまわりの様子です。道もうねっています。陥没しているところもあります。車窓からはがけ・土砂が崩れているところもあります。 



令和6年度 2学期始業式
おはようございます。
今朝も登下校の見守りなど、子どもたちの安全に心を配っていただいている地域の皆様、保護者の皆様、ありがとうございます。 始業式をもって2学期の教育活動がスタートしました。 校長先生からは、石川県災害ボランティアの話と四中校区の取組の話がありました。 石川県の話は、校長先生が現場で見たことや感じたことの話でした。こどもたちは、真剣に話を聞いていました。 四中校区の話では、テーマの再確認をしました。テーマは、「あいさつ 挑戦」です。今後の取組の様子は、ホームページで発信ししていきます。 校歌斉唱では、6年生の代表児童が伴奏を務めました。立派な伴奏ありがとうございました。体育館にきれいな歌声が響きました。 また、「子供が安心して生活できる学校づくり検証事業」実施校によって、9月1日付で新たなスタッフが着任し、紹介と自己紹介をいたしました。さっそく今日から、こどもたちの生活を支援しています。 子どもたちの健やかな成長を今年度も皆様と力を合わせて進めてまいります。 どうぞよろしくお願い申しあげます。 



|
小平市立小平第十小学校
〒187-0022 住所:東京都小平市上水本町4丁目4番1号 TEL:042-321-5576 FAX:042-321-5561 |