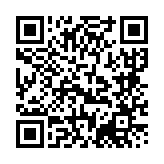|
最新更新日:2024/05/31 |
|
本日: 昨日:48 総数:282105 |
12/28 よいお年を

冬休みに入った昨日今日は出勤している職員の数も少ない。今日は昨日よりもさらに少ない。2学期も忙しい毎日だったので、宿院には冬休み中はゆっくり休んでリフレッシュしてほしい。私も明日からの年末年始休暇は、しっかり休んで英気を養いたい。 年末年始休暇明けの4日も学校閉庁日となるので、学校の業務が再開されるのは1月5日からとなる。どうぞ、良いお年をお迎えいただきたい。 12/27 表彰





消防写生会で入選した前回欠席した2年生男子。 日本武道総合格闘技連盟主催第56回RF武道空手道関東地区大会レギュラークラス小学4年生の部で準優勝した4年生男子。 ジャクパスポーツクラブ主催第33回東京支部体操競技大会1年生の部のマットで第6位、個人総合第9位の1年生男子。 同大会1年生の部のマットで第4位、跳び箱で第5位、個人総合で第6位だった1年生男子。 同大会2年生の部の跳び箱で第1位、個人総合で第6位の2年生女子。 東京書芸協会月例競書作品で最優秀賞を受賞した5年生男子。 ミニバスケットボールの小平秋季大会女子の部で優勝した小平シャイニングガールズに所属している4・5年生女子2名。 同大会男子の部で優勝した小川ミニバスケットボールクラブに所属している4・6年生男子3名。また、この男子チームは多摩リーグ第120回冬季大会で敢闘賞を受賞しているので、そちらも表彰した。 2学期の後半に結構多くの表彰ができたことを嬉しく思っている。3学期も子どもたちの活躍ぶりをなるべく多く表彰していきたい。 12/24 終業式の話 成長

今日で令和3年度の2学期が終わります。コロナ禍の中、始業式は放送で行いましたが、少しずつ感染拡大が収まってきて、全校朝会を対面とテレビのハイブリッドで行うようになり、今日は、全員で終業式を行うことができました。普段の授業でも少しずつできるようになったことが増えてきました。その中でも遠足や社会科見学、生活単元見学、移動教室などの校外学習に行くことができたことが、一番嬉しかったという子は多いと思います。 そんな2学期の間に、皆さんは心も体も成長しました。今日は、皆さんに「あゆみ」が渡されます。その「あゆみ」には、2学期の皆さんが成長した姿が、いっぱい書かれています。その中で、先生が思う皆さんの一番成長したのは態度面での成長だと思っています。 休み時間は楽しく元気に遊んでいる皆さんですが、授業中は集中して学習する子が大変多いです。校外学習に行ったときには、どの学年も「十二小の顔」として、約束を守って行動できました。そして、今、先生の話を聞いている態度もとても素晴らしい子が多いです。このように態度面で立派に成長した皆さんは、学習面でも運動面でも成長しています。3学期にさらに成長してくれることを楽しみにしています。 そんな3学期の前に、皆さんが楽しみにしている冬休みが明日から始まります。コロナ禍の影響がまだ心配なので、いつもの年のようにはいきませんが、年末年始にしかできないことを経験してください。そして、大きな事故や病気に気を付けて、元気な顔で、また3学期の始業式で会いましょう。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 今日で2学期が終わります。この2学期、子どもたちは、いろいろな面で成長しました。ご指導に感謝します。2学期の最終日の今日、「この学年、この学級で友達と共に2学期を過ごせたからこそ成長できた。」という気持ちにさせて、冬休みを迎えられるよう指導を工夫してください。お互いの成長を認め合ったり、お互いに感謝の気持ちを表したりできるといいです。 ○ 子どもたちのメリハリのある態度は本当に素晴らしいです。特に、授業中に集中して学習に取り組む子が多いことを嬉しく思っています。また、校外学習に出かけた時には、どの学年の先生方も「十二小の顔」を子どもたちに意識させてくださいました。そのおかげで、子どもたちも約束を守りながら楽しい思い出も作ることができたのだと思います。これからも楽しむときと集中するときのメリハリをつけることができる態度を、さらに伸ばしていきましょう。 ○ 明日から冬休みです。コロナ禍の影響は、まだまだ予断を許しません。しかし、年末年始に外出する子も昨年よりは増えると思われます。子どもたちには楽しい冬休みを過ごしてほしいですが、反面、生活のリズムが乱れがちになることも心配です。また、交通事故、お金の使い方、SNSによるトラブルなど、生活指導面で心配なこともたくさんあります。冬休みに入る前にもう一度、「冬休みの生活」についてお話しください。 〇 コロナ禍の中でも、学校行事や教育活動が少しでもできるように、先生方が工夫や変更を加えて計画・実施してくださいました。おかげで、教育活動の成果を上げることができました。本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。3学期は、短いですが、その中でもまた、コロナ禍への対応や年度末へ向けて忙しい毎日が続きます。展覧会、えがおまつり、研究発表会、卒業関連の活動もあります。体調を整えるためにも、冬休み及び年末年始休暇は、先生方もゆっくり休んでリフレッシュしてください。 以 上 12/23 霜柱
今週に入って朝の冷え込みが厳しくなってきた。正門前の学校園の土には霜柱が立つようになった。そんな霜柱に興味深げな子どもたちが低学年に多い。霜柱を見付けて感嘆の声を上げている子もいる。また、霜柱を掘り起こして手のひらに乗せて霜柱が解けるのをじっと見つめている子もいる。中には、登校中の道端できた霜柱をわざわざ持って来て、正門前に立っている私に見せてくれる子もいる。ふかふかしている土でできたのだろうその霜柱はとても大きいので、子どもたちも見逃せなかったのだろう。それくらい「霜柱」は子どもたちにとってとても興味のある存在なのだ。また冬場しか見られないので貴重な存在なのだろう。
霜柱に興味をもつことで、自然の不思議さを感じることができる。自然界には、その他にも不思議なことがたくさんある。そんな不思議さに出会うことで、理科好きな子も育つと思う。 あと2日で2学期が終わり冬休みに入る。冬休み中にも散策しながら、冬ならではの自然の不思議さに触れる機会があるといい。 12/22 体育授業研修会





子どもたちは自分で考えた回り方で楽しんだり、さらに、その動きに工夫を加えたりして楽しんでいた。また、友達の良い動きを真似して楽しんだりしていた。子どもたちはすすんで運動に取り組んでいた。 この研究授業は、多摩地区の各市町村教育委員会に所属している2年次の指導主事の研修会でもあった。30名ほどの指導主事が、この授業を参観してくれた。そして、気付いたことやアドバイスを残してくださった。その内容はとても参考になるものであった。本校の体育の研究に生かせる内容ばかりであった。ご指導いただいたことを基にして、研究をさらに深めていきたい。 12/21 給食運営委員会

今年度は、緊急事態宣言中の1学期には実施できなかったので、今回が第1回となり、また最後の委員会となった。会食は黙食で行い、その後意見交換した。意見交換では、気運営委員会の意義や給食の感想、子どもたちの様子、献立や調理の工夫などの話が出た。 子どもたちにとってバランスがよく、また健康に良い給食を提供するための栄養士の献立の工夫や調理員の頑張りなども改めて共通理解できた。いつも美味しい給食を提供してくれる給食室に改めて感謝したい。 今回の給食運営委員会はとてもいい情報交換の場となった。子どもたちも以前に比べて残さず食べるようになってきている。給食室には今回の委員会を受けて、さらに美味しい給食をこれからも提供してほしい。 12/20 2学期最終週

コロナ禍の中だったが、運動会や移動教室、遠足、社会科見学などの行事ができたことは嬉しい出来事だった。また、普段の学習の中でもいろいろな活動を工夫してできるようになった。人数限定・時間限定だったが学校公開も行うことができ、そんな日常の子どもたちの様子を、ご参観いただくことができたのもよかった。 12月に入って、そんな2学期のまとめに入った。各担任は、見通しをもって早めに学習面や生活面のまとめをしてくれていた。成績処理や学期末の事務作業も早めに進めてくれている。最終週は比較的余裕をもって子どもたちと生活できそうである。2学期末のお楽しみ会を計画しているクラスもある。 子どもたちには最後まで楽しい思い出を作ってほしい。そのためにも子どもたちの体調管理には十分気を付けていきたいので、残り5日間、各ご家庭でも最後までご協力をよろしくお願いしたい。 12/17 社会科見学引率





市役所では、全員で市議会場で議場や小平市についての説明を受けた後、2グループに分かれて、屋上や教委育委員会など庁内施設を回った。晴天で風があったので、屋上からは東京スカイツリーまでのはっきり見える眺めの良さに子どもたちは感動していた。グリーンロードでは、道沿いの景色を楽しんだり、施設をしっかり見学した。紅葉がきれいで感動していた。また、本校学区にある玉川上水沿道との違いも感じていた。3年生の子どもたちは、他の学年同様、校外学習の約束をしっかり守って見学することができた。とても立派であった。 これで全学年が校外学習を実施することができた。なかなか校外学習ができなかった中で、10月末から少しずつ校外に出ることができ、11月から遠足や社会科見学、移動教室を実施した。久しぶりの各学年の校外学習の様子を見たくて、今年度は全部引率に行ってきた。どの学年も、校外へ行くときは自分たちが「十二小の顔」であるという意識を高めて、約束を守って行動できていた。そんな様子を見ることができたので、忙しかったが行ってよかった。 12/16 えがおまつり





2月初旬に行うので、12月に入ってから各クラスで「えがおまつり」でどんなお店を開くのかの話し合いが行われている。1年生はもちろん2年生も初めての「えがおまつり」になるので楽しみにしているようである。また他の学年も2年ぶりなので、楽しみにして話し合っている。 本来ならば、高学年のお店に低学年の子どもたちが行って楽しむとともにそこで学んだことを自分たちのお店に生かすことができるのだが、その経験ができないことは残念である。しかし、先生方から一昨年度までのお店の紹介もしていただきながら考えているようである。12月中にはどのクラスもお店を決定する。そして、1月に入ったら少しずつその準備を始める。どんなお店になるのか楽しみである。 12/15 にいだんご
昨日、小平冬野菜煮だんごの話をした。栄養士が作成した動画に、煮だんごが小平市の伝統料理であるという説明があり、その説明の中で、昔は「にいだんご」と言っていたことが紹介されていた。私も、教員時代から長く小平市に勤務していて小平市の伝統料理の中に「だんご」があることは知っていたが「にいだんご」という名前だったことは、前任校での校長時代であった。
当時、3年生が総合的な学習の中で、七輪を使ってお餅を焼くという社会科の発展学習をしていた。コミュニティ・スクールのメンバーでの会合の中で、お餅を焼くのもいいが、どうせなら小平の伝統料理である団子を焼くことことにしようということになった。さらにその団子について、地域の方にゲストティーチャーの方にいらしていただいて学習することになり、その打合せの際に初めて「にいだんご」という名前を知った。 その3年生の活動は、だんごの生地を地域や保護者の方が作ってくださり、それをも子どもたちが丸めたり好きな形にしたりして、七輪で焼いて食べる活動になった。もちろん七輪の火の管理も保護者や地域の方々であった。多くのボランティアの方々のおかげでできた活動となった。さらに保護者と地域の方のいい交流の場ともなった。今でも続いているのだろうか。コロナ禍で途切れているかもしれないとも思う。 あの時の子どもたちもそうだが、関わった大人の方々の笑顔が忘れられない。あのような地域や保護者の方々と連携した授業を、本校でもできるといい。そのためにも早く、このコロナ禍が収束してほしい。 12/14 小平冬野菜煮だんご

小平市では、このように市内で採れた地場野菜を使うことを推奨している。給食でも時々「小平野菜の〇〇」という給食を出している。さらに小平野菜の〇〇の日」という市内一斉に同じ給食を提供している日も設定している。 今回の「煮だんごの日」には、栄養士が、動画とパワーポイントの資料を作ってくれた。子どもたちは、その日の給食を食べながら、その動画を視聴した。動画の内容は、小平市の伝統料理である「煮だんご(にいだんご)」についての説明や小平市で採れる代表的な7種類野菜についてのクイズを出してくれた。最後に冬野菜の良さについての話もあった。 子どもたちは、給食を食べながら、冬野菜煮だんごに入っている野菜を確認したことだろう。給食を食べながらいい食育の学習にもなった。視聴資料を作成してくれた栄養士に感謝である。 12/13 縦割り班遊び





昨日は前日の雨のためできた水たまりが多少残っていたが、午前中には青空が広がり気持ちのよい天気の中、実施できた。 どの班も、6年生が考えたボールを使った遊びや様々な鬼ごっこ、リレー、だるまさんがころんだなどを楽しんでいた。6年生が2年生を気遣って活動していたのがとてもよかった。参加していた5年生も、そんな6年生の様子を見ながら、4か月後の最高学年になることを考えたことだろう。 2学期の縦割り班遊びはこれで終了である。3学期に3回あり、どの学年もあと1回ずつ6年生と一緒に遊ぶことができる。どの学年も楽しみにしていてほしい。 12/10 不審者対応訓練

教員が不審者に対応する者と児童管理をする者に分かれての訓練である。子どもたちにとっては、警察が来て不審者が逮捕されるまでの間、教室内でひたすら静かにして気配を消す訓練であった。 不審者が確保されたという設定の後、放送でその旨を伝え各学年主任が在籍児童の人数確認をして本部に報告して訓練が終了であった。その後、私の方から放送で子どもたちに話をした。今回子どもたちは教室内でじっとしていて動くことはなかったので、今回の訓練の内容について説明した。そして、自分や友達の命をを守ためにも、警察が来るまでひたすら静かにしていることの重要性について話をした。 訓練後、担任の教員から話を聞いたが、ほとんどのクラスで、子どもたちは適切な行動をとることができたようである。不審者が侵入してくるというのは、子どもたちにとっては大変怖い経験である。それなのにしっかり約束を守って行動できたのは素晴らしいことである。これからも緊急な場合でも冷静な行動をとれるような子に育ってほしい。 12/9 学校公開アンケート
11月22日(月)に学校公開を行い、その後、学校公開アンケートを配布させていただいた。その回答を多くの皆様からいただいた。感謝している。私も全部目を通させていただいた。
感染拡大防止のため、各保護者の皆様には、各ご家庭1名ずつ1時間限定の授業公開としたののだが、およそ2年ぶりの学校公開の感謝の声も多くいただいた。また、「もっと参観したかった。」というお声もいただいた。その通りだと思う。我々教員もいろいろな授業での子どもたちの様子を参観していただきたかった。早くそんな学校公開ができるといい。また、今回は、こんな方法で実施するといいのではないかというご提案もいただいた。ありがたかった。さらに、教師の指導法等についてもご意見をいただいたので真摯に受け止めていきたい。 いただいたご意見を元に、授業改善したり学級経営や学年経営も改善したりしていきたい。また、次回は1月に展覧会に合わせて土曜公開を実施する。今回は平日だったが、次回は土曜日なので、より多くの方が参観したいところだろう。そんな保護者の皆様の思いを少しでも生かして公開できるように考えている。詳しくは、これから配布される3学期の学校公開のお知らせをご覧いただきたい。 12/8 消防写生会入選作品
今週月曜日の全校朝会で表彰した「消防写生会」の入選及び優秀賞を受賞した作品の複製画を図工室前に展示しています。






12/8 保護者会

さて、先週29日(月)から学年ブロックごとに実施してきた保護者会が今週6日(月)のけやき学級の保護者会ですべて終了した。私も出張で不在だった時を除いて、各教室の様子を見に行ったが、多くの保護者の皆様にご参会いただいていて嬉しく思っている。お忙しい中、時間に都合を付けてご来校いただきありがとうございました。 各担任から、2学期の子どもたちの成長ぶりや今後指導していくこと、冬休みの生活などについて短い時間であったが、報告・説明させていただいた。また前回続き、今回も1人1台のタブレットを実際に保護者の方にも使っていただいたクラスもあった。 また、保護者会では、学校側からの報告だけでなく、保護者の皆様からの話もしていただいた。当初の予定では2学期の保護者会は公開授業後に行う予定であったが、3密を避けるために、学校公開を別日に設定し、事前にご覧いただいていた。久しぶりの授業公開を受けてのお話もいただいたようである。いただいたご意見を参考にさせていただき、クラスや学年、学校全体で、それぞれ今後の教育活動を行っていきたい。 次回の保護者会は、2月下旬の予定である。こちらは1年間のまとめの保護者会になるので、また多くの保護者の皆様のご来校をお待ちしている。 12/7 表彰





国際空手道連盟極真会館城西世田谷東支部主催第14回支部内型交流試合太極1小学1年生の部で優勝した1年生。 消防写生会で入選した2・3年生、けやき学級の子どもたちの入選者15名と優秀賞の5名の合計20名。 第20回東京都少年剣道学年別個人錬成大会小学3年生の部で準優勝した3年生女子1名。 第47回小平市少年少女マラソン大会で5年男子の部2位と4位、5年女子の部2位と6位、4年男子の部4位と10位、3年男子の部3位、3年女子の部9位の合計8名の子どもたち。 第59回小平市民体育祭の少年サッカーの部2位パートB第3位だった小平FCウイングスブラックの5年生6名。 同大会2位パートB第1位だった小平FCウイングスレッドの5・6年生3名。 また、今年度、本校はスポーツ庁から全国学校体育研究優良校として表彰された。体育の研究を推進してきた研究主任に代表して賞状を渡した。 今回汰たくさんの表彰をすることができた。校庭で朝会に参加していた3・4年生、けやき学級の子どもたちが大きな拍手で祝福してくれた。次回は2学期修了式の際に表彰する。今日表彰した消防写生会の入選者1名が欠席だったので、その時に表彰する。また他にも表彰できる子がいるので、2学期最後の表彰も楽しみである。 12/6 全校朝会の話 体育

12月に入りました。だんだん寒い日が増えてきています。しかし、皆さんは、休み時間の外遊びを楽しんだり、体育の時間にいろいろな運動のすすんで取り組んだりしています。そんな姿を見ると先生は嬉しく思います。 十二小の先生方は、この2年間、運動することが大好きな子が増えてほしいと思い、いろいろなことを考えています。朝の時間に「朝活タイム」を始めたのもその一つです。 また、体育の時間についても、皆さんが楽しく学べるように先生方は研究を重ねています。たくさんの先生方が見に来た研究授業を行ったクラスもあります。その研究授業に向けて、担任の先生ではない同じ学年の先生が体育の授業を行ったクラスもあります。来年2月25日には、他の学校の先生方に、皆さんの体育の学習の様子を見ていただく体育の研究発表会を行う予定です。 そんな体育の研究の取組が認められて、日本学校体育研究連合会とスポーツ庁から「全国学校体育研究優良校」に十二小が選ばれました。あとで体育の研究を進めてくれている代表の先生に賞状を渡します。しかし、この賞状は、体育の学習を頑張ろう、そして体力を伸ばそうと頑張った皆さん全員への賞状です。 これからも、いろいろな運動に取り組んだり、外遊びをしたりして、体を動かしましょう。そして、さらに運動が好きな、元気な子に育ってください。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 教育目標達成のための12の施策1つ「健康・安全教育の充実(体力の向上のために)」を目指して研究をしていただいています。おかげで「全国学校体育研究優良校」として表彰されました。本校は、令和元年度から体育の研究を始めました。昨年度はコロナ禍の中でしたが、できることから研究を始めていただきました。また、今年度は東京都体育研究会(小体研)研究協力校として、小体研と連携して体育の研究を進め、積極的に小体研各領域部会と関わっていただきました。2月25日には、研究協力校として研究発表会があります。同時に小平市研究推進校の指定も受け、来年度は、その研究発表会もあります。これからも、子どもたちの体力向上と健康の保持増進を目指し研究を深めましょう。 〇 当初の予定だった11月19日の小体研多摩地区発表大会が延期になったのは残念でしたが、2月25日小体研研究発表大会(多摩地区会場)で、研究の成果を発表することができます。延期によって変更点がいろいろ出てきましたが対応していただきありがとうございました。先生方の研究に対する前向きな姿勢が嬉しいです。2月の研究発表大会まで2か月ちょっとです。研究推進委員会を中心に、小体研と連携しながら、しっかり準備を進めていきましょう。 ○ 11月の生活目標は「外で元気に遊ぼう」でした。目標通り、外で元気に遊んでいた子が多く、嬉しく思いました。11月が終わり12月に入り、次第に寒くなりますが、引き続き外遊びを励行していきましょう。外遊びができる日は子どもたちに声を掛け、外遊びをさせましょう。また、できる限り先生方も、休み時間の子どもたちの様子を見たり一緒に遊んだりしてください。児童理解も深まります。外遊び後の手洗いうがいのご指導も、よろしくお願いします。 以 上 12/3 消毒活動
昨年度の臨時休校明けの分散登校の時、分散登校の前後半の間の昼の時間と放課後の2回、教員が、教室、廊下、階段、トイレなどの消毒活動を行っていた。その様子を知った青少対の方々が、コミュニティ・スクール健全育成プロジェクトチームと連携して消毒ボランティアを募って、放課後の消毒活動を行ってくださってきた。教員の負担も減って、大変助かった。
さらにおやじの会の方々も、昨年度・今年度はコロナ禍のため通常の活動ができなかったので、少しでも子どもたちのため、学校のために活動したいということで、今年度から学期に一度「消毒大作成」と称し、土曜日に校内の消毒活動を実施してくださっている。2学期も11月20日(土)に実施してくださった。 そんな消毒活動だが、ここのところの感染状況の収束を受けて、放課後の消毒活動を11月いっぱいで終了することになった。今までの活動には本当に感謝の気持ちでいっぱいである。ところが、ボランティアのメンバーからは、2学期いっぱいは活動したいという話があり12月も継続して行っていただくことになった。その気持ちにさらにありがたく思った。子どもたちを思う気持ちが嬉しう。残りひと月だが、最後までよろしくお願いしたい。 12/2 避難所開設準備委員会
11月20日(土)に、第3回の避難所開設準備委員会があった。
本校は、まだ避難所運営マニュアルを作成していなかった。そこで、昨年度コミュニティ・スクールの研究を始めた時から、避難所運営マニュアル作成プロジェクトチームを立ち上げて、そのメンバーで運営マニュアルを作成してきた。さらに、途中から地域の方々にも数人に入っていただいてご意見をいただいてマニュアル案を完成させた。 本来、避難所運営マニュアルは、保護者や地域の方々とともに作成していくものである。そこで、プロジェクトチームで作成したマニュアル案を、広く学区内の自治会の方々にも見ていただく会をとして、第1回避難所開設準備委員会(避難所マニュアル作成会議)を7月に開催した。さらに9月の第2回会議を経て、今回の第3回でマニュアルを完成させた。しかし、マニュアルは、実際に動いてみてブラッシュアップしていく必要があるので、来年度に避難訓練を実施していくことにもなった。 第3回の会議後は、その避難訓練や今後の動きについて、参加者の中で立ち上げた避難所運営チームごとに話し合いが行われた。単にマニュアル作成に終わらず、この委員会を「小平第十二小学校避難所委員会」として動いていくことになった。コミュニティ・スクールのプロジェクトチームから地域と連携した取り組みとなったことを嬉しく思っている。これからもコミュニティ・スクールとして地域と連携した授業や教育活動、事業を展開していきたい。 |
小平市立小平第十二小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |