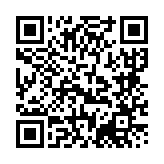|
最新更新日:2024/06/03 |
|
本日: 昨日:57 総数:282218 |
6/30 クラブ活動





子どもたちは、それぞれの活動を楽しんでやっていた。特に4年生は、3年生の3学期から4年生にから始まるクラブ活動を楽しみにしていて、それがようやく実現でき嬉しそうだった。 クラブ活動は同じ趣味やスポーツが好きなメンバーが集まってきている。お互いに話が合うし、切磋琢磨してお互いを高め合うことができる活動である。このコロナ禍で活動に制限がかかっているクラブもあるが、担当の教員がいい活動ができるように工夫してくれている。ありがたいことである。 子どもたちには、クラブ活動をこれからも楽しんでほしい。特に6年生は、小学校最後のクラブ活動である。回数は少なくなったが、下級生をしっかりリードしながら、楽しんでほしい。 6/29 けやき宿泊学習





子どもたちは、1日目の山登りと葉っぱスタンプでの作品づくり、夜の肝試しと花火、2日目の川遊びとマスのつかみ取り、買い物学習、どれもよく頑張り、いっぱい楽しんで活動することができた。また6年生のリーダーが下級生によく声掛けして生活したり、食事係が食事の準備を頑張ったり、代表の言葉をそれぞれ頑張ることもできた。さらに最後の昼食後、自ら進んで食堂の方々に「ごちそうさまでした。」や「ありがとうございました。」と言えた子もいた。 たった2日間だったが、子どもたちの成長を感じることができた。事前学習や準備から頑張ってきた成果であろう。けやき学級の担任や学習補助員、そして引率した教員も子どもたちへの支援を頑張ってくれた。感謝である。 6/28 保護者会

昨年度は、保護者会を書面開催という形で行ったが、今年度は4月の保護者会から30分という短時間で行うことにした。書面開催では、なかなか担任の思いが伝わらないからである。4月に実施した保護者会には多くの保護者の皆様にご来校いただき、各担任と顔合わせができたとともに、各学年や担任から1学期の学年・学級の経営方針を伝えることもできた。今回は、1学期の子どもたちの学校での様子や成長ぶり、そして夏休みの生活について各担任からお話させていただく。 1学期は学校公開を実施することができなかったので、学校でのお子様の様子をご覧いただけた機会がほとんどなかったので、ぜひ保護者会で直接担任から子どもたちの様子をお聞きいただきたい。しかし、コロナ禍である状況は変わらない。決して無理はしていただかなくて構わない。保護者の皆様には、各自で出欠席の判断をよろしくお願いしたい。 6/25 宿泊学習引率2日目

昨日の1日目は、午前中に自然散策体験、午後は作品制作をした。午前中の城山登山は傾斜がキツいところが多かったが、声を掛け合って頑張って登り、無事下山できた。午後の「葉っぱスタンプ」の作品作りも頑張って素敵な作品を作ることができた。夜の肝試しや花火も楽しんでいた。子どもたちは、とても元気に1日目を楽しく過ごすことができた。 今日は朝食後、荷物準備と掃除をし、自然休暇村「山渓」でマスのつかみ取り体験や川遊びを楽しむ。その後宿舎へ戻って昼食を取り、帰途に着く。途中秋川ファーマーズセンターで買い物学習としてお土産を買う。学校着は15時10分の予定である。天気予報では午前中は雨は降らないようなので川遊びはできそうである。しかし、天気情報には気をつけていきたい。 今日も子どもたちが楽しく活動できるように支援していきたい。 6/24 宿泊学習引率
今日と明日、特別支援学級「けやき学級」の3〜6年生が1泊2日の宿泊学習に行ってくる。私もその引率に行ってくる。
今日は8時に学校を出発し、バスで宿泊先である、あきる野市の「戸倉しろやまテラス」へ行く。その後自然散策をして宿舎に戻って昼食、開講式を行い。午後は宿舎の図工室で作品を制作し、自由時間・入浴・夕食となす。夜は肝試しと花火である。朝方までの雨も上がり、今朝の天気は曇り。今日はこの後も曇りで、にわか雨が降る予報も出ているが1日目の行事はほぼできそうである。 けやき学級の宿泊学習は、昨年度は中止になったので、2年ぶりである。今回は、宿泊先が貸し切り、公共交通機関を使わずに貸切バスでの往復という形にして実現にこぎつけた。コロナ禍の中、子どもたちの健康面には十分配慮して2日間を過ごさせたい。2日間学校を不在となるが、ご理解いただきたい。 6/23 研究授業
今日の午後に、先週に引き続いて今年度2回目の研究授業を実施する。11月に体育の研究発表会を実施する予定なので、今年度はそれまでに5つの研究授業を予定している。
今回は、5年生の保健領域の授業である。前回は校庭での「ティーボール」だったが、今回は保健の「けがの防止」なので、教室で行うことになる。教員全員が教室へ参観しに行くことは、今はできない。教室には、指導助言をいただく講師の先生と我々管理職、そして、高学年担任の教員が参観する。残りの教員は、授業の様子を撮影して、それを別室でライブで観るハイブリッドの形をとる。 そのような研究授業の仕方は、本校では初めてではあるが、実際にこの形で行っている研究会は、最近よくある。11月の研究発表会がどのような形で行っていくかまだ不透明な状態であるので、今回は一つの方法として試してみるいい機会である。 研究協議会も前回、教員一人1台のパソコンを使って、効率的な意見交換を試したことで見えてきた改善点を生かしてブラッシュアップして行っていく予定である。 パソコンの活用は、これからの教育に欠かせない。研究を通して、パソコンの活用についての教員の力も伸ばしていきたい。 6/22 改訂ガイドライン
緊急事態宣言解除、そして、7月11日までの蔓延防止等重点措置に伴って、「小平市立学校版感染症ガイドライン(新型コロナウイルス感染症)」が、昨夕に改訂された。そして、今日6月22日から改訂ガイドラインに従って教育活動を行っていく。このガイドラインは市のホームページで見ることができるので、ぜひご覧いただきたい。
今回の改定によって教育活動が緊急事態宣言時よりも緩和されるのではと、少し期待はしていたが、原則、これまでのガイドラインの方針を継続ということになった。蔓延防止等重点措置に移行したことや感染拡大が未だ収まらない状況では仕方がないことである。 しかし、その中で、校外学習、学校公開等を目前に控えた学校もあること、水泳指導は、児童・生徒の命を守ることに大きく関わることから、これまでのガイドラインに基づいた対応を基本としつつ、必要な取組については、学校と教育委員会事務局が協議し、実施の判断を行うこととなった。 本校のけやき学級は、明後日から1泊2日の宿泊学習を控えている。水泳指導も含め、早速、今日、事務局と相談してみることにする。水泳指導については、いつから再開されるか保護者の皆様にも、早めにお知らせできず申し訳なく思っている。昨日も水泳バッグを持って来ていた子どもたちもいたが、残念ながら入ることができなかった。今日の相談で再開日程が決まると思うので、もう少しお待ちいただきたい。 改訂ガイドラインを基に、本日、校内で会議を行い、今後の行事や教育活動について考え、全職員で共通理解を図る。その上でホームページやメールにてお知らせする。ご確認をよろしくお願いしたい。 6/21 全校朝会の話 プール
おはようございます。
緊急事態宣言が解除され、先週までできなかったことが、少しずつできるようになります。延期していたプールの学習もいよいよ始められることになりそうです。楽しみに待っていてよかったですね。しかし、今年は、いろいろなことに十分気を付けてプールの学習に取り組みましょう。 1・2年生の皆さんにとっては、初めての小学校でのプールの学習になります。また、3年生以上の皆さんにとっても2年ぶりのプールの学習になります。コロナ禍の中でのプールの学習なので、2年前までとプール内での約束や学習の仕方が違います。また、プールに入る前や出た後の行動も違います。いろいろな約束事をしっかり守ってプールの学習をしましょう。特に一番大事なのは、おしゃべりなどの声を出さないことです。プールにはマスクを外して入ります。楽しいでしょうが声は出さないという約束はしっかり守りましょう。 また、久しぶりのプールなので、体は冷たい水に慣れていません。体調のことを第一に考えてプールに入るようにしましょう。そして、少しずつ体を水に慣らしていきましょう。 先生は、皆さんの泳ぐ力が少しでも伸びてほしいと、いつも思っています。しかし、今年は、皆さんが水と親しむだけでよいと思っています。決して無理をせず健康や安全に十分気を付けてプールの学習をするようにしましょう。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ いよいよプールでの学習が始まります。緊急事態宣言延長で2週間延びてしまったので、それぞれの学年で時数の確保が難しい状況であると思います。動画視聴など教室での学習と合わせて指導していってください。また、今年度は、2年ぶりのプールになるので、技能向上よりは水に親しむことを目標にしましょう。そして、子どもたちの健康面や安全面には十分配慮して指導していきましょう。 ○ プール学習担当の先生中心に部会の先生方、準備や変更等ありがとうございました。コロナ禍で、例年通りの指導ができません。プールまでの動線もいつもと違います。教室での事前指導は行うとともに、初日は丁寧に動線を確認したりプール内やプールサイドでの動き方をしっかり確認したりしていきましょう。また、声を出さないことを徹底しましょう。 ○ 今年度は、夏休みのプールも例年通りにはできません。人数制限があるので、学年内でも分かれて入る必要があるからです。子どもたちがプールに入る回数は減りますが、安全に気を付けて行うようお願いします。 以 上 6/18 緊急事態宣言解除

2週間遅らせてきていたプールの学習も、来週以降始まる予定で各ご家庭でご準備いただきたい。特別支援学級であるけやき学級の1泊2日の宿泊学習も来週末に予定していたので行くことができる。クラブ活動や、縦割り班活動なども少しずつできるようになってくるだろう。詳しくは学校からのお知らせのページでお知らせしていく。 来週月曜日の全校朝会も校庭に集合して行う予定である。4月12日の全校朝会以来、久しぶりに子どもたち全員を見ながら朝会の話ができることを、私も楽しみにしている。 しかし、いつまた感染が拡大するか分からない。学校でも。マスク着用や手洗い、3密は避けるなど、感染拡大防止のための行動を、引き続き指導していく。各ご家庭でもご協力をよろしくお願いしたい。 6/17 研究授業





研究授業後の協議会では、教員一人1台のパソコンを使った協議を行った。事前に、授業を観ての感想や意見、質問をパソコンに入力し、それを集約して協議をする形を初めてやってみた。前回は発言した教員が限られたが、今回は、全員からいろいろな意見や質問が寄せられたのは、授業者にとっての良かったのではないかと思う。 講師の先生からは、ボール運動の基本的な考え方から体育科の指導方法まで、いろいろご指導をいただいた。今回の「ティーボール」は、11月の研究発表会でも他のクラスで実施する。今回の改善点を生かして、計画を立てていってほしい。 6/16 朝活タイム





1回目を経験した1・2年生の中には朝活タイムで遊んだ遊びを休み時間にも遊びたいという声が子どもたちから上がったという。そして、早速、クラス遊びの時間に遊んだという。これは、朝活タイムのねらいの一つである。いろいろな遊びを経験することで、すすんで体を動かしたり、経験した遊びを日常的に遊んだりすることを繰り返し、外遊びや体を動かすことが好きな子どもたちに育ってほしい。3〜6年生も朝活タイムを楽しんでいたので、今後につながるといい。 次回は、来週、けやき学級が初めて行う。また1年生は2回目の活動になる。どちらも活動を楽しんでほしい。 6/15 展覧会テーマ

各学年で、このテーマに向けて作品を作っていってほしい。展覧会は、例年なら11月中旬頃に行うのだが、今年度は体育の研究発表会と重なる時期なので、1月にずらした。まだ半年以上もあるので、各学年でじくりと取り組んでほしい。 また、一昨年、展覧会を行い、昨年度は学芸会の予定だったが中止とした。その学芸会を今年度に延期することも考えたが、コロナ禍の3密も考え展覧会とした。現段階では予定通り行うつもりだが、もしかしたら入場に制限をかけるかもしれないが、保護者や地域の皆様には、展覧会開催を楽しみに待っていていただきたい。 6/14 教育実習終了





11日(金)には、実習のまとめとして4人全員が1時間ずつ授業研究を行った。それぞれ指導教官の担任の先生に指導してもらいながら指導案を作成し、授業に臨んだ。それぞれの研究授業には、指導教官以外の先生方も時間を取って参観してくれた。そして、放課後の研究協議会でもいろいろなアドバイスをしてくれた。 また、最終日の12日(土)には各クラスで「お別れ会」があった。ゲームをしたり出し物を見たり楽しみながらいいお別れができたようだ。 実習生としては、すべてがうまくいったわけではないだろうが、手ごたえは感じたことと思う。4人の学生は、この大変真面目に実習してきた。十二小での実習で学んだことを生かして、いい教員になってほしい。 6/12 土曜授業

また、今週は急に気温が高い日が続き、休み時間や体育の学習の後の子どもたちは、だいぶ暑がっていた。他の地域では熱中症で児童生徒が搬送された報道もあった。6日間の登校と気温が高かったことで、本校の子どもたちも疲れている子が多いと思われる。今日の午後と明日の日曜日はゆっくり休養を取らせてほしい。そして、来週月硫黄日には、また元気に子どもたちが登校してくることを楽しみにしている。 6/11 学校公開中止
明日12日(土)は、年度当初の予定では今年度最初の学校公開日であった。しかし、緊急事態宣言が延長されたので、残念だったが中止とした。令和3年度が始まって2か月が経った。に4月に入学した1年生の小学校での生活をぜひご覧いただきたかったし、他の学年も進級した子どもたちの学校での様子を見てほしかった。本当に残念である。
昨年度は一度も学校公開ができなかったので、今年度の1年生だけでなく、2年生も学校での様子を保護者や地域の皆様にご覧いただけていない。最後に公開できたのは、令和元年度の1月だった。およそ1年5か月、子どもたちの学校の様子をご覧いただけていない。大変残念だが、その分、このホームページで子どもたちの様子を毎日お伝えしていくので、今後もぜひご覧いただきたい。また、今月末から始まる保護者会は、現段階では実施する予定である。短時間にはなるが1学期の子どもたちの様子も各担任から話をさせていただく。この状況なので、無理はしていただかなくて構わないが、出席可能な方はご参会いただきたい。 次回の学校公開は、9月11日(土)に予定している。こちらはできるといい。また、明日は、公開はしないが土曜授業である。午前中、子どもたちは学校なので、各ご家庭でご対応よろしくお願いしたい。 6/10 小・中連携の日





昨年度はコロナ禍のため実施できなかったので、およそ1年半ぶりの開催だった。本来ならば昨日は第一小学校に4校で集まり、授業参観し、分科会ごとに情報交換するのだが、緊急事態宣言発令中なので、一斉に集まらずに、小・中連携の日で初めてリモート会議の形で実施した。教員は教科等の分科会ごとに各教室に分かれて、リモートで全体会と分科会に参加した。第一小学校の公開授業も事前に撮影した動画であるが全体会の中で参観することができた。またその後行われた分科会もいい情報交換の場になった。 コロナ禍の中、教育活動が制限されているので、昨年度の各校の実践を基にしての情報交換は、自校の今後の計画にも生かせるところが多々あったことであろう。ぜひ生かしていってほしい。私は体育部会に参加したが、小学校のソフトバレーボールから中学校のバレーボールへつなげるために小学校のうちにやってほしいことなどについて情報交換でした。中学校の保健・体育の現状などの情報も大変参考になった。 子どもたちを9年間で育てていくことが大事なことである。これからも近隣小中学校で連携していろいろな活動を行っていきたい。 6/9 コース別一斉下校訓練





昨年度まで本校では、コース別集団下校訓練を実施していた。放送の指示で、各クラスからコースごとに校庭に集まり、各担当の教員と一緒に下校する訓練だった。しかし、子どもたちが集合y場所を忘れて迷ってしまうなど時間がかかり過ぎることが課題であった。そこで、計画を直し、より良い方法を担当の生活指導部会で話し合い新たな形で実施することになった。 初めての訓練方法になったが、だいぶスムーズに実施し終えることができた。今回の反省を生かして、来年度はさらにブラッシュアップした訓練を実施していきたい。また、実際に災害が発生した時も、今回の訓練の反省をを生していきたい。 6/8 朝活タイム





初日の3日(木)は、1・2年生が朝活タイムを行った。1年生が体育館で、肋木を使った遊びやゴム跳び、プラぽっくり、リバーシという遊びを行った。また2年生は校庭でナイスシュート、タイムショック、〇の字綱引き、スカットボーイ投げを行った。クラスごとに短時間ではあるがローテーションしながらいろいろな遊びを体験した。どの遊び場でも子どもたちは楽しそうに活動していた。 この活動は、東京都小学校体育研究会の体育的活動部会からアドバイスを受けた4年生の担任を中心とした本校の体育的活動部会の先生方が計画してくれた。先月の実技研修会で教員が遊びを経験した時も楽しそうだった。それを子どもたちにも伝えたいという思いで早速活動が始まった。子どもたちにとって初めての遊びも多々あった。 この朝活タイムの経験を今後の休み時間の遊びやクラス遊びに生かしてほしい。そして、すすんで遊んだり運動したりする子どもに育ってほしい。 6/7 全校朝会の話 楽しみに待つ
おはようございます。
5月31日で解除になる予定だった緊急事態宣言が、6月20日まで延長されました。そのため、先週2日から2泊3日で6年生が行く予定だった移動教室が2学期に延期されました。移動教室は小学校生活6年間の中でも、特に思い出に残る大きな行事です。それが延期されたのは大変残念なことだったのですが、6年生はがっかりせずに「楽しみは2学期に。」と前向きに捉えてくれたそうです。さすが6年生だと思い、先生は嬉しく思いました。 宣言が延長されたことで、今日から始まる予定だったプールの学習や来週行く予定だった3年生の社会科見学も延期になりました。また1年生から5年生の遠足もすでに延期になっています。しかし、皆さんは残念だという気持ちを出さずに楽しく学校生活を送ってくれています。 皆さんは「赤毛のアン」というお話を知っていますか。そのお話の中にこんな言葉があります。「何かを楽しみに待つということが、その嬉しいことの半分あたるのよ。待つときの楽しさだけは間違いなく自分のものですもの。」という前向きな言葉です。皆さんは、もう1年以上も、制限のある学校生活を送っています。しかし、先生方は、皆さんに楽しい学校生活を送ってほしいと考えて、いろいろ工夫してできることを増やしてくれています。ですから皆さんも、自分がしたいことが、もうちょっと我慢すればできるようになると前向きに考えて、これからも楽しみに待ち、楽しい学校生活を送りましょう。 これで先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 緊急事態宣言が延長され、6年生の移動教室が2学期に延期になりました。担任の先生方は、子どもたちにどう伝えようかと、いろいろ考えていただきました。4月末から5月にかけて遠足が2学期になった1〜5年生の先生方も同じです。ご支援ありがとうございます。子どもたちが前向きに考えてくれているのも、先生方のおかげです。 〇 プールの学習も、担当の先生方が3密を避けて実施できる方法を考えてくださいました。ありがとうございました。プールの学習が実施できるようになったら、3密・安全に気を付けて実施していきましょう。また、昨年度のスポーツフェスティバルをはじめとして、これまで1年以上、いろいろ工夫して、行事を実施してくださいました。今年度も、これまでの経験を生かして考えていきましょう。 〇 今日は「楽しみに待つ」という話で「赤毛のアン」の1場面を引用しました。こんな場面です。 教会の帰り道、日曜学校のピクニックをどれだけ楽しみかを力説するアンに、養母であるマリラが、 「あんたは物事を思い詰めすぎるよ。一生の間にどれくらいがっかりするか知れないよ。」 と忠告しました。それに対してアンが言いました。 「何かを楽しみに待つということが、そのうれしいことの半分にあたるのよ。・・・本当にならないかもしれないけれど、でもそれを待つときの楽しさだけは間違いなく自分のものですもの。・・・何にも期待しない方が、がっかりすることよりもっとつまらないと思うわ。」 低学年には少し難しい意味を含んだ言葉かもしれないので、フォローしてください。アンの前向きなこの言葉を胸に、頑張っていきましょう。 以 上 6/4 教育実習





今回の実習生は、東京学芸大学4年生の4名である。2〜5年生のクラスにぞれぞれ入って、指導教官の授業を参観したり私や副校長の講話を聴いたりしている。今週に入ってからは毎日1〜2時間の授業実習を行っている。毎日、その日の授業を反省し、担当の教員から指導を受けている。少しずつ授業のノウハウを身に付けてきているようである。 毎朝、私のところに挨拶に来た時に前日の振り返りを聞いてみると、少しずつ手ごたえを感じていることが分かり頼もしく思っている。しかし、まだまだ不安もいっぱいだろうから、これからもしっかり準備をして子どもたちの成長のために頑張りながら、実習生自身もいろいろな経験をして力を付けていってほしい。来週は最終週となる。研究授業もある。最後まで頑張ってほしい。 |
小平市立小平第十二小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |