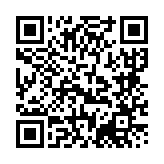|
最新更新日:2024/06/03 |
|
本日: 昨日:57 総数:282194 |
2/28 研究発表会





22日にオンラインでリハーサルを行い、25日の夕方にオンラインで2時間ほどの発表会の中で、本校の実践を発表した。これまで中心的に研究を進めてきた研究推進部長をはじめ、研究推進部会の教員に感謝である。 本校は、今年度と来年度の2年間、小平市教育委員会から研究推進校の指定を受けている。これまで3年間の体育の研究の成果を、来年令和5年1月20日(金)に研究発表会として報告する。来年こそは、公開授業、対面での発表会ができることを願っている。 2/25 長縄チャレンジ





18日の集会では、そのチャレンジの様子を動画撮影していたものを各クラスで視聴した。1年生の子どもたちは、高学年の連続跳びの速さに驚いていた。動画視聴終了後に体育委員会から各学年の最高記録を出したクラスの発表があった。その後、各クラスに記録証が渡された。集会の動画の最後に体育委員会の子どもたちも、長縄チャレンジを通してクラスの絆が深まっただろうという話があったが、私も休み時間の子どもたちの取組の様子を見ていてそう思っていた。みんなで協力してよく頑張っていた。 長縄チャレンジが終わった今週も休み時間にクラスで長縄に取り組んいるクラスがあった。取り組むたびに上達しているので楽しいのだろう。そんな機会を作ってくれた体育委員会に感謝である。 2/24 クラブ発表集会





ダンスクラブは「パプリカ」をはじめ3曲のダンスを披露してくれた。音楽クラブは「鬼滅の刃」の「炎」という曲を合奏してくれた。マジッククラブはトランプを使ったマジックなどを披露してくれた。理科クラブはスーパーボールを作る様子を見せてくれた。どのクラブの発表も興味深く子どもたちは観ていた。どのクラブも1年間の活動の成果を見せ、いい発表にしてくれた。感謝である。 集会の日に発表しなかったクラブも動画を撮影している。2月1日に3年生対象にクラブ見学が行われる予定であった。それがまん延防止等重点措置が適用されたため実施できなかった。それを見越して事前に全クラブが活動の様子を動画撮影してくれていた。来年度4月からクラブ活動に参加する3年生が視聴するために作成したのだが、どのクラブも頑張って作成した動画なので、クラブ担当の教員の計らいで、給食中にどのクラスでも見られるようにしてくれた。私も視聴したが、とても楽しく観ることができた。動画を観た3年生もきっと4月からどのクラブに入ろうか楽しみにしたことだろう。動画を作成してくれた各クラブに担当と子どもたちに感謝である。 2/22 表彰





今回は、4年生が2学期に全校に呼びかけた「服の力プロジェクト」への感謝状であった。4年生は、総合的な学習の時間にこの取組について学習した。この「服の力プロジェクト」はUNIQLOやGUを経営しているファーストりテイリング社の取組である。4年生はたくさんの服を全校から集めて貧困で困っている国へファーストリテイリング社を通して送った。それについての感謝状が、ファーストリテイリング社とUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の連名で届いたので、昨日の全校朝会で4年生の代表の子に渡した。 表彰後、4年生代表の6人から、全校へ向けての感謝の挨拶があった。全校児童の協力があっての今回の感謝状だからである。とてもいい内容の言葉であった。もうすぐ高学年になることにふさわしい言葉で成長を感じ嬉しくなった。 今回は前回の表彰に引き続き、社会への貢献活動についての表彰をすることができた。これからも子どもたちにはそのような活動をしていってほしい。 2/21 全校朝会の話

早いもので、3学期も半分が過ぎました。3学期が始まってすぐに短縄旬間があり、皆さんは体育の時間や休み時間にどんどん縄跳びの技に挑戦し、いろいろな技ができるようになりました。また、短縄旬間が終わると、長縄チャレンジが始まりました。先週18日まで、皆さんはクラスで協力して新記録を目指して取り組んでいました。そして、初めの記録よりも、多くのクラスが、記録を大幅に伸ばすことができました。短縄も長縄も、皆さんが頑張って取り組んでいる姿を見ていて、先生はとても嬉しかったです。 初めはできないことでも、諦めずに挑戦し続けることできるようになります。それは、練習を繰り返しているうちにコツをつかむことできるからです。それを実感した子はいたはずです。また、友達と一緒に練習するといいことに気付いた子もいると思います。お互いに教え合うことができるし、できる子の跳び方を見て真似することでコツをつかめることもあるからです。 2月は「ふれあい月間」です。これからも友達と仲良く縄跳びなどで遊びながら、友達と一緒に楽しんだりいろいろな運動ができるようになったりするといいです。寒い日が続きますが、寒さに負けず、すすんで体を動かして、運動が好きな、元気な子に育ってください。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 短縄旬間の取組ありがとうございました。先生方も一緒に縄跳びをしたり声掛けしたりしていただいたおかげで、子どもたちも縄跳びに意欲的に取り組んだのだと思います。また、長縄チャレンジの取組もありがとうございました。クラスの絆も深まったのではないでしょうか。 ○ 小学校の時期の子どもたちは、体力面では、筋力や持久力よりも巧緻性が大きく伸びます。巧緻性とは、サッカーのリフティングやドリブル、バスケットボールのドリブル、野球のボールコントロール、鉄棒や縄跳びなどの技、ダンスのステップなどもそうです。大人になってからでも筋力や持久力は向上しますが、巧緻性は大人になってからだとなかなか身に付きません。しかし、今のうちにやっておくと大人になってからも巧緻性を発揮できると言われています。ですから縄跳びは今の時期の子どもたちにぴったりな運動なので、これからも縄跳びのいろいろな技に挑戦してほしいと思っています。 ○ 2月の「ふれあい月間」に合わせて、友達と一緒に教え合いながら縄跳びをするといいことも話しました。友達と一緒に練習することで、上達が早まることは多いです。遊びの中でも教え合いをして、お互いを高め合える子どもたちを育てていきましょう。 ○ 学校経営方針の柱の一つが「子どもたちが元気な学校」です。日頃から外遊びを奨励し、先生方自身も子どもたちと一緒に外遊びをしていただいていることに感謝しています。きっと児童理解にも役立っていることと思います。寒い日が続きますが、引き続き外遊びの励行をお願いします。また、運動後の手洗い等、子どもたちの体調管理には十分気を付けていきましょう。 以 上 2/18 避難訓練





訓練では、緊急地震速報が流れ、その後放送で机の下にもぐる指示を出した。1月の時は1年生の教室の様子を見ていると緊急地震速報が鳴った段階で、すでに行動を起こしていた。今回もどの学年もそのような行動をとれていたと各担任から聞いている。また、校庭で体育をしていた学級も校庭の真ん中に集まって静かに待機できていた。素晴らしかった。 その後、火災発生から校庭へ避難することは感染拡大の状況を考えて、今回も廊下までの避難とした。実際に校庭まで避難して避難経路の確認をすることはできなかったので、訓練後の事後指導で各学級で確認させた。 今回の避難訓練でも子どもたちはしっかり行動できていた。とても立派であった。今後の生活に、ぜひ生かしていってほしい。 2/17 ICT研修会
先週8日(火)は4時間授業で、午後からは、教員のICT研修会を行った。信州大学の佐藤和紀先生を講師にお迎えしてお話を伺う予定であったが、今回は、感染拡大の状況だったので、オンラインの研修会となった。
研修の内容は、実際に教員全員が自分の端末を使ってジャムボードやスプレットシートを使いながら佐藤先生のお話を伺った。ICT活用の重要性、スキルの大切さ、ICTを活用した授業のポイント、そして、学級経営への生かし方などを学ぶことができた。毎日少しずつ子どもたちに端末を使わせることが大事であることがよく分かった。 2月に入って先週までの間に私が参加したオンラインでの研修会や会議は、対面とのハイブリッド方式を含めて8回あった。ゲストティーチャーによるオンライン授業も数回行っている。コロナ禍以前には考えられないくらいICTを活用してきていて、GIGAスクール構想が進んでいることを実感している。我々もこうやって少しずつ使いながら端末の使用に慣れてきている。子どもたちにも毎日少しずつ使わせていきたい。 大変有意義な研修会であった。講師の佐藤先生に感謝したい。 2/16 模範授業





本来なら、模範授業は他校からも希望者が参観しに来るのだが、今回は感染拡大に伴い参観を中止した。その対応策としてオンラインでの授業公開とした。本校の教員が、教室後方から動画撮影し、子どもたちが調べ学習に入ると、その様子をカメラを持って教室内を回り撮影した。他校からの動画視聴による参観者は15名ほどだった。初めての試みだったので、活動の様子や教師の支援の仕方を十分に伝えることはできなかったかも知れない。私も実際に教室に行って参観したり動画撮影の様子を見たりし、その後、校長室へ戻って動画視聴もした。全体での話し合いなどはよく分かったが、個別の活動についての動画撮影については、改善点はあったと感じている。今後またこのような事態に授業を公開する際には、今回の反省を生かしていきたい。 いい授業を提供してくれた本校の指導教諭、そして、動画視聴をしてくださった先生方に感謝である。 2/15 トニー



1月22日は土曜授業だったので、いつもお世話していた栽培飼育委員会の子どもたちが放課後に集まって、担当の先生からトニーが亡くなったことを聞いた。それを聞いて涙した子も多かったようだ。そして、週明けの1月25日の委員会の時にトニーへのメッセージを書いた。また、全校児童へもどのように知らせるかを考えて、1月28日の保健委員会集会の前に、放送で全校児童に知らせるとともに、メッセージを書いてほしいというお知らせもした。すると子どもたちからたくさんのメッセージがトニーの元に届いた。トニーも天国で喜んでいることだろう。これからも子どもたちのことを天国から見守っていてほしい。 2/14 端末接続練習





そこで、先週9日(水)に、子どもたちに端末を持ち帰らせて、各家庭で接続練習を行った。9月に一度実施したのだが、忘れている可能性もあるので実施した。9日はクラスごとに時間を決めて実施した。各クラスである程度うまくいったようである。不具合などがあった場合は、各担任までお知らせいただきたい。 今回は、端末を持ち帰って接続練習したが、そのようなことがなく学校生活を送ることができることを願っている。そのためにも、今後も各ご家庭で一層子どもたちの体調管理には気を付けていただくようよろしくお願いしたい。 2/10 えがおまつり

さて、先週4日(金)に「えがおまつり」があった。コロナ禍の中での開催となるので、担当の特別活動部の教員は、年度当初の予定を変更し全校一斉に行わず、4日に、学年内での交流という形で計画してくれていた。しかし、感染拡大の状況の中で、さらに計画を変更し、学年で同じ時間に開催するが、クラス間の交流はせず、クラス内での開催とした。多くの学年が4日に開催したが、後日開催する学年も出てきた。欠席者が多いとか、お化け屋敷などお店の内容がクラス内だと楽しめないので他のお店にするなどが主な理由であった。それでも昨年度は、実施日を決めずに年度末までに各学級で実施したので、今年度は同一日に学年で開催することができる方法を考えてくれた特別活動部の教員には感謝である。 しかし、全校で交流すると他の学年のお店をたくさん見ることができて、その内容や運営方法などを次の学年になった時に生かせるので、そのような機会が2年連続でなくなってきることを危惧している教員もいる。同感である。上級生の活躍する姿を見て下級生が育っていくのだが、そのような機会がコロナ禍で少なくなってきている。来年度以降の子どもたちの活動が充実するように教員が支援していかなければならない。早く子どもたち同士で学び合える環境が戻って来ることを期待したい。 2/9 校内研究授業
先週2日(水)に今年度最後の校内研究授業を行った。今回はけやき学級の4〜6年生でティーボールの学習であった。子どもたちは攻める時、守る時の作戦をそれぞれ楽しみながらゲームをした。
今年度本校は、東京都小学校体育研究会の研究協力校の指定を受けて研究を進めてきた。今月末の25日には、その研究発表会をオンラインで実施する。今回の研究授業はその発表会へ向けてではなく、来年度の研究へ向けての第1回目の授業であった。本校は、今年度、小平市教育委員会研究推進校の指定も受けている。この指定は2年間で、来年度研究発表会を行う。今年度、小体研の各領域部会からアドバイスを受けて研究を深めてきたことを生かして来年度へ向けて研究を深めている。 研究協議会では、授業を参観した教員から子どもたちがよく頑張っていたことについての感想が多く出ていた。指導講評では、2年間、本校の研究のご指導をいただいてる講師の先生から貴重なご指導をいただいた。それを今後の研究に生かしていきたい。次回の研究授業は令和4年度に入ってからである。教員の体育指導への意識の変化を感じている。来年度の研究も楽しみである。 2/8 表彰





「English Vocal Election vol6〜全国英語歌唱コンクール〜」北関東エリアホール審査グループの部ジュニアS4部門第2位になった「Rainbows」のメンバーの5年生。 そして、本校は今年度「人権の花運動」に取り組んだので、その活動への感謝状が東京都人権擁護委員会連合会から届いたので、中心的に活動してくれた栽培飼育委員会の委員長に渡した。 今回は、友達と協力して活動したことに対しての表彰をすることができた。ちょうど全校朝会でも「協力」という話をした後だった。子どもたちにはこれからも友達と協力していろいろな活動を行っていってほしい。 2/7 全校朝会の話 協力
おはようございます。
先週、2月4日に学年別ではありますが全校一斉に「えがおまつり」を行う予定でした。しかし、感染が拡大している状況だったので、一斉に行わないことにしました。さらに、学年内で交流する予定でしたが、それもやめて学年同じ時間ではありましたが、学級ごとで行うことにしました。他の学年や他の学級の友達と交流することができなかったのは残念でした。しかし、4日に行ったクラスは「えがおまつり」を楽しんだことでしょう。コロナ禍で、できる行事が少なくなっていたので、「えがおまつり」はいい思い出になったはずです。これから行うクラスもぜひ「えがおまつり」を楽しんでください。 先生は、「えがおまつり」当日まで、各クラスでお店について話し合ったり、準備をしたりしている様子を見てきました。皆さんは、お客さんを楽しませるお店にするために、よく考えて話し合っていました。また、友達と「協力」して、お店の準備もしていました。「えがおまつり」の取組を通して、皆さんは友達と協力する大切さを改めて感じ、クラスの友達との絆を深めることができたと思います。この経験をこれからの生活に、ぜひ生かしてください。 2月は「ふれあい月間」です。いじめや暴力は決して行わず、「えがおまつり」のように、友達と協力して仲良く学習したり生活したりして、たくさんの思い出を作りましょう。 これで校長先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 「えがおまつり」の取組ありがとうございました。コロナ禍の中での開催へ向けて工夫して計画してくださり、また感染拡大に伴い、直前まで対応を検討していただいた特活部の先生方、ありがとうございました。また、各クラスでも、子どもたちが主体的に準備できるようご支援いただきありがとうございました。開催を延期した学年の先生方は、子どもたちの気持ちを考えながら、今後の対応もよろしくお願いします。 〇 各クラスで「えがおまつり」を子どもたちが協力して取り組んできたことは大きな財産です。この経験を生かして、これからも協力していろいろな活動をしたり生活したりする意識を高めましょう。今年度も残りひと月半です。最後まで、子どもたちやクラスのいろいろな力を伸ばしていってください。そして、今のクラスでの思い出もたくさん作りましょう。 ○ 2月は、今年度最後の「ふれあい月間」です。いつも以上に「いじめゼロ・暴力ゼロ」を目指しましょう。いじめの未然防止のためには、子どもたちの言動に注意を払い、些細なことでも見逃さないことが大事ですので、一層の児童理解に努めましょう。さらに、いじめが発生した場合は、早期発見・早期対応に努めましょう。そして組織的に対応していきましょう。また、「体罰ゼロ」も目指しましょう。教師の言動にも十分に注意をして「不適切な指導」もないようにしましょう。 以 上 2/4 新1年生保護者説明会

例年は受付と必要な事務処理を行った後、会場で説明会を行い、業者による物品販売場所で必要なものを購入していただいていた。それを昨年度から受付と必要な事務処理後に、説明を受けたい保護者のみの説明会とした。すでに兄弟姉妹の関係で説明を聞かなくても分かるという保護者の方々には、受付で資料を受け取って帰ったり、受付後物品購入して帰ったりしていただいた。また、本校に兄姉が通っている場合は、説明会当日に来校せず、兄姉へ資料を渡すようにもしていいる。また当日ではなく後日資料を取りに来てもよいことにもしている。これらの3密を避けるための手立てにご協力をいただいた保護者の皆様には感謝している。 説明会では、初めて小学校にお子様を入学させる保護者の方の不安を少しでも解消するための説明をさせていただいた。感染拡大防止のため時間も短くして実施したので、まだまだ不明な点があるかもしれない。入学するまでの間、ご不明な点はいつでもご相談していただいて構わない。いつでも連絡をお待ちしている。 2/3 えがおまつり準備

しかし、コロナ禍で緊急事態宣言中だった昨年度は、全体での交流どころか学年内での交流ができなかったので、各クラスでの実施となった。今年度は、学年内での交流は可能な状況だったので、感染防止に気を付けながら学年内で実施することにした。しかし、感染が拡大している状況を受け、今週に入ってから改めて学年同じ時間に実施はするが学年内の交流もせずクラス単位で楽しむこととした。さらに、明日の実施を基本とするが、学年ごとに日程を再調整することとした。 いろいろ変更はしたものの、子どもたちは「えがおまつり」へ向けて準備を進めている。例年だとお客さんとして楽しむ1年生も、今回はお店を開く。準備の様子を見ていると、本当に楽しみながら準備をしていたし、しっかり協力して準備していて成長も感じた。1年生だけでなく、他の学年の子どもたちも12月から学級会で開くお店を考え、展覧会終了後の先週から準備を始めてきた。子どもたちにとって思い出に残る行事の一つなので最後までしっかり準備して「えがおまつり」をクラスごとに十分に楽しんでほしい。 2/2 保健委員会集会





動画の内容は、新型コロナウイルスに関係する豆知識やマスクの正しい装着の仕方、手の正しい洗い方などを、クイズ形式で説明してくれた。また、いつも中休み終了後に放送で流している「手洗いの歌」を流して手洗いの仕方を確認してくれた。また、今週から保健委員会が実施するハンカチチェックと窓開けチェックについての説明もあった。 クイズや動きを取り入れながらの動画だったので1年生にとっても分かりやすく、集中して観ることができていた。感染が拡大している状況なので、感染予防・感染拡大防止へ向けて、もう一度、約束を確認することができた。 今回の集会のために動画作成してくれた保健委員会の子どもたちに感謝である。 2/1 2月

16都県に適用されている「まん延防止等重点措置」に、先週新たに18道府県が加わり2月20日までの適用となった。これで34都道府県である。さらに、最初に適用された3県も2月20日まで期限が延長された。東京都を含む13都県は2月13日までが適用期間である。あと2週間である。現在の感染拡大の状況を考えると、あと2週間で収束しそうにない気がする。 まん延防止等重点措置期間中に中止にした学校行事や教育活動もあるが、何とか縮小して行ったものもある。これからもできるだけ工夫して行っていきたいとは考えている。しかし、異学年が交流する縦割り班遊びは先週中止した。今日のクラブ活動も同じように中止した。さらに今日のクラブは3年生のクラブ見学も兼ねていたので、子どもたちにとっては残念だったことだろう。しかし、前回のクラブ活動はまん延防止等重点措置が適用される前だったので、万一のことを考えてその時にクラブの様子は動画撮影していた。3年生には、それを見てもらうことにした。 2月も感染状況に合わせていろいろ対応を考えながら教育活動を行っていきたい。ご協力をよろしくお願いしたい。 |
小平市立小平第十二小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |