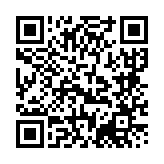|
最新更新日:2024/06/11 |
|
本日: 昨日:92 総数:283375 |
3/10 卒業式練習





今年度は、コロナ禍のため、縮小した卒業式となる。例年ならば、呼びかけや合唱の練習もするのだが、それもない。また5年生も入退場の曲の演奏練習や呼びかけ合唱練習もあるのだが、式に参列しないので練習もない。例年とは違う卒業式練習となる。 6年生は、昨年度の卒業式には参列していない。ただ入退場曲の演奏練習をしてきたので、その録音のために、一度だけ、6年生の入場練習に参加した。今も忘れないが、6年生の緊張感が当時5年生だった子どもたちにも伝わり、立派な態度で演奏していたのを思い出す。いい6年生になるだろうなと思ったことを覚えている。 昨年、式を見ていない分、一から入場や退場の仕方、礼の仕方、起立の仕方などを練習しなければいけない。式自体の厳格な雰囲気も出さねければいけない。6年生の担任にとって大変だとは思うが、頑張って指導していってほしい。練習を見に行くと、いい緊張感の中、とてもよく集中して練習している。小学校生活の集大成である卒業式を成功させたいという気持ちが伝わってくる。これからの練習も楽しみである。私もできる限り参加したいと思う。 3/9 避難訓練





訓練を実施たのは2時間目の後半だったが、後から聞くと、子どもたちは放送の指示に従いながら冷静に行動できたようだった。今回もコロナ禍のため校庭までの避難は行わず廊下までだった。各学年の報告終了後、私の方から話をした。今回は、今年度最後の避難訓練だったので、各クラスで訓練後に1年間の反省をするように伝えた。また、1週間後は、東日本大震災から10年目の節目となる。当時のことは今の5・6年生でさえ1・2歳だったので覚えてはいないだろう。だから各担任から当時のことや、自分の体験や学んだことなどを話すように伝えておいた。きっと各クラスで、いい学級指導をしてくれたことと思う。 週末に東日本大震災の特集番組がテレビで放映されていた。明後日が3.11である。各ご家庭でも、東日本大震災について話していただくとありがたい。よろしくお願いしたい。 3/8 全校朝会の話 感謝
おおはようございます。
先週から3月に入り、令和2年度も残りわずかになりました。この全校朝会も今日が最後で、6年生はあと14日で卒業し、十二小とお別れします。 そんな6年生の卒業をお祝いするために、2月26日金曜日に、6年生を送る会を行う予定でした。しかし、緊急事態宣言発令延長中なこともあり、全員で集まることは中止にしました。 6年生は、「十二小の顔」としてクラブや委員会、縦割り班活動で下級生を引っ張ってくれました。また、自分たちからすすんで挨拶をして、十二小に挨拶を広めてくれました。このコロナ禍の中で、「十二小の顔」としてできることをしてくれました。 そんな6年生に対しての感謝の気持ちを、皆さんはメッセージとプレゼントという形で贈ってくれました。先生は皆さんがメッセージを書いたりプレゼントを作ったりしている様子を見て嬉しく思いました。皆さんの感謝の気持ちは、6年生にも伝わったと思います。 6年生と過ごせるのも残りわずかです。特に5年生は、卒業式の予行練習で6年生の姿を目に焼き付けてください。そして、4月から自分たちが「十二小の顔」になるという意識を高めてください。他の学年の皆さんも最後まで6年生への感謝の気持ちを忘れないで生活してください。 これで校長先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 「6年生を送る会」は中止になりましたが、特活部で、6年生への感謝の気持ちを伝えるための取組を考えていただきありがとうございました。また、各クラスでは、6年生への感謝の気持ちを高めていただき、ありがとうございました。6年生へのメッセージやプレゼントには、子どもたちの気持ちが表れていたと思います。今回の活動を通して、「豊かな心」を育てていただきありがとうございました。 〇 6年生は、この1年間、コロナ禍の中でも、できることをしっかり考えて「十二小の顔」として頑張ってくれました。そんな6年生の卒業を全職員で支援していきましょう。また、通常だと5年生には6年生との合同練習を通して「4月からは自分たちが『十二小の顔』になる。」という意識を高められるのですが、今年度はそれができません。卒業式予行や学級での指導を通して、最高学年への意識が高まるよう支援していってください。 〇 3学期も残り3週間ありません。各学年で、この1年間の振り返りをする時期です。子どもたちの成長を振り返り、伸びたところはしっかり褒めていってください。そして、最後まで子どもたちの意欲を高め、力を伸ばし、次の学年に引き継いでください。 以 上 3/5 緊急事態宣言再延長
緊急事態宣言が3月7日で終了することを期待していたが、今日、再延長される予定になった。残念だが、まだまだ厳しい状態なので延長は当然なのだろう。予定ではさらに2週間になりそうなので21日までとなる。3学期は、ほとんど緊急事態宣言下での教育活動となった。
1月に緊急事態宣言が発令されてから、校外学習など、いろいろな行事を中止してきた。クラブ活動も同様に中止していた。来週9日に最後のクラブ活動がある。最終のクラブ活動については1年間のまとめをするので、市の感染症予防ガイドラインの中学校部活動の内容に従って、感染予防策を十分にとって実施することにした。4〜6年生は6時間目終了後に下校となるのでご了解いただきたい。例年3年生は4年生からクラブ活動が始まるので、2月にクラブ見学を実施していたが、今年度は中止にした。その代わり各クラブで活動の様子を紹介する動画を撮影した。それを3年生が視聴する形のクラブ見学とした。それ以外の3月のでは、修了式を放送で短縮して実施する。卒業式も昨年度以上に短縮して実施する。それ以外は大きな行事がないので変更点はない。 本校の欠席状況は、ここのところ大変少ない。例年だとインフルエンザの流行を心配している時期だが、今年度はマスク着用、手洗い・うがいの徹底が大きいのだろう。また各ご家庭のご協力のおかげでもある。とはいえ、緊急事態宣言が再延長されたので、さらに気を付けて子どもたちの体調管理をしていく。各ご家庭でも引き続きご協力をよろしくお願いしたい。 3/4 九九チャレンジ





チャレンジカードのすべて合格した子どもたちは、学年担任の3人の先生方にもチェックしてもらった。そして、最終段階は、私の前で「1×1=1」から「9×9=81」までを3分以内に言えるかどうかをチャレンジすることである。これは昨年度は実施していないが、前任校では毎年やっていた。だから今年度の2年生担任から依頼が来た時には、快諾した。 2年生の子どもたちは、毎日、中休みか昼休みに5〜8人くらいずつ校長室にやってきて、一人一人、私の前でチャレンジしてい。緊張している面持ちでチャレンジするが、見事合格するととても嬉しそうだし、ホッとしているようであった。昨日までに多くの子が合格した。残りわずかである。全員が合格できるようチャレンジさせながら励ましたいと思っているので、各ご家庭でも励ましの声をかけていただきたい。 3/3 すごろく集会





集会委員会の子どもたちは、全クラス分のすごろくのマスを作成してくれた。「1回休み」や「1つ進む」だけでなく「13マス戻る」や「ジャンケンで勝ったら5マス進む」、さらに、「担任の先生のいいところを発表する」「だれか一人が物まねをする」「先生にありがとうを言う」などもり、全部で20マスあった。それを時間内に何周回ることができるかを、クラスごとにチャレンジする集会だった. 私は1年生の各クラスの様子を見に行ったが、とても盛り上がっていた。それぞれのクラスには集会委員会の子どもたちも来ていて、会を盛り上げてくれていた。とても楽しい集会だった。急遽、集会を引き受けて計画・実施してくれた集会委員会の子どもたちに感謝したい。 3/2 体育実技研修会





今回は教師道場で2年間研究した本校教員が講師になって実施した。内容は、先生方からリクエストが多かった「準備運動」と「楽しい運動ネタ」についてだった。 準備運動では、動的ストレッチを紹介した。楽しい運動ネタでは体つくりの「あっち向いてホイッ」「開いて閉じて」「上下横」「腕立てホッケー」を紹介してくれた。 参加は任意であったが、出張や面談などがあった教員以外ほとんどの教員が参加して楽しく運動していた。とても有意義な研修になったので、今後の指導に生かしてくれることだろう。この実技研修会は、教員の教材研究とともに、体を動かすことで教員自身のリフレッシュとなる。今後も行っていく予定である。 3/1 3月

校長室前の紅梅も先週から満開となっている。ついこの間までは真っ暗な中、通勤してきたが、日に日に日の出が早まり明るくなるのも早くなってきていて春の訪れを感じている。とはいえ、先週は前半は暖かかったものの後半は気温が下がった。3月もこのように寒暖を繰り返して春になっていくのだろう。気温の変化が大きいと体調も崩しがちになる。さらに校内を回っていると「校長先生、今日は花粉がひどいです・・・。」と話しかけてくる子が何人もいる。花粉症の子どもたちはもちろん、花粉症の方には早く終わってほしい季節だろう。 残りの日々を充実させるためにも、新型コロナウイルス感染拡大防止も含めて、子どもたちの体調管理には、引き続き気を付けていきたい。各ご家庭でもご協力をよろしくお願いしたい。 2/26 6年生を送る会





しかし、その代わりに6年生にプレゼントを作成して送ることになった。縦割り班ごとに、全員が6年生にメッセージカード書いて、それを5年生が取りまとめてリーフレットを作成した。さらに、1年生は王冠を、2年生はペンダントを作った。それらを、今日の朝、中休み、4時間目にそれぞれの学年が6年生に渡しに行く予定である。私も先週・今週と子どもたちがプレゼントを作成している様子を見ていた。心を込めて作成している姿がよく分かった。子どもたちの気持ちは、きっと6年生に届くはずである。 6年生が卒業するのは寂しいが、今回の6年生を送る取組を通して、子どもたちの豊かな心が育ったことは嬉しく思う。6年生には、卒業までの残りひと月を、充実させ、楽しい思い出を一つでも多く作って卒業していってほしい。 2/25 体育委員会集会





年度当初は長縄集会を予定だったが、現状では全校で校庭に集まって行う集会はできないので、体育委員会の子どもたちが「自宅でできるストレッチ」として8つのストレッチを動画に撮って見せてくれた。観ていた子どもたちも、実際にストレッチをしながら視聴していた。 今回の動画視聴後、各クラスに体育委員会で作成したストレッチカードが配布された。そして、集会の翌日2月20日(土)から3月7日(日)までの2週間程度、子どもたちは自宅でストレッチに取り組むことになっている。コロナ禍の状況で、この1年間、子どもたちの運動不足も心配の一つになっている。この2週間、子どもたちが気持ちよくストレッチに取り組み、少しでも体を動かす機会を増やすことができるよう、各ご家庭でも声掛けをお願いしたい。 2/24 桜

一昨日、出勤して校庭の様子を見るといつも見慣れていた桜の木が1本なくなっていた。このブログでも何度も写真に載せていた桜の木2本うちの東側を今回は伐採した。写真で一見すると大きな一本の桜の木に見えていたのだが、2本とも外側に枝を伸ばしていたので1本に見えていたのだ。1本が伐採されて半分なくなった感じに見えて寂しさを感じる。 本校は開校して50年以上たつ、ソメイヨシノの寿命は60年ほどと言われる。桜の木もだいぶ古木となってきていて特に今回伐採した桜は、朽ち始めてきていて伐採する予定にはなっていた。さらに、昨秋には大きな枝が落下したので、しばらくは桜の木の下を立入禁止にしていた。そして、先週末に伐採した。 桜の木は、満開の花を咲かせる春にはクラスの記念写真の背景になっていた。暑い夏はいい日陰になっていた。子どもたちにとって親しみのある木だった。学校東側の道路拡張のため、数年前に大きなケヤキの木を伐採し、今回は、桜を伐採した。木が減ってきて寂しいが、それに代わる桜の木も昨年から植えている。数十年先にはなるだろうが、その木が本校のシンボルになることを願っている。 2/22 全校朝会の話 目標
おはようございます。
早いもので、今週が2月の最終週、来週からは3月に入り、ひと月後には修了式・卒業式を迎えます。皆さんは、3学期の初めに目標を立てましたが、その目標はどの程度達成できていますか。今の学年が終わるまで残りひと月になる今週は、ぜひ、自分の目標がどれくらいできているかを振り返ってみてください。そして、残りひと月は、その目標を意識して生活し、自分が立てた目標をできるだけ達成してほしいと思います。 また、クラス目標についても振り返ってみてください。2月に全校で行う予定だった「えがおまつり」がなくなりました。しかし、「えがおまつり」に代わることを各クラスで行うことになっていて、すでに終わっているクラスもあります。そんなクラス行事の取組を通して、クラス目標に近づけたかどうかも振り返ってみるとよいでしょう。 2月は「ふれあい月間」でした。皆さんの中には、3学期の目標を「友達と仲良くする。」とした子も多かったようです。3月で、今の学級の友達とはお別れになるので、それまで仲良くしたいという気持ちから、目標にしたのでしょう。「ふれあい月間」が終わっても「いじめや暴力を絶対にしない、許さない。」という気持ちを忘れずに最後まで友達と仲良く生活し、楽しい思い出をたくさんつくりましょう。 これで先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 3学期の初めに子どもたちは「3学期のめあて」を立てました。めあては立てさせただけでなく、時々振り返らせて、その達成具合をチェックしたり、修正を加えたりすることが大事です。また、途中で振り返ることは、めあてをさらに意識して生活することにもつながります。ぜひ「3学期のめあて」を書かせっぱなしにせず、めあてを意識して生活させて、子どもたちを伸ばしてあげてください。 ○ 個人のめあてだけでなく、学年末にもなるので、「クラス目標」についても振り返りをさせてみてください。そして、こちらも達成具合をチェックして、残りひと月を「クラス目標」を意識して生活させて、緊急事態宣言発令延長中の状況ですが、楽しい思い出を作らせてあげてください。 〇 「えがおまつり」が中止になりました。その代わりになるクラス行事にすでに取り組んでいただいたクラスもあります。楽しそうに活動している子どもたちの姿が印象的でした。また、今、話し合いを行っているクラスもあります。クラス行事の取組にもクラス目標を意識させて、いい思い出の会にしてあげてください。 〇 今週末に予定していた「6年生を送る会」も6年生にメッセージなどを送る形に変更しました。この取組を通して、6年生への感謝に気持ちを高めてあげてください。 ○ 毎時間の授業でも、教師主導の授業ではなく、子どもたちに「めあて」をもたせて取り組ませ、それを振り返るという学習をさせることも大事です。校内研究で研究している体育科での課題解決的な学習を、他の各教科・領域にも生かしていきましょう。それが、「主体的・対話的で深い学び」にもつながります。 以 上 2/19 梅

さて、本校の梅は紅梅と白梅がある。ただ、私にとって、この時期の「梅」といえば、「青梅」である。毎年2月第3日曜日には、「青梅マラソンン」に参加し30キロを走っている。しかも今年は第55回の記念大会だった。しかし、コロナ禍の影響で55回大会は来年へ延期となった。保護者の方でも青梅マラソンを走っている方がいらっしゃる。昨秋お会いした時に二人で残念がった。そして来年青梅で会うことを誓い合った。青梅を走ることができないのは残念だが、こちらの楽しみは来年にとっておくことにする。 2/18 体育館床改修工事



今までは、床の板が破損している箇所の板の張り替えや研磨での対応をしていた。しかし、破損個所が年々多くなってきたので、今回は床全面を研磨してきれいにしてもらった。さらに体育館に引かれているラインもすべてきれいに引き直してもらった。またワックスがけもしっかりやってもらった。半年前に実施した体力テストで反復横跳びでは踏ん張りがききにくく、横滑りをしてしまった子も結構いた。しかし、それも修正された。 今週15日の朝には、きれいになった床を見に行ったが、他にも数名の教員もいて、きれいになった床を見て感動していた。早速体育も始まり、きれいになった体育館で、子どもたちは気持ちよく体を動かしていた。 これからも、子どもたちにはきれいになった体育館で思い切り体を動かして運動好きな子に育っていってほしい。 2/17 学校経営協議会(試行)
先週10日(水)に、今年度最後の第6回学校経営協議会(試行)を開催した。今回は、学校経営協議会の役割の一つである令和3年度の教育課程の承認が主な議題であった。
教育課程には、学校経営・教育活動の基本方針、重点的に指導すること、授業日数と授業時数、年間行事予定が書かれている。これを毎年3月初旬までに作成して市教委へ届出し受理されることで次年度の学校経営・教育活動が動き出すことができる重要な文書である。コミュニティ・スクールになると、市教委へ届出する前に学校経営協議会に承認を得ることになる。本校は今年度、まだ研究段階だが、試行的に教育課程の承認も行った。委員の方々には、事前に送付してご覧いただいていた。当日は、質疑応答の後、無事、承認を得ることができた。 今年度の学校経営協議会は、今回で最後となった。各プロジェクトチームでいろいろ動いていただいたことに感謝している。またご協力いただいた地域・保護者の皆様にも感謝している。 ただ、コロナ禍のため、コミュニティ・スクールとしてやりたかった事で、できなかったことも多々あった。来年度4月以降に、状況を見ながらできることからやっていきたいと思う。地域・保護者の皆様にもご協力をいただきたいことがある。その時にはご協力をよろしくお願いしたい。 2/16 避難訓練





しかし、緊急事態宣言延長のため、今回も廊下までの避難となった。廊下避難後、学年主任が本部まで人員報告をした。子どもたちは非常に行動が早く、報告も早く終了した。その後私から話をしたが、まずは、行動の早さを褒めた。そして、今回は、避難経路を各クラスで確認することと乾燥している冬の時期の火の危険性について話をした。 校庭で体育の授業をしていた2クラスの訓練後の担任による指導の様子を見ていたが、担任からも再度、火の危険性について話してくれていた。子どもたちもよく話を聞いていた。きっとどのクラスでもしっかり指導してくれたことと思う。 各ご家庭でも特に寒く乾燥する日が続く冬の時期の火の危険性について子どもたちに話していただけるとありがたい。よろしくお願いしたい。 2/15 教育委員会訪問

本校では、私が学校や地域の特色や取り組んでいることについて説明し、その後、校内を回っていただいた。建築したばかりの西校舎を見ていただいた後、各学年1クラスずつの授業を観ていただいた。 その後、本日参観した感想やご意見、ご指導をいただいた。またお褒めの言葉もいただき大変嬉しかった。短い時間ではあったが大変貴重な時間となった。ご指導いただいたことを今後の教育活動に生かしていきたい。そして、今後さらによい学校経営・教育活動を行っていきたい。ご指導いただいた教育委員の皆様、教育委員会事務局の皆様に感謝である。 2/12 研究発表会





本校は、連携校だったので、全員が参加する予定だったが、オンラインのため参観者の定員が80名と絞られていた。本校だけで30名近くになってしまうので、5つの授業に合わせて5名だけが事前申し込みをした。そして、分科会ごとに各教室に分かれて大型テレビにつないで全員が参加することができた。今回は、法教育についての研究内容がよくわたっかだけでなく、オンライン発表会の良さを感じることもできた。とてもいい研究発表会であった。 後日、急遽、オンライン開催にした五中の校長先生から、準備段階から当日までの苦労話や良かったことについて話を聞くことができた。オンライン発表は、今後の研究発表会の一つとして広まる気がする。本校が研究発表会を行う機会があったら、オンラインも視野に考えていきたい。多くのことを学ばせていただいた小平第五中学校の校長先生をはじめ先生方に感謝したい。 2/10 校歌
1月に音楽専科の教員と卒業式や入学式の話をした。このコロナ禍で卒業式の入退場や合唱ができないので、どのように対応していくかという話だった。その中で、校歌も歌うことができないことを話していたとき、ふと、そういえばこの1年間、校歌を聞く機会がほとんどなかったことに気が付いた。
昨年度までは月曜朝会の中で月に1回歌っていた。今年度もその予定でいたのだが、コロナ禍で全校朝会自体ができなくなったので朝会で歌うことがなくなった。入学したての1年生が、臨時休校明けにCDを聞いて校歌を覚えていたのを聞いたくらいであった。本校の校歌は、歌詞が長いので、私も着任したばかりの昨年、ようやく覚えたからと思たっところで臨時休校となってしまった。今でもメロディーは覚えてはいるが、歌詞を忘れてしまっている部分はある。子どもたちも同様だと思う。 そこで、音楽専科と相談して1月末から朝の時間に「校歌」を流している。朝、正門前で子どもたちを挨拶を交わしながら校舎内から流れてくる校歌を聞くことができる。いいものである。子どもたちも自然に耳に入ってくるので忘れかけていた子たちも思い出すことだろう。子どもたちには「校歌」を大切にし十二小を大切にする子に育ってほしい。 2/9 教師道場授業



そのうちの体育科の道場部員が、もうすぐ2年間の研修を修了することになる。そこで、その研修の成果を公開授業の形で1月29日(金)に行う予定だった。市内や市外の教員から公開授業に参会したいという連絡が入っていた。しかし、緊急事態宣言中なので、授業を公開することは中止とした。指導いただく予定だった講師の先生は市外の大変力がある指導教諭だったので、話を聞くことができるのを楽しみにしていただけに残念だった。 一番残念だったのは道場部員本人だった。そこで、事前に授業は行い、29日は校内だけの研究協議会とした。2年間の道場での研修報告と今回の授業について指導計画の意図や成果と課題について説明した。そして指導案上ではあるが教員からの質疑応答も行った。本校は、今年度から3年間、校内研究で体育科の研究をしているので、教員も熱心に質問や意見を出してくれた。 道場部員にとっては残念だったが、それでも自分が培った力を本校に還元してくたのは嬉しい。今後も本校の体育の研究を牽引していってほしい。 |
小平市立小平第十二小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |