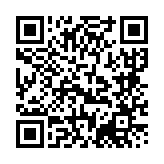|
最新更新日:2024/06/11 |
|
本日: 昨日:92 総数:283353 |
2/9 教師道場授業



そのうちの体育科の道場部員が、もうすぐ2年間の研修を修了することになる。そこで、その研修の成果を公開授業の形で1月29日(金)に行う予定だった。市内や市外の教員から公開授業に参会したいという連絡が入っていた。しかし、緊急事態宣言中なので、授業を公開することは中止とした。指導いただく予定だった講師の先生は市外の大変力がある指導教諭だったので、話を聞くことができるのを楽しみにしていただけに残念だった。 一番残念だったのは道場部員本人だった。そこで、事前に授業は行い、29日は校内だけの研究協議会とした。2年間の道場での研修報告と今回の授業について指導計画の意図や成果と課題について説明した。そして指導案上ではあるが教員からの質疑応答も行った。本校は、今年度から3年間、校内研究で体育科の研究をしているので、教員も熱心に質問や意見を出してくれた。 道場部員にとっては残念だったが、それでも自分が培った力を本校に還元してくたのは嬉しい。今後も本校の体育の研究を牽引していってほしい。 2/8 全校朝会の話 挑戦
おはようございます。
早いもので、1月が終わり先週から2月に入りました。1月に取り組んできた短縄旬間が先週で終わりました。3週間に渡って、皆さんは体育の時間や休み時間にどんどん縄跳びの技に挑戦し、いろいろな技ができるようになりました。また、今年から縄跳びカードで取り組む技が変わり、新しい技も出てきました。そんな新しい技にもどんどん取り組んでいました。そんなやる気いっぱいの皆さんを見ていて、とても嬉しかったです。 できない技に挑戦すると、当然、はじめはできません。しかし、諦めずに挑戦し続けることで、できるようになります。それは、練習を繰り返しているうちにコツをつかむことできるからです。ですから諦めないことが大事です。また、友達と一緒に練習するといいことに気付いた子もいると思います。お互いに教え合うことができるし、できる子の跳び方を見て真似することでコツをつかめることもあるからです。 2月は「ふれあい月間」でもあります。短縄旬間は終わりましたが、これからも友達と仲良く縄跳びなどで遊びながら、友達と一緒に楽しんだりいろいろな運動ができるようになったりするといいですね。寒い日が続きますが、寒さに負けず、すすんで体を動かして、運動が好きな、元気な子に育ってください。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 短縄旬間の取組ありがとうございました。先生方も一緒に縄跳びをしたり声掛けしたりしていただいたおかげで、子どもたちも縄跳びに意欲的に取り組んだのだと思います。短縄旬間は終わりましたが、今回の取組をきっかけにして、今後も子どもたちに縄跳びに取り組ませてください。 小学校の時期の子どもたちは、体力面では、筋力や持久力よりも巧緻性が大きく伸びます。巧緻性とは、サッカーのリフティングやドリブル、バスケットボールのドリブル、野球のボールコントロール、鉄棒や縄跳びなどの技、ダンスのステップなどもそうです。大人になってからでも筋力や持久力は向上しますが、巧緻性は大人になってからだとなかなか身に付きません。しかし、今のうちにやっておくと大人になってからも巧緻性を発揮できると言われています。ですから子どもたちには、縄跳びのいろいろな技に挑戦してほしいと思っています。 ○ 2月「ふれあい月間」に合わせて、友達と一緒に教え合いながら縄跳びをするといいことも話しました。友達と一緒に練習することで、上達が早まることは多いです。遊びの中でも教え合いができるように、普段の学習中でも教え合いの場面を、感染症予防対策を講じながら設定してみましょう。そして、お互いを高め合える子どもたちを育てていきましょう。 ○ 学校経営方針の柱の一つが「子どもたちが元気な学校」です。日頃から外遊びを奨励し、先生方自身も子どもたちと一緒に外遊びをしていただいていることに感謝しています。きっと児童理解にも役立っていることと思います。寒い日が続きますが、引き続き外遊びの励行をお願いします。また、コロナウイルスとともに、インフルエンザの流行も心配です。手洗いうがい等、子どもたちの体調管理には十分気を付けていきましょう。 以 上 2/5 算数教室





そして、その翌日29日からは西校舎で、算数を行っている。子どもたちは新しい教室での学習に、気持ちを新たにして取り組んでいる。いいことである。渡り廊下を通っていくので多少の不便は感じるが、子どもたちには新しい教室で勉学に励んでほしい。 西校舎には、来年度から特別支援教室とパソコンルームも開設する予定である。今年度は学校を公開できなかったが、来年度になって学校公開が再開されることになったらぜひ西校舎もご覧いただきたい。 2/4 保健委員会集会





今回のテーマは「手洗い」だった。手洗い実験で、手洗い前・水洗い後・接点での手洗い後の汚れの落ち方の違いを示してくれた。さらに、手洗いの歌に合わせて実際に手洗いの仕方をやってみながを再確認しくれた。さらにハンカチ調査の結果報告と班活を持ってくるように啓発もしてくれた。そして最後にクイズで手洗いのポイントを再度確認してくれた。観ていた子どもたちもよく視聴していたし、手洗いの歌に合わせてしっかり手洗いの練習をしたりクイズを楽しんだりしていた。楽しみながらしっかり学ぶことができた。 緊急事態宣言発令中で、手洗いの励行を重点化している。寒い時期だが子どもたちには予防策として石鹸での手洗いを励行している。そんな中での手洗いについての集会だったので、大変ありがたかった。作成してくれた保健委員会の子どもたちに感謝である。 2/3 作品展





そして、先週1月28日(木)に図工専科の教員が展示してくれて、翌日の1月29日(金)から今週末の2月5日(金)までの1週間で子どもたちに公開している。 本来ならば地域や保護者の皆様にもご覧いただきたいところだが、今は難しい状況である。そこでホームページ上にもアップルことにして、すでに「図工室」のページにアップしてあるので、そちらをぜひご覧いただきたい。来年度は、コロナ禍が収束し、市内小学校児童作品展が開催されることを心から願っている。 昨夕、緊急事態宣言が1か月延長された。それに伴って3月1週目までの行事等で変更・中止したものがある。児童の下校時刻が変わるものもあるので、そちらについては一斉メールでもこれから発信するが、中止・変更分については「学校からのお知らせ」のページにアップするので、そちらもご覧いただきたい。 2/2 節分





節分が2月3日でないのは、昭和59年(1984年)2月4日以来37年ぶり、2月2日になるのは、実に明治30年(1897年)2月2日以来124年ぶりのことだそうだ。国立天文台のコメントを読むと、その原因は、地球が太陽の周りを回る公転の周期が、1年きっかりではないことが原因で、微妙なずれが積み重なった結果だそうだ。公転周期が365日ぴったりではないことは、もちろん知っていた。だから「閏年(うるうどし)」が4年に1度あり調整していると理解していた。ただ、それだけでは微妙なずれは修正できないようだ。それで立春が例年の日付から前後することがあり、それに伴い節分の日も2月3日からずれるケースが出てくるというのだ。なるほどと感心したが、さらに驚いた。124年ぶりに2月2日になったのだから、次に節分が2月2日になるのは124年後だと考えがちだが、そうではないようだ。計算方法の詳細は国立天文台のホームページを参考にしていただきたい。前回の節分が2月2日になった時にも1902年から84年にかけて、2月2日となる年がたびたびあったそうだ。そして、今回も今年からしばらくは4年ごとに2月2日となり、2057年の次は58年で2年続くという。 私が教員になって30数年間、当たり前のように2月3日に向けて鬼のお面を作ったり、自分の中のこんな鬼を追い出そうという目標カードに取り組んだりしてきたが、今年は2月2日。1年生の教室前の廊下には、先週から図工で作った鬼のお面が掲示されていて、その隣に「今年の節分は2月2日」という表示が書かれている。今の小学生の子どもたちにとっては、大人になったとしても節分はオリンピックやパラリンピックなどのように4年に一度来ることが常識になるのだろう。私が今までの常識だと思っていたことがそうでなくなる。頭を切り替えないといけない。 2/1 2月

子どもたちは1月も集中して学習に取り組んでいた。2月も同様に頑張ってほしい。予定では、今日は5年生が社会科見学に行くことになっていた。しかし、緊急事態宣言の再発令で中止とした。2月中旬に実施予定だった6年生の社会科見学も中止した。子どもたちが楽しみにしていた行事がなくなってしまったのは残念ではあるが、日々の生活を楽しく過ごしてほしい。そのために教員一同頑張っていくので、2月もご協力をよろしくお願いしたい。 1/29 寒さ対策

学校では、コロナウイルス感染拡大防止策として教室の換気に努めている。冬なので暖房もしながら窓とドアを少し開け常に通気をよくしている。しかし暖房効率が悪く、授業中に寒さを感じている子もいる。そこで各担任が寒さ対策をいろいろ考えてくれている。例年のこの時期だと、登校の時に着てきた上着は教室内では脱ぐことになっているが、授業中に寒さを感じたら来てよいことにしたクラスがあった。また、廊下側のドアを閉めて窓を開けた方が咲くさ対策になることを発見したクラスもあった。そこで、それらの各担任の工夫を全職員で共通理解して、上記の二つを全クラス採用して同じ寒さ対策をとることとした。 特に教室内での上着の着用については、子どもたちに身に付けさせたい力にも関係している。自分の体感で寒く感じたら上着を着る暑くなったら脱ぐという、自ら「衣服を着脱」する力である。意外とできないのが、暑くても脱がない方である。コロナ禍をいい機会として衣服の着脱について学校で指導していく。各ご家庭でも意識していただけるとありがたい。 1/28 十二小タイム





学習内容は、基本的に「東京ベーシック・ドリル」を使って前の学年の既習事項を復習することを中心としている。子どもたちは、どんどんクリントの問題を解き、終わったら先生にマルを付けてもらい、全部正解したら次のプリントに取り組むことになっている。マル付けに並ぶことになるので、担任一人で対応するのではなく、十二小タイムがない1年生担任、けやき学級担任、専科教員なども各学年各クラスの支援に入っている。 一昨日も各教室を回ったが、子どもたちはとても集中して取り組んでいた。その学ぶ姿勢を嬉しく思った。これからも子どもたちの学力定着の一つとして十二小タイムを続けていく。 1/27 新1年生保護者説明会
一昨日の午後に新1年生保護者説明会を実施した。緊急事態宣言発令中の中、解除後に延期することも考えたが、いつになったら収束するか分からないので予定通りの日程で実施することにした。ただし方法は例年とは変更した。
例年は受付と必要な事務処理を行った後、会場で説明会を行い、業者による物品販売場所で必要なものを購入していただいていた。今回は、受付と必要な事務処理後に、説明を受けたい保護者のみの説明会とした。すでに兄弟姉妹の関係で説明を聞かなくても分かるという保護者の方々には、受付で資料を受け取って帰ったり、受付後物品購入して帰ったりしていただいた。また、本校に兄姉が通っている場合は、説明会当日に来校せず、兄姉へ資料を渡すようにもした。また当日ではなく後日資料を取りに来てもよいことにもした。これらの3密を避けるための手立てにご協力をいただいた保護者の皆様には感謝している。 説明会では、初めて小学校にお子様を入学させる保護者の方の不安を少しでも解消するための説明をさせていただいた。感染拡大防止のため例年よりも時間も短くして実施したので、まだまだ不明な点があるかもしれない。入学するまでの間、ご不明な点はいつでもご相談していただいて構わない。いつでも連絡をお待ちしている。 1/26 赤十字委員会集会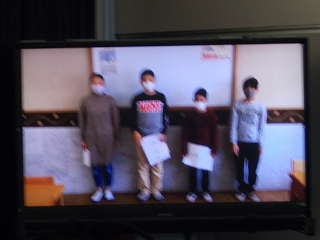

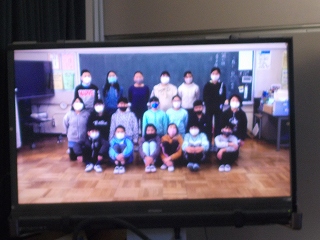



今回の内容は、「1円玉貯金」と「愛のはがき運動」についてであった。それぞれの取組の趣旨や方法をクイズなども入れて分かりやすく説明してくれた。動画を観ていた子どもたちもしっかり話を聞きながらよく観ていた。 1円玉募金は、早速、昨日と今日の朝に実施した。昇降口前で青少年赤十字委員会の子どもたちが募金を呼びかけ、募金してくれた子も多かった。愛のはがき運動は2月いっぱい取り組むことになっている。書き損じた年賀状などが各御家庭にあったら子どもたちに持たせてほしい。このような取り組みを通して、世界へ目を向けたり社会問題に関心をもったりする子どもたちを育てていきたい。また、心の優しい子に育てていきたい。各ご家庭でもご協力をよろしくお願いしたい。 1/25 1月最終週

昨日は雪の予報があり、今日の子どもたちの登校時の積雪の心配をしていたが、雨は雪には変わらず、昨日は一安心した。また久しぶりに雨が降ってくれたので乾燥していて土埃が舞っていた校庭も今日は水たまりができ、しっとりしている。 子どもたちも、この土日は雨も降り、不要不急の外出もしなかったことだろう。しっかり休養もできたことと思う。今週も縄跳び旬間中である。休み時間には縄跳びの技にチャレンジするなど、元気に過ごしてほしい。各ご家庭では、今週も引き続き子どもたちの体調管理についてご協力をよろしくお願いしたい。 今日は新1年生保護者説明会がある。感染症対策をしっかり講じて実施する。関係の保護者の皆様には、「学校からのお知らせ」に先週アップした確認事項を再度ご覧いただき、決して無理せずに、ご協力をよろしくお願いしたい。 1/22 校内研究授業



今回は2年生の鬼遊び「宝とり鬼」の授業だった。子どもたちは、とてもよく頑張っていて、また楽しそうに取り組んでいた。とてもよい授業だった。後から授業者の教員に聞くと、子どもたちは緊張していたようであった。緊張しながらも頑張っていた子どもたちに教員は感謝したいと話していた。その授業者も教員3年目の若手で緊張した中で指導していたとのことだったが、よく頑張っていた。体育を専門的に研究しているわけではなかったが、今回の研究授業へ向けて準備する中で、力を付けてきた。私も何度か事前の授業を見てきたので、その成長ぶりを嬉しく思った。講師の先生からもお褒めの言葉をいただいた。 今年度は、年度当初、低・中・高学年分科会で1本ずつ研究授業を行う予定であったが、コロナ禍で分科会の授業は、今回が今年度最初で最後となった。しかし、今回の研究授業を来年度につなげていき、来年度は、さらに研究を深めていきたい。そして、体育の学習に主体的に取り組む子どもたちを育てていきたい。 1/21 避難訓練





報告終了後、私の方から放送で子どもたちに話をした。今回は地震・火災の設定だったが、前日の1月17日が阪神大震災から26年目だったということもあり、その話をした。阪神大震災の時も火災は発生したが、それよりも早朝に発生したこともあって、棚などの倒壊によって被害に遭われた方が多かったことを話した。現在、各教室にある棚は金具によって固定されている。それは阪神大震災の教訓を生かしてのことであることも話した。 地震はそれ自体も恐ろしいが、その後の火災、津波など2次的災害が発生することもある。子どもたちには「自分の命は自分で守る」ことをいつも頭において生活してほしい。各御家庭でも災害が発生した場合の約束などを決めておくなど、災害について子どもたちと話をしていただけるとありがたい。 1/20 学校公開

さて、先週16日(土)は年度当初の予定では学校公開日であった。3学期の学校公開は昨日載せた「書き初め展」に合わせて行う予定であった。しかしコロナ禍のため残念ながら公開できなくなってしまった。 学校公開も今年度中にはコロナが収まれば公開できるだろうと思っていたが、一向に収まらず、とうとう一度も教育活動公開することなく今年度終了することになった。普段の授業の様子だけでなく、運動会や学芸会などの行事も公開できず、本当に残念な1年となった。そんな中、スポーツフェスティバルの動画配信や日々の学習の様子をホームページで毎日公開するなど、コロナ禍の中、できるだけの情報を発信してきた。各担任も少しでもクラスの様子を使えようと学級通信を発行してくれているクラスもあった。 保護者の皆様にとって今年度は十分満足できた情報発信とはいかなかったかも知れない。このような状態が少しでも早く鎮静化して、来年度は、予定通りの学校公開ができることを願っている。 1/19 書き初め展





今年度は、コロナ禍のため、保護者や地域の皆様には、子どもたちの作品を公開することができなかったのは本当に残念である。そんな中、学級通信で子どもたちの作品を写真で保護者の皆様に伝えてくれたクラスもあった。ありがたかった。来年は多くの皆様に子どもたちの書き初め作品をご覧いただけるようになることを願っている。 1/18 全校朝会の話 給食
おはようございます。
来週1月24日から1月30日までの1週間は学校給食週間です。ですから今日は「給食」についての話をします。 今年度は、臨時休校があり、給食が始まったのは6月15日からでした。給食が始まる前に、栄養士の佐々木さんを中心にして、給食の時の新しい約束を決めました。今、皆さんはその約束を守って給食の時間を過ごしています。いつもの年は、友達と会話を楽しみながら食べていましたが、今はそれもできません。少し寂しいかもしれませんが、緊急事態宣言も発令されている状況ですから、これからも給食の約束を守って給食の時間を過ごしてください。 そんな中での給食ですが、栄養士の佐々木さんや給食室の方々は、例えば、野菜を地元の小平で採れた新鮮な野菜をよく使ったり、食材の煮込み方や揚げ方を工夫したりしているなど皆さんに給食を美味しく食べてもらおうと努力してくださっています。また、栄養のバランスを考えて出してくださっています。食べ物の好き嫌いがある子もいるとは思いますが、苦手な食べ物も少しでもいいので食べるようにしましょう。 また、これからは、皆さんに美味しい給食を食べてもらおうと努力してくださっている給食室の方々や給食に関わっている多くの方々、そして、給食の食材そのものへの感謝の気持ちを忘れずに給食を食べるようにしましょう。 これで校長先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 来週は学校給食週間です。毎年1月24日から30日が学校給食週間です。各学級でも、食材を育ててくださっている方々、運んでくださっている方々、そして、調理をしてくださっている給食室の方々、そして食材そのものへの感謝の気持ちを育ててください。合わせて、給食についての話も、今週はいろいろ話してあげてください。先生方が子どもだった頃の給食メニューなどを情報交換して子どもたちに伝えるのも面白いかもしれませんね。 〇 緊急事態宣言が再発令中です。給食時の約束をもう一度確認して感染防止に努めましょう。特に寒い時期なので、手洗いがおろそかになっているかもしれません。休み時間や体育の時間の前後などもそうですが、給食前もしっかり石鹸を使っての手洗いをさせましょう。また、会食時に感染する事例が多いことが分かっています。給食中の会話の自粛、終了後にすぐマスク着用などの約束も徹底しましょう。 ○ 1月から2月は一年で一番寒い時期ですが、なわとびチャレンジも始まりました。外遊びを励行し体をたくさん動かす、そして、給食をしっかり食べる元気な子どもたちを育てていきましょう。しかし、コロナ禍の中、暖房を使いながら教室内の換気もしなければいけません。授業中の上着の着脱についてはご配慮をお願いします。また、先生方も、子どもたちに負けないように健康の保持・増進に努めてください。 以 上 1/16 土曜授業

今週は月曜日が成人の日だったので、6日連続とはならず、5日目の登校日なので比較的子どもたちの疲れもないのかとは思われる。しかし、冬休み明けということもある。また、月曜日が振替休業日にはしておらず1日だけ休んで、また5日連続の登校となる。来週に疲れを残さないためにも、今日の午後と明日は子どもたちを十分に休養させていただくなど体調管理には十分気を付けていただきたい。さらに緊急事態宣言発令中でもある。不要不急の外出は極力自粛していただきたい。ご協力をよろしくお願いしたい。 昨日、今年度の新1年生保護者説明会の概要を「学校からのお知らせ」ページにアップしたので、来年度本校にお子様を入学させる保護者の皆様は、そちらもご覧いただきたい。 1/15 短縄旬間

今年度から短縄旬間の取り組み方を変更した。リズム縄跳びで順番に短縄の技に取り組むのではなく、なわとびカードから、自分がチャレンジしたい技に挑戦することにした。「技を選ぶ」ことで、主体的に取り組むようなることを狙っての変更だった。子どもたちは、ぞれぞれなわとびカードから跳べそうな技から選んで挑戦しているようだ。そこから始まり、できてきたらできない技にも挑戦するようになるといい。 小学校の時期の子どもたちは、体力面で「筋力」や「持久力」よりも「巧緻性」と言われる、いわゆる技能やテクニックが伸びる時期である。なわとびは、ぴったりな運動である。短縄旬間は2月2日(火)まで3週間行う。各ご家庭でも励ましの言葉をかけてあげていただきたい。 1/14 3学期のめあて





その後、校内を回ると「3学期のめあて」を立ててめあてカードに書いているクラスが何クラスもあった。 めあてを立てるのはとても大事なことである。さらにそのめあてを忘れずにめあて達成に向けて努力することが、さらに大事である。そのためにクラスによっては、めあての振り返りを時々行ってくれているクラスもある。ありがたいことである。 子どもたちには、ぜひ立てた目標を達成してほしい。3学期は短い。あっという間に過ぎていくので、目標多勢英に向けて日々努力していってほしい。各ご家庭でも、子どもたちがどんなめあてを立てたのか、ぜひ聞いていただきたい。 |
小平市立小平第十二小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |