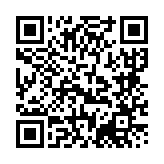|
最新更新日:2024/06/14 |
|
本日: 昨日:73 総数:284072 |
2/10 全校朝会の話 協力
おはようございます。
2月は「ふれあい月間」です。皆さんは、「いじめは絶対しない。」「暴力をふるわない。」ということを今月は特に意識して毎日を過ごしてください。 先週、「えがおまつり」がありました。どのクラスも楽しいお店を出して、お客さんを楽しませてくれました。先生は、「えがおまつり」当日まで、各クラスでの準備の様子を見てきました。皆さんは、お客さんを楽しませるお店にするために、よく考えて話し合っていました。また、友達と「協力」して、お店の準備もしていました。そして、「えがおまつり」当日も「協力」して頑張り、お客さんを楽しませてくれました。 「えがおまつり」の取組を通して、皆さんは「友達と協力する大切さ」を改めて感じ、「クラスの絆」を深めることができたと思います。この「えがおまつり」の経験をこれからの生活に、ぜひ生かしてください。3学期も後半に入ります。今のクラスで生活できるのも、残りひと月半です。これからも、クラスの友達と協力して生活し、たくさんの思い出を作って、絆を深めてください。そういうクラスでは、絶対にいじめも起きません。そんなクラスを最後まで目指してください。 これで校長先生の話を終わります。 以 上 <先生方へ> ○ 「えがおまつり」の取組ありがとうございました。特に6年生は、卒業へ向けての準備と並行しての活動でしたが、最後まで立派に取り組むことができました。「えがおまつり」を通して、子どもたちは成長しました。今年度も残りひと月半です。最後まで、子どもたちやクラスのいろいろな力を伸ばしていってください。 〇 「えがおまつり」を協力して取り組んできたことは大きな財産です。この経験を生かして、これからも協力していろいろな活動をしたり生活したりする意識を高めましょう。そして、今のクラスでの思い出もたくさん作りましょう。同時に、5年生が次の「十二小の顔」になるように、他の学年も次の学年に向けた子どもたちの意識も高めていきましょう。 ○ 2月は、今年度最後の「ふれあい月間」です。いつも以上に「いじめゼロ」を目指しましょう。いじめの未然防止のためには、子どもたちの言動に注意を払い、些細なことでも見逃さないことが大事です。さらに、いじめが発生した場合は、早期発見・早期対応に努めましょう。そして組織的に対応していきましょう。また、「体罰ゼロ」も目指しましょう。教師の言動にも十分に注意をして「不適切な指導」もないようにしましょう。 以 上 2/7 保健委員会集会





心の健康を保つために大事なことについて寸劇やクイズで、全校児童に教えてくれた。また、簡単にできるリラックス体操も教えてくれた。見ていた子どもたちもよく話を聞き、寸劇での楽しい場面では、笑いも起こった。またリラックス体操は全校で一緒にやってみた。 とても楽しく、そして、ためになる集会だった。子どもたちはいろいろなストレスをためている。それをなるべく減らしてあげたい。子どもたちも対処法が分かったことだろう。とてもいい集会を開いてくれた保健委員会の子どもたちに感謝である。 2/6 小平駅伝





前任校から毎年参加し8回目の参加となり、毎年タイムは少しずつ落ちてきている。しかし、楽しい。だから来年度も参加したい。今度は教職員だけでなく、保護者や地域の方々とも一緒にチームを組み、地域ぐるみで盛り上がりたい。参加者を募集したい。 2/5 表彰





日本将棋連盟小平支部主催新春将棋大会C級第3位の5年生。 第57回小平市民体育祭フットサル大会少女の部で優秀選手賞を受賞した4年生。 羽村動物園写生コンクールで、それぞれ金賞・銀賞・銅賞・佳作を受賞した1年生4人であった。 子どもたちは、運動面でも文化面でも頑張っている。全校で、大きな拍手で祝福した。 さらに、2日に行われた第40回こだいら市民駅伝大会に参加した教員・事務職員・兆輪・介助員・学生ボランティアの12名(朝会には全員は参加できなかったが。)を表彰した。また、一緒に参加したおやじの会のメンバーも仕事の関係で来られなかったので名前だけ紹介した。表彰の際「校長先生も走りました。頑張りました。」と話すと、子どもたちから驚きの声が上がった。子どもたちから大きな拍手で祝福され嬉しかった。 子どもたち同様、大人も頑張っている。これからも子どもたちと共に、大人の活躍も紹介していきたい。 2/4 2月

2月も見通しをもって何事も計画的に進めるように教職員には話している。教員が忙しくなると子どもたちにも影響があるし、残りひと月半でクラス替えにもなるので、最後まで子どもたちと楽しい毎日を過ごしてほしいと考えているからである。 子どもたちも、2月3月は学年のまとめをしっかりしていってほしい。そして先生や友達とたくさんの思い出を作ってほしい。そのためにも、健康第一である。本校では今のところ大丈夫ではあるが、他校ではインフルエンザも流行している。学校でも気を付けるが、各ご家庭でも子どもたちの体調管理には十分気を付けていただきたい。よろしくお願いしたい。 2/3 全校朝会の話 挑戦
おはようございます。
先週まで3週間、短縄旬間でした。これまでの3週間、体育の時間や休み時間に皆さんが縄跳びに取り組んでいる様子を見ていると、多くの皆さんがどんどん縄跳びの技に挑戦し、いろいろな技ができるようになったことが、よく分かりました。そんなやる気いっぱいの皆さんを見ていて、とても嬉しかったです。 皆さんも経験があると思いますが、できない技に挑戦すると、当然、始めはできません。しかし、そこで諦めずに挑戦するからこそ、できるようになるのです。なかなかできなくても、練習を繰り返し、コツをつかむとできるようになります。諦めないことが大事です。また、友達と一緒に練習することが有効だと分かった子もいると思います。お互いに教え合うことができるし、できる子の跳び方を見て真似することでコツをつかめることもあるからです。 2月は「ふれあい月間」です。「短縄旬間」は終わりましたが、これからも友達と仲よく縄跳びなどで遊びながら、友達と共にいろいろな運動ができるようになるといいと思います。十二小は「子どもたちが元気な学校」を目指しています。寒い日が続きますが、寒さに負けず、毎日体を動かしましょう。そして運動が好きな、元気な子に育ってください。 これで校長先生のお話を終わります。 以 上 <先生方へ> 〇 短縄旬間の取組ありがとうございました。先生方が一緒に縄跳びを跳んだり声掛けしたりしていただいたおかげで、子どもたちもなわとびに意欲的に取り組んだのだと思います。短縄旬間は終わりますが、今回の取組をきっかけにして、今後も子どもたちに、なわとびに取り組ませてください。 ○ 小学校の時期の子どもたちは、体力面では、「筋力」や「持久力」よりも「巧緻性」が大きく伸びます。「巧緻性」とは、「巧みな動き」のことで、例えば、サッカーのリフティングやドリブル、バスケットボールのドリブル、野球のピッチングなどのボールを扱い方、鉄棒や縄跳びなど用具を使った技、ダンスのステップなどもそうです。大人になってからでも筋力や持久力は身につくけれども、大人になってからだと巧緻性を身に付けようと思ってもなかなか身につかない、今のうちにやっておくと大人になってからも巧緻性を発揮できると言われています。ですから縄跳びは、この時期の子どもたちには、たくさんの技に挑戦してほしいと思っています。 ○ 2月「ふれあい月間」に合わせて、友達と一緒に教え合いながらなわとびの練習をするといいことも話しました。実際に友達と一緒に練習することで、上達が早まることは多いです。遊びの中でも「教え合い」ができるように、普段の学習でのペア学習やグループ学習を進めていきましょう。また、体育の授業でもそのような活動を入れていきましょう。そして、今後もお互いを高め合える子どもたちを育てていきましょう。 ○ 学校経営方針の柱の一つが「子どもたちが元気な学校」です。日頃から外遊びを奨励し、先生方自身も子どもたちと一緒に外遊びをしていただいていることに感謝しています。きっと児童理解にも役立っていることと思います。寒い日が続きますが、引き続き外遊びの励行をよろしくお願いします。また、インフルエンザの流行も心配です。手洗いうがい等、子どもたちの体調管理には十分気を付けていきましょう。 以 上 |
小平市立小平第十二小学校
〒187-0032 住所:東京都小平市小川町1丁目464番地 TEL:042-342-1761 FAX:042-342-1760 |