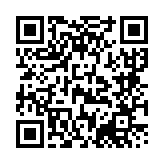|
最新更新日:2024/06/11 |
|
本日: 昨日:56 総数:210785 |
学校経営協議会を行いました!
12月8日(水)
この日、学校経営協議会を開催いたしました。 先に実施した音楽会や五小灯りまつりの報告、各委員さんからのお話の後、事業型コミュニティ・スクールとしての取組について審議しました。 ○地域防災プロジェクト 12月11日(土)の「みんなで防災教室」についての打合せを行いました。 ○地域参画型授業プロジェクト 現在4年生ですすめている、SDGsについての学びとその発表・交流についてご報告し、今後の教育支援について協議しました。 PTA,地域の方々のご支援、ご協力があって五小の教育活動はすすんでいきます。 心から感謝申し上げるとともに、今後もどうぞよろしくお願いいたします。 



研究授業を行いました(さくら学級)(2)
12月6日(月)
さくら学級では、国語としての基礎的な力を付けるだけでなく、自分の考えをもつことや、考えを表現する力を大切しています。 一人一人の個に応じた目標と課題を設定し、個に合わせたワークシートなどを活用しながら、どの子も「できた」という実感がもてるようにしていきました。 画像は、4組(「のらねこ大調査」) 5組(「山小屋で3日間過ごすなら」) の様子です。 



研究授業を行いました(さくら学級)(1)
12月6日(月)
本校では、 自分の考えを広げ深める児童の育成 〜「対話的な学び」を軸としたICT活用授業づくり〜 のテーマの下、各学年、さくら学級、専科でよりよい授業作りを追究しています。 さくら学級では、1学期から1人1台端末を学びに取り入れてきました。 植物の生長の様子の観察では、画像を撮影してそれを共有し合い、気が付いたことをモニターに映して発表し合ったり、一人一人に合わせた課題に取り組んだり、タイピングの練習をしたり、まさに文房具としての活用が当たり前になっています。 この日の授業は、習熟度別5展開で国語の学習を行いました。 画像は、1組(言葉集め) 2組(たぬきの糸車) 3組(伝えたいことを決めて発表する「花丸ぷれぜんたーになろう」) の様子です。 





12月8日(水)のこんだて



3年灯りまつり・・・続き・・・
12月7日(火)
先日、灯りまつりを大成功に終えた3年生ですが、この学びを通して、この灯りまつりのことや地域のこと、地域の方々のことをもっと知りたいという気持ちが高まっています。 この日は、青少対会長の小林様に子どもたちが、インタビューしました。 ご多用な中、快く応じていただいた小林様、本当にありがとうございました。、 

12月7日(火)のこんだて

今日のお昼の放送では、梅室さんから五小の皆さんへのメッセージ動画を放送しました。 梅室さんは、いつも地場産野菜を育てて届けてくださっている農家さんです。 今日は赤かぶを届けてくださいました。 動画を見て、五小の子どもたちは「今食べている赤かぶは梅室さんが育ててくれたもの」というように食べ物と生産者の方がつながったのではないかなと思います。 

12月6日(月)のこんだて



12月3日(金)のこんだて



「東京学芸大学教育フォーラム」で、小林先生が発表しました!
先月28日(日)に、東京学芸大学で、「『教育フォーラム2021』GIGA時代の学びに向けて」が行われました。これは、2008年から実施されていて、今回が第14回目になります。
この研究フォーラムに本校から小林信輔教諭が発表者として参加しました。 自分の考えを広げ深める児童の育成 〜「対話的な学び」を軸としたICT活用授業づくり〜 と題して、本校が本年度推進している教育実践について、とても分かりやすく発表しました。 





馬場喜久雄先生の道徳授業
少し前になってしまいますが、
先月の11日に、元全国小学校道徳教育研究会会長の馬場喜久雄先生を本校にお迎えして、4年生と6年生で道徳の授業を行っていただきました。 親切で行ったことが相手には伝わらず、ありがた迷惑になってしまったり、会いたい人に会いたい心と、相手の命を思う心との葛藤が起きたりすることが、コロナ禍において実施に起きています。こうした葛藤や心のすれ違いを入り口にして、 4年生では、ルールについて、 6年生では、偏見や差別について 考えました。 同じ題材を使っても、子どもが考えを深める内容は決して同じになるとは限りません。そこで大切なのは、教師の発問です。両方の授業を拝見させていただいて、心を耕す題材と教師の発問の大切さを改めて感じました。 





4年紙漉き体験(2日目)
12月3日(金)
4年生の紙漉き体験の2日目です。 2日間かけて、3学級の児童が紙漉きを行いました。 そして、午後は田村師匠への質問会です。 「どうして和紙作りを志したのですか?」 「和紙を作っていて一番楽しかったことは何ですか?」 など、紙漉きの技術的なことだけではなく、生き方に迫る質問も多くされました。 手漉きの和紙は、原料を流し込む型が決まっているので、和紙の大きさも大体決まってきてしまうのですが、特注の特大和紙もあり、その和紙も見せていただきました(画像)。最後には、特大和紙に書かれたサトウハチローさんの 「美しく自分を染め上げてください」 の詩を全員で音読しました。 ”美しく自分を染め上げてください” 赤ちゃんのときは白 誰でも白 どんな人でも白 からだや心が そだっていくのといっしょに その白を 美しく染めていく 染めあげていく 毎朝 目がさめたら きょうも一日 ウソのない生活を おくりたいと祈る 夜 眠るときに ふりかえって その通りだったらありがとうとつぶやく ひとにはやさしく 自分にはきびしく これをつづけると 白はすばらしい色になる ひとをいたわり 自分をきたえる これが重なると 輝きのある色になる なにもかも忘れて ひとのために働く 汗はキモチよく蒸発し くたびれも よろこびとなる こんな日のひぐれには 母の言葉が耳にすきとおり 父の顔が目の中で ゴムマリみたいに はずむ 生まれてきたからには よき方向へすすめ からだや心を大きくするには よき道をえらべ 横道はごめんだ おことわりだ いそがずに ちゃくちゃくと 自分で自分を 美しく より美しく 染めあげて下さい サトウハチロー 





歩道橋工事に伴う朝の見守り
12月3日(金)
歩道橋の工事に伴う閉鎖で、横断歩道を使って小金井街道を渡らなければならなくなりました。今日で5日目です。 今朝は、小平警察署の方が安全の見守りに立ってくださいました。 「登校する児童が通ります!自転車の方はスピードを緩めてください!」 と、メガホンで丁寧に呼びかけてくださる姿に、とても頼もしさを感じました。 と、同時に、交通安全のゼッケンや旗、「五小パトロール」のピンクのネームプレートを付けた人が立つことで、地域の方々が、 「ああ、この時間は今こういう状態になっているのだな!」 と認識してくれて、これまでより意識的に安全に気を配ってくれるようになるといいと感じています。 今朝も、青少対、PTAの皆さんが要所要所に立って児童の安全の見守りをしてくださいました。小平警察の方、青少対、PTAの皆様、本当にありがとうございます。 





12月2日(木)のこんだて



12月1日(水)のこんだて



4年紙すき体験(1日目)(2)
12月2日(木)
紙漉き体験の様子です。 「弁慶が、五条の橋を渡るとき・・・うんとこどっこいしょ!」 と、紙漉きの歌を歌いながら、楮を叩いて繊維をほぐしていきました。 





4年紙すき体験(1日目)
12月2日(木)
毎年紙漉き職人の田村正さんを講師にお迎えして、4年生の紙漉き体験を行っています。紙漉き体験は、様々なところで行われていますが、この学習はただ紙を漉くだけではありません。材料の楮(こうぞ)の繊維を叩いたり、塵をとったりといった一つ一つの工程を大切に手作りの和紙作りを体験していきます。併せて、師から弟子へ技を伝授するというコンセプトで、真剣勝負で作業を進めていきます。師匠である田村さんと子どもたちの関わりの中で生まれる「人から真剣に学ぶ」姿勢もこの学びの中でとても大切な要素です。 アシスタントは、同じく和紙職人の北村春香さんです。 画像:和紙作りに必要な道具や材料を力を合わせて運ぶところから学習は始まります。 楮の繊維を叩いたり、塵をとったり、紙を漉いたりしている様子です。 





11月30日(火)のこんだて

4年生は、総合的な学習の時間にSDGsについての取組を進めています。 今日の「胡瓜とめかぶの梅おかか和え」は、食品ロスに取り組んでいるグループの皆さんが考えてくれた料理です。 梅干しの酸っぱさは、まだ難しい子もいるかもしれませんが、日本を代表する漬物のひとつです。旨味のある おかかと一緒に和えることで、爽やかな酸味や香りを楽しめる料理になります。 

歩道橋工事に伴う朝の見守り
12月2日(木)
歩道橋に足場が組まれたので、児童が通るところが正門に向かって右側になりました。 コーンを置いて道を作ってくださったのは、工事関係の皆さんです。今朝も、PTAや青少対の皆さんが交通安全の見守りを行ってくださいました本当にありがとうございます。 





こども食堂
12月1日(水)
こども食堂とは、地域住民や自治体が主体となり、無料または低価格帯で子どもたちに食事を提供するコミュニティの場を指しています。また、単に「子どもたちの食事提供の場」としてだけではなく、帰りが遅い会社員、家事をする時間のない家族などが集まって食事をとることも可能です。このように、「人が多く集まる場所」ができたことで、地域住民のコミュニケーションの場としても機能しているのです。 こども食堂は、民間発の自主的、自発的な取り組みから始まりました。 こども食堂は、東京都大田区にある八百屋の店主が2012年に始めたことがきっかけです。 朝ごはんや晩ごはんを十分に食べることができない子どもたちがいることを知った八百屋の店主が、自ら始めたのです。 その活動を知った東京都豊島区の子ども支援をしていた団体のメンバーが活動に取り入れたことで、瞬く間に全国に活動の輪が広がっていきました。 (出典:全国移住ナビ公式サイト「そもそも子ども食堂って?」) 小平市でも、「カモミール子ども食堂」がその担い手として活動を続けていただいています。代表は、元本校調理員の田中貴子さんです。小平市の実態として、貧困家庭、一人暮らし、特に一人暮らしの高齢者が主な利用者だそうです。「一人も取り残さない」というSDGsの理念そのものですね。 この日は(12/1)に花小金井地区で初の子ども食堂が行われました。 場所は、花小金井南公民館です。 17:30〜 無くなり次第終了 お弁当を配布するという形で実施しました。ちなみに、 子ども無料 大人300円です。 お弁当だけでなく、有志の方からのミカンや、お子様向けゼリー、文房具等のプレゼントもありました。 ちょうどSDGsの学習をすすめていることもあり、五小からも保護者、児童、教職員が何人か参加させていただきました。素晴らしい取組、本当にありがとうございます。 





歩道橋工事に伴う朝の見守り
12月1日(水)
今週月曜日から、小金井街道にかかる五小正門前の歩道橋の工事が始まりました。工期は3月半ばまでと伺っています。 どうしても横断歩道を渡らなければいけない児童もとてもたくさんいます。それに対し、登校時間帯には、自転車等で駅に向かう人の流れがとても多くなります。安全のために警備員もついてくださるのですが、より安全を期すために、PTAと青少対の皆様に応援をお願いしました。 PTA並びに青少対、地域の皆様、本当にありがとうございます。 





|
小平市立小平第五小学校
〒187-0002 住所:東京都小平市花小金井6丁目24番1号 TEL:042-461-9300 FAX:042-461-9423 |